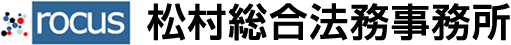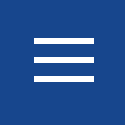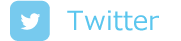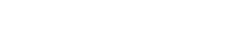判例集2017.02.15
DNA鑑定に関する裁判例1(民事)
判例集2017.02.15
親子関係不存在確認等請求控訴事件(東京高等裁判所判決平成22年9月6日判決)
判決要旨
産院で取り違えられ,生物学的な親子関係がない夫婦の実子として戸籍に記載され,長期間にわたり実の親子と同様の生活実体を形成してきた兄に対して,両親の死後,遺産争いを直接の契機として,戸籍上の弟らがDNA鑑定による兄弟関係の不存在をもとに提起した親子関係不存在確認請求が,権利の濫用に当たるとされた事例
主文
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人らの請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は、第1、2審を通じて、被控訴人らの負担とする。
事実及び理由
第1 控訴の趣旨 主文1項、2項と同旨
第2 事案の概要 本件は、甲野太郎(本籍・《略》、以下「太郎」という。)とその妻である甲野花子(本籍同上、以下「花子」という。)との間の長男として戸籍に記載されている控訴人に対し、太郎・花子夫婦の子である被控訴人ら(控訴人の戸籍上の弟たち)が、同夫婦の死後、同夫婦と控訴人との間に親子関係が存在しないことの確認を求めた事案(以下「本件訴訟」という。)である。
1 事実関係
(1) 太郎(大正13年2月8日生)と花子(昭和3年1月1日生)は、昭和27年5月15日、婚姻届出した。
(2) 控訴人は、太郎・花子夫婦の長男として、昭和28年3月30日に出生した旨戸籍に記載されている。
(3) 控訴人は、太郎・花子夫婦の長男として養育され、大学を卒業した後、会社勤めをし、30歳で妻松子と結婚して、両者間には長女竹子(平成元年4月25日生)、2女梅子(平成3年4月28日生)が生まれた。控訴人は、上記会社に20年ほど勤めた後、退職して、10年ほど太郎の不動産業を手伝ったが、その後、独立した。
(4) 被控訴人甲野二郎(昭和29年4月13日生、以下「被控訴人二郎」という。)、被控訴人甲野三郎(昭和31年4月1日生、以下「被控訴人三郎」という。)及び被控訴人甲野四郎(昭和33年1月16日生、以下「被控訴人四郎」という。)は、いずれも太郎・花子夫婦の子である。
(5) 花子は、平成11年4月2日に死亡した。
(6) 花子の遺産については、既に遺産分割が終わり、控訴人は、現在の居住建物の敷地所有権を始めとする相続財産を取得した。
(7) 太郎は、控訴人及び被控訴人らに対しそれぞれ不動産や預貯金等を相続させる旨の公正証書遺言(以下「公正証書遺言」という。)をした。これにより控訴人が取得する財産は、千葉県船橋市にある土地建物(以下「船橋の家」という。)等である。
(8) 太郎は、平成19年10月7日に死亡した。これにより、公正証書遺言の効力が発生した。
(9) 被控訴人らは、平成20年7月2日、控訴人に対し本件訴訟を提起した。
(10) 被控訴人らは、原審において、控訴人と被控訴人らとの間に両親を同じくする兄弟関係があるか否かのDNA鑑定(以下「本件DNA鑑定」という。)を申し立て、控訴人は、本件DNA鑑定の採用を争わず、本件DNA鑑定は採用された。
(11) 本件DNA鑑定において、控訴人と被控訴人らとの間には、生物学的な父を同じくする兄弟関係、生物学的な母を同じくする兄弟関係いずれも存在しない旨のDNA鑑定結果が得られた。
(12) 原審は、平成21年6月11日、本件DNA鑑定の結果に基づいて、控訴人と太郎、控訴人と花子の間にはいずれも親子関係が存在しないことを確認する判決を言い渡した。
(13) 控訴人は、原判決を不服として、控訴を提起した。
2 争点
本件訴訟の争点は、被控訴人らの本件請求が権利の濫用に当たるか否かである。
(1) 控訴人の主張
ア 控訴人の出生から太郎・花子夫婦の死亡まで50年間前後にわたり、同夫婦と控訴人との間には実の親子と同様の生活の実体があった。 控訴人は、新生児であった当時、花子が出産した乙山病院(東京都《略》所在)で太郎・花子夫婦の実子と取り違えられたものと思われるが、太郎・花子夫婦は、そのようなことは全く知らないまま、控訴人を実子と信じて1生を終えた。控訴人も、本件DNA鑑定の結果が出るまで、同夫婦との間に親子関係がないなどとは、夢にも思わなかった。そのため、控訴人は同夫婦の実子であることを証明しようとして、本件DNA鑑定を受けた。
イ しかし、本件DNA鑑定が控訴人の予想外の結果になったため、控訴人は激しいショックを受けており、それはいまだに癒えていない。まして、控訴人と太郎・花子夫婦との間の親子関係の不存在を確認する原判決が確定すれば、控訴人がさらに著しい精神的苦痛を受けることは必定である。加えて、控訴人の家族の社会生活に与える影響も極めて大きく、ことに長女竹子(平成元年4月25日生)、2女梅子(平成3年4月28日生)の就職、結婚などに重大な不利益が想定される。
ウ 太郎・花子夫婦が生存していれば、控訴人を見捨てることなく、養子縁組をしてくれたはずである。しかし、同夫婦はいずれも既に死亡しており、養子縁組をすることは不可能である。
エ 控訴人と太郎・花子夫婦との間の親子関係の不存在を確認する原判決が確定すれば、控訴人は、太郎及び花子の相続人の地位を失う。しかし、控訴人は、花子から相続した土地上に自宅建物を建てて家族と共に居住していることを始め、遺産分割により取得した花子の相続財産(現金約500万円、上記土地3000万円相当)を基礎として生活を営んできており、これを不当利得として返還しなければならなくなると、控訴人の経済的不利益は極めて大きい。
オ 太郎は公正証書遺言を残して死亡したが、被控訴人らは、花子の遺産分割において控訴人が法定相続分を大きく超える相続財産を取得したとして、太郎の遺産分割においては、公正証書遺言の内容と異なる分割を主張した。そして、被控訴人らは、平成20年5月ころ、控訴人に対し、太郎の遺産分割につき分割案を示したが、この案では控訴人の取得分が太郎の公正証書遺言の内容よりも少なくなっていたので、控訴人がこの案を拒絶したところ、その後まもなく、被控訴人らが本件訴訟を提起した。すなわち、被控訴人らは、太郎の遺産分割を有利に進めることを目的として本件訴訟を提起したのである。そして、被控訴人らは、本件請求が認容されれば、財産的利得を得ることになるが、認容されなくても、格別不利益な状態は生じないのである。
カ 最高裁平成17年(受)第833号、同第1708号各平成18年7月7日第2小法廷判決(民集60巻6号2307頁、裁判集民事220号673頁)は、親子関係不存在確認請求について権利濫用を認めており、本件訴訟でも同様に権利濫用が認められるベきである。
(2) 被控訴人らの反論
ア 民法は、親子関係につき血縁主義の原則に基づくものであり、これが戸籍に正しく表示されることが、身分的法律関係の基礎となる。被控訴人らは、自然的血縁関係の不存在であることを理由に、本件請求をしているものであり、これが濫用とされるいわれはない。
イ 権利濫用を肯定した2件の最高裁平成18年7月7日判決は、いわゆる「藁の上からの養子」の事案であって、戸籍上の親の側に虚偽の戸籍作出につき帰責事由が認められる事案である。しかし、濫用は極めて例外的にしか認められるべきでなく、そもそも、本件は、戸籍上の親の側に何ら帰責事由や禁反言の事情は存在せず、上記判例の射程距離外にある。
ウ 花子は、生前、控訴人が病院で生まれたとき、花子が用意した産着と異なる粗末な産着を着せられて、花子のもとに連れられてきたという話を繰り返し語っていた。花子は、産着が異なることから、病院での新生児取り違えを察知し、控訴人が実子でないことを推察していたものである。 花子が、控訴人に対し親子関係不存在確認請求訴訟の提起等をしなかったのは、そのような手続を知らなかったからにすぎず、繰り返し産着の話をしていたのは、被控訴人らに対し、その疑念を晴らしてほしいという意思を伝えていたものである。
エ 控訴人は、花子の死後、老齢の太郎に対し冷たい態度を取ったばかりか、被控訴人らに対しても冷たい態度を取ってきており、甲野家の長男としてふさわしくない。花子の遺産分割の際、控訴人が、脳梗塞で認知症になった太郎の在宅介護を引き受けると言うので、被控訴人らが、控訴人に花子の遺産の大半を取得させたにもかかわらず、控訴人は太郎を老人施設に入所させようとし、これに反対して在宅介護を始めた被控訴人らに協力することを拒絶し、その後、被控訴人らの要求により在宅介護を分担するようになった後も、十分な介護をしなかった。被控訴人らは、それ以前、花子から産着の話を聞いてもまさかと思っていたが、控訴人が太郎に対しあまりに冷たいのを見て、本当に血のつながりがないから、これほど冷たいのではないかと思うようになった。被控訴人三郎は、当時、北海道で勤務していたが、介護のため転勤を希望し、太郎・花子夫婦がときどき使用していた船橋の家に転居して、兄弟と共に太郎の在宅介護に当たり、太郎の死後も船橋の家に居住している。控訴人は、太郎の公正証書遺言に船橋の家は控訴人に相続させると記載されていることを楯にとって、当初、被控訴人三郎に対し船橋の家の明渡しを求めると解される態度を取り、当審に至っても、上記家の時価による買取り又は賃借を求める等述べているのである(乙6、7)。
オ 控訴人が被害と主張する精神的苦痛は、事柄の性質上甘受すべきものであるし、経済的不利益を被ることも法的な効果にほかならないから、やむを得ないものである。被控訴人らがその反面において財産的利得を得ることも本来あるべき状態になるにすぎず、何ら問題というべきではない。
3 裁判所の判断
1 原審におけるDNA鑑定の結果によれば、控訴人と太郎との間には生物学的な父子関係が存在せず、控訴人と花子との間には生物学的な母子関係が存在しないことが認められる。
そうであるのに、控訴人がいかにして太郎・花子夫婦の実子として戸籍に記載され、養育されるに至ったのかは必ずしも明らかとはいえない。しかし、弁論の全趣旨によれば、控訴人の実母と花子が同じ病院で、同じ日又は極めて近接した日に出産し、出生後まもない控訴人と花子の産んだ子とが何らかの事情で取り違えられ、そのことに気付くことのないまま、太郎・花子夫婦は控訴人を実子として出生届出をし、実子として養育するに至ったものと推認される。このことは驚くべき事態というべきであるが、太郎・花子夫婦はもとより、控訴人もこれにつき何の責任もないのである。関係者にとっては、他に例をみることの極めて稀な悲劇であり、当裁判所としても、法的評価、判断は別として、まことに同情を禁じ得ない。
2 当裁判所は、わが民法が血縁主義の原則を採用し、これは国民の法的確信を基礎としていることを前提の認識としつつ、権利の濫用が禁じられることも民法の原則(民法1条3項)であることに思いを致し、親子関係存否確認の請求についても、権利濫用禁止の法理が妥当する場合があるものと解する。そして、本件については、被控訴人らの親子関係不存在確認請求は、権利の濫用に当たり、理由がないものと判断する。その理由は、次のとおりである。
(1) 親子関係存否確認訴訟は、親子関係という血縁に基づく基本的親族関係の存否について関係者間に紛争がある場合に対世的効力を有する判決をもって画一的確定を図り、これにより親子関係を公証する戸籍の記載の正確性を確保する機能を有するものであるから、真実の親子関係と戸籍の記載が異なる場合には、親子関係が存在しないことの確認を求めることができるのが原則である。
しかしながら、このような血縁主義の原則及びこれを具体化した戸籍の記載の正確性の要請等が例外を認めないものではないことは、民法が一定の場合に、戸籍の記載を真実の実親子関係と合致させることについて制限を設けていること(776条、777条、782条、783条、785条)などから明らかである。
真実の親子関係と異なる出生の届出に基づき戸籍上甲乙夫婦の嫡出子として記載されている丙が、甲乙夫婦との間で長期間にわたり実の親子と同様に生活し、関係者もこれを前提として社会生活上の関係を形成してきた場合において、実親子関係が存在しないことを判決で確定するときは、事実に反する届出について何ら帰責事由のない丙に軽視し得ない精神的苦痛、経済的不利益を強いることになるばかりか、関係者間に形成された社会的秩序が一挙に破壊されることにもなりかねない。
そして、甲乙夫婦が既に死亡しているときには、丙は甲乙夫婦と改めて養子縁組の届出をする手続を採って同夫婦の嫡出子の身分を取得することもできない。そこで、戸籍上の両親以外の第三者である丁が甲乙夫婦とその戸籍上の子である丙との間の実親子関係が存在しないことの確認を求めている場合においては、甲乙夫婦と丙との間に実の親子と同様の生活の実体があった期間の長さ、判決をもって実親子関係の不存在を確定することにより丙及びその関係者の被る精神的苦痛、経済的不利益、改めて養子縁組の届出をすることにより丙が甲乙夫婦の嫡出子としての身分を取得する可能性の有無、丁が実親子関係の不存在確認請求をするに至った経緯及び請求をする動機、目的、実親子関係が存在しないことが確定されないとした場合に丁以外に著しい不利益を受ける者の有無等の諸般の事情を考慮し、実親子関係の不存在を確定することが著しく不当な結果をもたらすものといえるときには、当該確認請求は権利の濫用に当たり許されないものというべきである(最高裁平成17年(受)第833号平成18年7月7日第2小法廷判決・民集60巻6号2307頁)。
(2) 本件においては、次の事情があることが認められる。
ア 控訴人は、昭和28年3月30日又はこれに極めて近接した日に、乙山病院(東京都《略》所在)で出生し、同病院において、花子が産んだ太郎・花子夫婦の実子(長男)と取り違えられ、以後、太郎・花子夫婦により同夫婦の実子(長男)として養育された。控訴人は、同夫婦の下で、大学を卒業後、製版会社に就職し、30歳で妻松子と結婚した。控訴人と松子との間には、長女竹子(平成元年4月25日生)と2女梅子(平成3年4月28日生)が生まれている。そして、控訴人は、上記会社に20年ほど勤めた後、退職して、10年ほど太郎の不動産業を手伝ったが、その後、独立した。その後も、控訴人と太郎・花子夫婦との間には、花子が平成11年4月2日に、太郎が平成19年10月7日にそれぞれ死亡するまで、実の親子と同様の生活の実体があった。その年数は、花子について約46年、太郎について約54年半もの長きに及んでいる(乙1、控訴人)。 被控訴人らは、控訴人が、花子の死後、介護を必要とする太郎に冷たい態度を取ったと主張する。しかし、老親の介護に対する態度が冷淡かどうかは主観的な評価に係るものである上、そうした態度を取る実子は、世上しばしば見られるところでもある。したがって、控訴人に太郎の介護につき問題があったとしても、控訴人と太郎・花子夫婦との間に実の親子と同様の生活の実体があったことが否定されるものではない。
イ 太郎・花子夫婦はいずれも、生前、控訴人が同夫婦の実子であることを否定したことはない。もとより、それは、太郎と花子が、控訴人との間に生物学的親子関係(血縁)がないことを知らなかったからであるが、そうであったとしても、関係者間に形成された社会的秩序である親子関係について考えるときには、実子であることが否定されなかったという事実が重視されるべきである。
被控訴人らは、花子が生前、控訴人は、病院で、花子が用意した産着と異なる粗末な産着を着せられて花子のもとに連れて来られたと話していたが、これは、控訴人が自分の子であるかどうか花子が疑念を持っており、その疑念を晴らしてほしいという希望を表明したものであると主張する。しかし、花子が、生前、そのような話をしたとしても、実親が実子について親子関係を否定するような冗談を言うこともままあることであり、花子が、控訴人が実子であることに真に疑念を持って産着の話をしたと認めるべき証拠はなく、そのように推論することもできない。
ウ 控訴人は、本件DNA鑑定前、自分と太郎・花子夫婦との間には親子関係があると確信していたが、本件DNA鑑定により生物学的な親子関係が否定された結果を知り、実に大きなショックを受けている(控訴人)。また、控訴人の出生後50年以上を経過した現在では、控訴人の実父母がだれであるのか、どこにいるのか、今も生存しているのかさえ、調査することが著しく困難であることは明らかである。
したがって、法的な親子関係の不存在を確認した原判決が確定すれば、控訴人は、太郎・花子夫婦との間の親子関係を否定され、かつ、実父母がだれであるのかわからない状態に陥り、控訴人のアイデンティティは、いわば二重の危機にさらされることになる。また、控訴人の実父母が判明しない限り、戸籍上、控訴人の両親の欄は空欄となる(乙5)が、これにより、控訴人本人やその家族が奇異の目で見られ、精神的苦痛を受ける可能性は高いといわざるを得ない。
上記事情に照らせば、判決をもって親子関係の不存在が確定されるとすれば、控訴人の受ける精神的苦痛には著しいものがあると評価すべきである。 なお、被控訴人らは、控訴人が自発的に本件DNA鑑定(DNA鑑定)を受けたにもかかわらず、その結果が出てから権利濫用の主張をすることについて、禁反言であると主張するが、事柄の性質上、これを禁反言として、主張することを禁止することは相当とは解されない。
エ 前記ア、イの事情、前記1の事実関係によれば、太郎・花子夫婦は、その生前、控訴人が実子でないことが判明していれば、控訴人との間で養子縁組をし、控訴人をして法的に同夫婦の子としての地位を取得させた蓋然性が高かったように思われる。しかし、控訴人が太郎・花子夫婦の子でないことが判明したのは、同夫婦がいずれも死亡した後であったから、控訴人が同夫婦と養子縁組をして嫡出子としての身分を取得することは不可能である。
オ 控訴人と太郎・花子夫婦との間に親子関係がないことを確認する判決が確定すれば、控訴人は、太郎、花子の相続人としての地位を失い、既に取得した相続財産は不当利得として返還すべき義務を負う。これは、相続適格を欠くとされることの法的効果であるから、それ自体はやむを得ないことではあるが、具体的にみると次のとおりである。
花子の遺産については、既に遺産分割が終わっており、控訴人は、現在の居住建物の敷地所有権を始めとする相続財産を取得した。しかし、原判決が確定すれば、被控訴人らが上記敷地の所有権を主張して、同敷地についての現在の控訴人名義の所有権移転登記の抹消登記手続を請求したり、控訴人の居住建物を収去して敷地を明け渡すことを請求する等の事態が考えられる。もっとも、居住建物は、控訴人が建築した同人の所有名義のものであるから、その敷地を取得した経緯から、直ちに明け渡すべきであるとの結論に至ることには問題があろう。ただ、いずれにしても、控訴人の被る不利益は重大である。
一方、太郎は公正証書遺言を作成しており、控訴人も被控訴人らと共に受遺者となっているので、これに基づく控訴人の権利が、親子関係の不存在により、直ちに影響を受けることは少ないと考えられるものの、上記遺言の前提事実に関わるとしてその効力が問題とされる余地は十分想定される。また、上記遺言後に太郎が購入した土地があり(弁論の全趣旨)、それについては、親子関係の不存在が確定すれば、控訴人が取得する余地はない。この点についても、控訴人は不利益を被ることになる。
以上のとおり、親子関係不存在を確認する判決が確定すれば、それによる法的効果ではあるにしても、控訴人は、少なからぬ不利益を被る結果となる。
カ 被控訴人らは、平成20年5月ころ、控訴人に対し、公正証書遺言の内容とは異なる太郎の遺産分割案を提示した。しかし、控訴人は、これを不満として公正証書遺言のとおりにするよう求め、被控訴人らの案を拒絶したところ、その約1か月後、被控訴人らが本件訴訟を提起した。被控訴人三郎本人尋問においても、被控訴人三郎は、控訴人代理人弁護士の「今回の相続の話もあって訴訟提起に至っているわけですけれども、……(中略)……もしもあなたの思いどおりの要望で1郎さんが分かったという話だったら、この訴えって起きてましたか。」との質問に対して、「起きてませんよ。」と答えている。被控訴人らが、本件訴訟を提起した動機、目的には、もちろん身分関係を正したいとの思いがあると解されるが、以上の経過からすると、それと同時に、あるいはそれよりも少なからぬ比重で遺産分割を有利に展開する意図があったと評価すベきところである。 被控訴人らは、本件訴訟提起の動機、目的は遺産分割にあるのではなく、根底に控訴人の太郎に対する冷たい態度による控訴人と被控訴人らとの間の不和があったと主張する。しかし、被控訴人らの主張によれば、例えば、花子の遺産分割の際、控訴人が太郎の在宅介護をすると言うので、控訴人に花子の遺産の大半を取得させたにもかかわらず、控訴人は太郎の在宅介護をせず、老人施設に入れようとしたため、被控訴人らが共同して在宅介護をしたが、控訴人は十分な協力をしなかったというのであるから、太郎の介護をめぐる兄弟間の不和といっても、結局は、財産的問題である遺産分割が大きく関わっているということができる。 もっとも、《証拠略》によれば、公正証書遺言では、船橋の家は控訴人が取得するところ、控訴人は、北海道から転勤してきて船橋の家に住み、兄弟と共に太郎の在宅介護をし、太郎の死後も船橋の家を生活の本拠として居住し続けている被控訴人三郎に対し、当初、被控訴人三郎が控訴人から船橋の家の明渡しを求められると心配するような態度を示し(被控訴人三郎)、当審においても、船橋の家の時価による買取り又は賃借を求める態度(乙6、7)を示した(もっとも、その後、控訴人の態度はより柔軟になっている。)。このような控訴人の態度が、利己的な冷たい態度として、被控訴人らの反感を買ったことは想像に難くないが、親子関係不存在確認請求の動機、目的としては必ずしも相当とはいえない。 そうすると、被控訴人らの親子関係不存在確認請求が認められない場合、被控訴人らは、法的には遺産相続上の不利益を受け、これは少なからぬ不利益ではあるが、著しい不利益と評するには躊躇を覚える。また、実際にも、控訴人が謙抑的対応をすることにより、事実上、被控訴人らの被る不利益を減少させることは可能でもある。
(3) 以上のとおり、控訴人と太郎・花子夫婦との間で長期間にわたり実の親子と同様の生活の実体があったこと、太郎と花子はいずれも既に死亡しており、控訴人が太郎・花子夫婦との間で養子縁組をすることがもはや不可能であること、親子関係の不存在が確認された場合、控訴人が受ける重大な精神的苦痛及び少なからぬ経済的不利益、被控訴人らと控訴人の関係、被控訴人らが控訴人と太郎・花子夫婦との親子関係の不存在確認請求をするに至った経緯及び請求をする動機、目的、親子関係が存在しないことが確認されない場合、被控訴人ら以外に不利益を受ける者はいないことなどを考慮すると、被控訴人らの親子関係不存在確認請求は、権利の濫用に当たり許されないというべきである。
以上のように解するのは、病院で取り違えられた控訴人が育ての親と46年から54年もの長きにわたり実の親子と同様の生活実体を形成してきたのにもかかわらず、両親の死後、その遺産争いを直接の契機とし、戸籍上の弟である被控訴人らが本件訴訟を提起したという本件の事実関係における個別性、特殊性に由来するものであることはいうまでもない。
3 なお、当裁判所は、太郎や被控訴人らに対する配慮を欠くと感じられる控訴人の態度が本件訴訟提起の原因の1つにもなっていることを、控訴人としては深く反省すべきであると考えるので付言する。そして、太郎の相続財産については、本件訴訟の判決確定後に再び和解交渉が始まる可能性が高いが、その際には、控訴人は、利己的な態度を取ることなく、花子の遺産分割の内容その他をも考え併せて、謙抑的な立場で太郎の遺産分割協議に臨むことが望まれる。また、控訴人代理人弁護士に対しても、本判決の意のあるところを汲み、控訴人に対し、然るべく助言することを要請しておきたい。
4 結論
以上によれば、被控訴人らの請求はいずれも理由がないから棄却すべきであり、これと異なる原判決は相当でない。
よって、原判決を取り消して、被控訴人らの請求をいずれも棄却することとし、主文のとおり判決する。
(本判決文は、プライバシー保護、読みやすさ等の観点から、一定の編集しておりますので引用の際は、原本をお確かめください。)
松村総合法務事務所
ビザ総合サポートセンター
DNA ローカス大阪オフィス
〒540-0012
大阪市中央区谷町2 丁目5-4
エフベースラドルフ1102
TEL:06-6949-8551
FAX:06-6949-8552