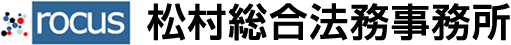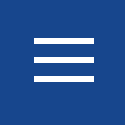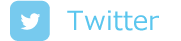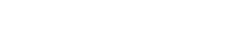判例集2019.02.05
在留資格変更不許可決定等取消請求事件
判例集2019.02.05
名古屋地方裁判所判決平成17年2月17日 判決
主 文
1 本件訴えのうち,被告が平成16年1月16日付けで原告に対してした在留期間の更新を許可しない旨の通知の取消しを求める部分を却下する。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1 当事者の求めた裁判
1 請求の趣旨
(1)被告が平成16年2月3日付けで原告に対してしたビザの変更を許可しない旨の処分を取り消す。
(2)被告が平成16年1月16日付けで原告に対してした在留期間の更新を許可しない旨の通知を取り消す。
(3)用は被告の負担とする。
2 被告の答弁
主文同旨
第2 事案の概要
本件は,出入国管理及び難民認定法(以下「法」ともいう。)2条の2第2項を受けた別表第1の2に定める「技能」のビザをもって本邦に在留していた原告が,在留期間の更新を申請したところ,被告から申請どおりの内容では許可できない旨の通知(以下「本件不更新通知」という。)を受けたため,出国準備を目的とするビザに変更することを内容とする申請内容変更申出書を提出し,これによって被告からビザを「特定活動(5月)」に変更するとの許可を受けたが,その後,ビザを元の「技能」に変更する許可を申請したところ,被告から同申請を許可しない旨の処分(以下「本件在留資格変更不許可処分」という。)を受けたため,選択的に本件不更新通知ないし本件在留資格変更不許可処分の取消しを求めた抗告訴訟である。
1 前提事実(争いのない事実のほか証拠により明らかに認められる事実)
(1)当事者
原告は,1970年(昭和45年)1月5日生まれのインド国籍を有する男性である。
被告は,法69条の2,法施行規則(以下「規則」ともいう。)61条の2第6号及び第7号により,法20条3項のビザの変更許可及び法21条3項の在留期間の更新許可についての法務大臣の権限の委任を受けた者である。
(2)原告の入国及びビザ等の経緯
ア 原告は,法務大臣から,ビザ「技能(1年)」とするビザ認定証明書の交付を受け,平成11年12月7日,入国審査官から上陸許可を受けて,成田空港から本邦へ上陸した(乙5)。
イ 原告は,平成12年11月22日,被告に対して,在留期間の更新を申請したところ,被告は,平成13年1月22日,原告に対して,1年の在留期間の更新を許可した(乙5)。
ウ 原告は,同年12月4日,東京入国管理局長野出張所長に対して,在留期間の更新を申請したところ,同所長は,平成14年1月23日,原告に対して,不許可の通知をした。そこで,原告は,同年2月6日,同所長に対し,在留資格変更を申請し,同所長は,同日,原告に対して,ビザを「短期滞在(90日)」へ変更することを許可した(乙5)。
エ その後,原告は,2度にわたり,被告から在留期間(各90日)の更新を受けたが,同年9月3日,東京入国管理局長に対して,ビザの変更を申請し,同局長は,同年10月10日,ビザを「技能(1年)」へ変更することを許可した(乙5)。
(3)被告による処分の経緯
ア 原告は,平成15年9月3日,被告に対して,在留期間の更新の許可を申請した(申請番号名就E-03-19663号。以下「本件更新申請」という。)ところ,被告は,平成16年1月16日,原告が提出した資料等からみて「技能(Skilled Labor)」のビザに該当する活動を行うことに係る十分な立証がなされているとは認められず,在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるとは認められないため,申請どおりの内容では許可できないが,申請内容を出国準備を目的とする申請に変更するのであれば,申請内容変更申出書を提出されたいとの内容の本件不更新通知をした(甲3,乙1,2)。
イ 上記通知を受けた原告は,同日,被告に対して,本件更新申請を「出国準備を目的とするビザの変更許可申請」に変更するとの申請内容変更申出書を提出したところ,被告は,同日,原告のビザを「特定活動(5月)」とする変更許可処分(以下「本件資格変更許可処分」という。)をした(乙6)。
ウ 原告は,平成16年2月2日,被告に対して,ビザを「技能」に変更する旨の申請(以下「本件資格変更申請」という。)をしたところ,被告は,同月3日付けで,これを許可しない旨の本件在留資格変更不許可処分をした(甲1,2,乙7,8)。
2 本件の争点
(1)本案前の争点-本件不更新通知の取消しを求める訴えの利益の有無
(2)本案の争点-本件在留資格変更不許可処分の適法性の有無
3 争点についての当事者の主張
(1)争点(1)(本案前の争点-本件不更新通知の取消しを求める訴えの利益の有無)について
(被告の主張)
ア 訴えの利益の喪失について
行政処分の取消しの訴えは、当該処分により権利又は法律上保護された利益の侵害を受けた者が,その処分の取消しにより上記権利ないし利益を回復することを目的とするものであり,その権利ないし利益の回復可能性が皆無となった場合には,当該処分が取り消されたとしても,もはや権利ないし利益を回復することはできないから,かかる場合には処分取消しの訴えの利益を欠くというべきである(最高裁判所昭和57年4月8日第一小法廷判決・民集36巻4号594頁参照)。
イ 「ビザ」及び「在留期間」の性質
法及び規則によれば,本邦に上陸する外国人は,一定のビザをもって本邦に在留するものとされる(法7条1項2号)が,このビザは,在留期間と一体不可分のものであって,ビザを決定する場合には,必ずそのビザに対応する在留期間が定められることとなっている(法2条の2第1項及び第3項,規則3条及び別表第2,法9条1項及び3項,20条並びに21条)とともに,上陸,在留資格変更,在留期間更新のいずれの許可においても,ビザ,在留期間は1個のみ記載することとされている(法69条,規則7条1項,法20条4項,21条4項)。
そして,既にビザ(及びこれに対応する在留期間)を有する外国人が,在留期間経過後も適法に在留するためには,現に有するビザを変更することなく在留期間の更新を受けるか(法21条),ビザの変更を受ける(法20条)ことが必要とされている。
これらの規定からすれば,法及び規則は,外国人が上陸許可又はビザの変更若しくは在留期間の更新許可を受けて本邦に適法に在留するためには,1個のビザと,それに伴う1個の在留期間が決定されることを必要としており,同時に複数のビザを有したり,終期の異なる数個の在留期間を有することを許容していないものと解される。
ウ 本件不更新通知の取消しの訴えの利益
原告は,本件不更新通知を受けた後,自らの意思をもって,出国のための準備を理由としてビザの変更申請をし,ビザを「特定活動」,在留期間を「5月」とする本件資格変更許可処分を受けているのであるから,原告の最終のビザが「特定活動」,在留期間「5月」であることは明らかである。
そうすると,本件不更新通知後に原告から提出された申請内容変更届出書に基づいて被告がした本件資格変更許可処分により,原告のビザは「特定活動」に変更された以上,現時点で本件不更新通知が取り消されたとしても,原告に対してそれ以前のビザである「技能」としての資格をもって在留期間の更新の許可を受ける余地はないというべきである。
このことは,「現に有するビザを変更すること」のない(法21条1項)在留期間更新の性質からみて明らかであり,かつ,このように解したとしても,原告は,変更されたビザ及び在留期間を前提として,改めて従前のビザへの在留資格変更申請をすることができるのであるから,その利益を不当に害することにはならない。
したがって,原告には本件不更新通知の取消しを求める訴えの利益はない。
(原告の主張)
被告の主張は争う。
被告ないし法務大臣は,在留期間の更新許可申請に対して不許可とした場合に,その申請者から訴訟を起こすなどと苦情を言われると,その申請者が本邦に在留することは「不法滞在」といいながら,それを帳消しにする手法だとして,後日さかのぼって「短期滞在」への在留資格変更許可申請と短期滞在の在留期間更新の許可申請とを出させ,さらに「技能」への在留資格変更の許可申請を出させ,それらを一挙に「許可」することにより,ビザを認めてきた。それを今になって,原告は任意の意思に基づいて出国準備を目的とするビザの変更許可申請に変更するための申請内容変更申出書を提出したと殊更主張するのは,従前と180度異なるものであって,納得できない。
(2)争点(2)(本案の争点-本件在留資格変更不許可処分の適法性の有無)について
(被告の主張)
ア 判断基準
ビザを有する外国人は,その者の有するビザの変更を受けることができるが,法務大臣は,当該外国人が提出した文書により,ビザの変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り,これを許可することができる(法20条1項,3項本文)。すなわち,まず,〔1〕当該外国人がこれから行おうとする活動が,法が定めるビザの類型に該当するか否か(ビザ該当性)を判断し,ビザ該当性が認められる場合には,〔2〕このビザ該当性を除くその他の諸般の事情,すなわち国内の治安と善良な風俗の維持,保健衛生の確保,労働市場の安定などの国益維持,当該外国人の在留中の一切の行状,国内の政治・経済・社会等の諸事情,国際情勢,外交関係,国際礼譲などを考慮した上で,専門的,政治的見地からビザの変更を認めるのが相当であるか否かを判断することになる。
このように,法は,我が国に在留する外国人のビザの変更につき,その許否を法務大臣の裁量にかからしめているのであるが,これは,国際慣習法上,国家は外国人を受入れる義務を負うものではなく,特別の条約がない限り,外国人を自国内に受け入れるか否か,また受け入れる場合にいかなる条件を付すかは,当該国家が自由に決定することができるとされていること,憲法上,外国人は我が国に入国する自由を保障されているものではないことはもちろん,在留の権利等を保障されているものでもないこと(最高裁判所昭和53年10月4日大法廷判決・民集32巻7号1223頁参照)に由来する。したがって,法務大臣の裁量権の行使としてされたビザの変更申請の許否の判断が違法となるのは,被告の第一次的な裁量判断が既に存在することを前提として,上記判断の基礎とされた重要な事実に誤認があるなどにより上記判断が全く事実の基礎を欠くかどうか,又は事実に対する評価が明白に合理性を欠くことなどにより上記判断が社会通念上著しく妥当性を欠いていることが明らかであり,法務大臣に与えられた裁量権の範囲を逸脱し,又はその裁量権を濫用した場合に限られる。
イ 「技能」によって行うことのできる活動
(ア)ビザ相互の調整の問題について
上記(1)でも述べたとおり,法は,外国人が上陸許可又はビザの変更若しくは在留期間の更新を受けて本邦に適法に在留するためには,1個のビザとそれに対応する1個の在留期間が決定されることを必要としており,同時に複数のビザを有することを許容していない。
したがって,外国人が本邦において行おうとする活動が複数のビザの特徴的な活動を含んでいる場合,問題となるビザ相互の調整という問題が生じ得る。そして,このような問題につき,法は一定の場合,調整規定を置いているが,このような規定がない場合には,問題となる活動の性質・性格や,これらを踏まえた相互関係等を勘案し,また,資格外活動許可を受けない限り収入を伴い,又は報酬を受ける資格外活動を行ってはならない旨を定める法19条1項との関係を考慮しつつ,問題となるビザによる活動の範囲を決することとなる。
(イ)「技能」のビザと「投資・経営」のビザの相互関係について
a 「技能」のビザにより許容される活動の範囲
「技能」のビザは,「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動」をいい(法別表第1の2),また,法7条の委任により,ビザについての具体的な審査基準を定めた「出入国及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令」(以下「上陸審査基準」という。)は,「申請人が次のいずれかに該当し,かつ,日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること」とし,そのうちの一つに「1 料理の調理……に係る技能で外国において考案され我が国において特殊なものについて10年以上の実務経験……を有する者で,当該技能を要する業務に従事するもの」とする。
このような法及び規則から把握できる,「技能」のビザに対応する活動の特徴は,長年の実務経験によって習得し得る熟練した技量を必要とする業務に従事する活動である。そして,このような活動の特徴や法19条1項との関係を勘案するならば,「技能」のビザにより許容される活動には,経営判断といった要素を含んだ活動は想定されていないというほかない。
b 「投資・経営」のビザにより許容される活動の範囲
他方,「投資・経営」のビザは,「本邦において貿易その他の事業の経営を開始し……てその経営を行」う等の活動をいい(法別表第1の2),また上陸審査基準は,これにつき「1 申請人が本邦において貿易その他の事業の経営を開始しようとする場合には,次のいずれにも該当していること」とし,その基準として「イ 当該事業を営むための事業所として使用する施設が本邦に確保されていること,ロ 当該事業がその経営又は管理に従事する者以外に2人以上の本邦に居住する者(法別表第1の上欄のビザをもって在留する者を除く。)で,常勤の職員が従事して営まれる規模のものであること」としている。
そして,法や規則から把握できる,ビザ「投資・経営」に対応する活動の特徴は,経営判断を含む事業経営活動であるということができる。
もっとも,経営の実態として中小規模の事業の場合には経営者が経営等の一環として,当該経営に係る業務に従事することはよくみられることを勘案すると,ビザ「投資・経営」に対応する活動には,経営者が当該経営に係る事業活動に従事することも含まれていると解される。
c 小括
そうすると,外国人が飲食店を経営し,かつ,その調理活動にも従事するためには「投資・経営」のビザが必要であり,「技能」のビザではこのような活動を行うことはできない。
ウ 本件在留資格変更不許可処分の適法性
以下に述べるとおり,〔1〕原告のこれまでの在留期間中の活動状況を踏まえると,原告が今後行おうとする活動が事業経営活動に該当するものであることが想定されたことから,「技能」のビザ該当性を認めることができなかったばかりか,〔2〕そもそも,本件資格変更申請当時の原告のビザが出国準備を前提とする「特定活動」であった等の事情から,「ビザの変更を適当と認める相当な理由」を認めるに至らなかった。
(ア)本件不更新通知の経緯
本件更新申請に関する被告担当者の審査において,名古屋市○○区○○○丁目○○番○○号所在のインド料理店「A」(以下「本件店舗」という。)の賃貸借契約書における借主が原告名義であること,原告が平成15年4月21日に名古屋市千種保健所から飲食店営業等の許可を得ていること,上記賃貸借契約における原告の連帯保証人であるB(以下「B」という。),本件店舗の販売促進物品の製作に携わったC(以下「C」という。),及び本件店舗の改装等に携わったS(以下「S」という。)らから,原告は本件店舗を経営しているなどの情報提供を受けたこと,本件更新申請時に提出された原告を被用者とし,同人の実弟であるT又は同人が代表取締役となって設立(平成15年7月14日)された有限会社F(以下「本件会社」という。)を雇用主とする雇用契約書は3通も存在し,それ自体不自然である上に,その作成過程にも疑義があることが明らかとなった。
したがって,被告は,原告のビザが「技能」であるにもかかわらず,原告が本件店舗の経営活動を行っており,それゆえ,今後も本件店舗で原告が行おうとする活動もこれと同様の経営活動であるとみられたことから,法2条の2,別表第1の2のビザ「技能」によって行うことのできる活動(「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動」)に該当するとは認められないと判断して,平成16年1月16日,原告に対して本件不更新通知をしたものである。
エ 本件在留資格変更不許可処分における被告の判断の適法性
上記1(3)イの本件資格変更許可処分の後,原告は,本件店舗において調理師として就業することを理由として,本件資格変更申請をし,理由書や雇用契約書等の資料を提出した。
しかし,これらの資料自体の信用性に疑義があった上,理由書には,原告が本件店舗の経営に関与していることを自認する旨の記載もあり,さらには,Bから提供された同人から原告に対する保証料支払請求事件に関する名古屋簡易裁判所の和解調書の内容は,原告が本件店舗を経営していることと整合していた。
したがって,被告は,原告が従前本件店舗の経営活動に従事していたこと,本件資格変更申請も原告が経営していた本件店舗での就業を理由とするものであることなどの事情から,今後,原告がビザ「技能」に該当する活動を行うと認めるに足りる十分な立証がされているとはいえないと判断した。そして,これに併せて,原告のビザが出国準備のための特定活動という短期期限付きのビザであったことなどを勘案して,被告は,本件在留資格変更不許可処分を行ったものである。
以上によれば,本件在留資格変更不許可処分における被告の判断が全く事実の基礎を欠き,あるいは,社会通念上著しく妥当性を欠くことが明らかであるなど,被告に与えられた裁量権の範囲を逸脱し,又はその裁量権を濫用したとはいえない。
オ 原告の主張に対する反論
なお,原告は,本件店舗の経営は,Tないし本件会社によって行われていたのであって,原告が本件店舗の経営に従事していたのではない旨主張する。
しかし,Tの代行として本件店舗の開業準備行為をする必要があったとしても,原告自身の名義で本件店舗の賃貸借契約を締結したり,飲食店営業等の許可を取る必要はないこと,Bが本件店舗の賃貸借契約の連帯保証人を辞するため新たな連帯保証人を立てる必要が生じた際,原告は賃貸仲介業者に対して本件会社を連帯保証人とすることを提案していること,原告は,元々,Bの経営する店舗を手伝っていたものであるが,本件店舗の賃貸借契約を締結するに当たり,自分の店を持ちたいという希望を表明していたこと,販売促進物の製作や本件店舗の造作・改装等を依頼するに当たって,原告が主体的に関与していること,原告が本件店舗の経営をしていることを隠ぺいするため賃貸借契約書を改ざんしていることなどに照らすと,原告の主張は理由がない。
(原告の主張)
ア 「技能」のビザ該当性
原告は,1980年代の後半からインドにおいてインド料理のコックをしており,「技能」のビザで本邦へ入国した後,平成11年12月から岐阜県○○ 市所在のGにて,平成13年6月から長野県所在のHにて,平成14年8月から東京都港区所在のIにて,それぞれコックとして勤務してきた。
そして,原告は,平成15年7月28日,原告の実弟Tが経営し,インド料理店の経営を主目的とする本件会社に雇用され,本件店舗の料理長兼食品衛生責任者として勤務していたものである。
そうすると,原告について「技能」のビザがあるのは当然のことである。
イ 被告の主張に対する反論
(ア)インド料理店「A」の経営主体について
被告は,本件店舗の賃貸借契約書の借主欄に原告の名前があることなどをあげつらって,「技能」のビザがないと主張する。
しかし,原告は,Tないしは本件会社からの依頼を受け,その資金を使って本件店舗の賃貸借契約を締結するなどの開業準備行為をしたにすぎず,その際,当初は自己の名義で行っていたが,本件会社が設立された後は,同社名義で行ってきた。したがって,これらの開業準備行為は,本件会社の計算に基づき,原告がその業務を先行して行ったものにすぎない。このような活動をしたからといって,技能の資格が消滅するものではない。
(イ)「技能」の資格該当性について
a 「公私の機関との契約に基づいて」という要件について
ビザの一つである「技能」が「公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動」だとしても,「公私の機関との契約に基づいて」いない場合,すなわち個人経営の店舗においてインド料理の調理をする業務に従事する活動が「技能」に該当しないとはいえない。
b 「技能」の資格で行い得る活動について
被告は,インド料理店のコックないしシェフは,「技能」の資格で本邦に在留することが許可されているのであるから,厨房で調理することだけが許され,客から飲食代金を受け取ったり,食材等を注文・購入したり,店舗を賃借したり,内装工事をしたり,飲食店営業許可を受けるような店舗の営業に関する行為は一切許されないと考えているものと思料される。
しかし,日本の飲食店では,調理師が自ら1人だけで,あるいはわずかの従業員を使い,自ら調理業務をこなしながら,店舗の営業に関する行為をしている例が多数ある。インド料理店であっても,同種の規模のものの存在が許されるのであれば,コックが店舗の営業に関する行為をすることは当然であり,何ら違法ではない。被告の本件在留資格変更不許可処分は,非現実的かつ狭あいな考えに基づくものである。
ウ 裁量権の逸脱・濫用
被告は,Bら原告を快く思っていなかった者らの悪意に満ちた誹謗中傷に惑わされ,過去に2度までも「技能」のビザを認められていた原告に対して,本件更新申請を不許可としたもので,他のコック(例えば原告の弟であるT)と全く異なる取扱いをするもので,その裁量権を逸脱し,濫用するものである。
その上で,被告は,原告に対して,ビザを「特定活動」とする申請内容変更申出をそそのかして本件資格変更許可処分をしたものであるが,上述のように,本件更新申請の不許可は裁量権の範囲を著しく逸脱したものであるから,特定活動から技能への本件資格変更申請は,法20条3項ただし書所定の「やむを得ない特別な事情」に基づくものとして,許可されるべきであり,被告がこれを認めないのは裁量権の逸脱・濫用にほかならない。
第3 当裁判所の判断
1 争点(1)(本案前の争点-本件不更新通知の取消しを求める訴えの利益の有無)について
(1)訴えの利益の有無を判断する前提として,本件不更新通知が抗告訴訟の対象となる行政処分性を有するかについて判断するに,一般に,行政処分とは,公権力の主体たる国又は公共団体が行う行為のうち,直接国民の権利義務を形成し,又はその範囲を確定することが法令によって認められているものを指す(行特法1条の処分に関する最高裁判所昭和30年2月24日第一小法廷判決・民集9巻2号217頁,同裁判所昭和39年10月29日第一小法廷判決・民集18巻8号1809頁等参照)ところ,その判断は,必ずしも形式にこだわらず,その内容に即して客観的,実質的になされるべきものである。
ところで,前記第2の1(3)によれば,本件不更新通知は,「申請どおりの内容では許可できません」との文言に続けて,「申請内容を出国準備を目的とする申請に変更するのであれば,別紙の申出書を提出して下さい。」との文言が記載されているところ,ここにいう別紙の申出書とは,新たな申請書ではなく,当初の申請の内容を変更することを示す「申請内容変更申出書」の形式を採用しており,かつ,この「申出」に対する応答として,本件資格変更許可処分が行われた事実が認められ,これらによれば,本件不更新通知は,一見すると,自らの意思で当初の申請を取り下げた上,新たな内容の申請を行うことを勧告ないし促すものにすぎないと見られなくもない。
しかしながら,本件不更新通知は,原告のした本件更新申請に対応したものであると考えられること,その作成主体は被告であって,法21条3項の処分を行う権限を有していること(69条の2,規則61条の2第7号),上記申請を許可できない旨の判断とその理由が確定的に示されていることなどを考慮すると,客観的,実質的には本件更新申請に対する不許可処分とみることができ,したがって,上記の行政処分性を肯認するのが相当である。
(2)そこで訴えの利益の有無について判断するに,一般に,行政処分の取消しの訴えは,当該処分により法律上の権利又は利益の侵害を受けた者が,その処分の取消しにより上記権利ないし利益を回復することを目的とするものである。したがって,当該処分が取り消されたとしても,当該権利ないし利益の回復の可能性が皆無となった場合には,もはや訴えの目的を達成することができないから,かかる場合における処分取消しの訴えは,その利益を欠くというべきである。
そして,法及び規則によれば,本邦に上陸しようとする外国人は,一定のビザを有することの審査を受けなければならず(法7条1項2号),本邦に在留する外国人は,特別の規定がある場合を除き,当該外国人に対する上陸許可若しくは当該外国人が取得し又は変更に係る一定のビザをもって本邦に在留するものとされている(法2条の2第1項)。また,ビザを決定する場合には,必ずそのビザに対応する在留期間が定められることとなっていること(法2条の2第1項及び第3項,規則3条,同別表第2,法9条1項及び3項,20条4項,21条4項),上陸,在留資格変更,在留期間の更新のいずれの許可においても,ビザ,在留期間は,1個のみ記載することとされていること(法69条,規則7条1項,20条6項,21条4項),既にビザ(及びこれに対応する在留期間)を有する外国人が,在留期間経過後も適法に在留するためには,現に有するビザを変更することなく在留期間の更新を受けるか(法21条),又はビザの変更を受ける(法20条)ことを必要とすることなどに照らすと,ビザは,これに対応する在留期間と常に一体不可分に観念されるべきものであることが明らかである。
そうすると,法及び規則は,外国人が上陸許可又はビザの変更若しくは在留期間の更新許可を受けて本邦に適法に在留するためには,1個のビザと,それに対応する1個の在留期間が決定されることを必要としており,同時に複数のビザを有したり,終期の異なる数個の在留期間を有することを許容していないものと解される。
したがって,あるビザに基づいて在留期間更新の申請をした者が,その不許可処分を受けた後,他のビザへの変更許可申請をし,その変更許可処分を受けたときは,後者の処分に重大かつ明白な瑕疵があって無効というべき特段の事情が存しない限り,これと抵触する従前のビザに基づく在留期間更新申請は一応その目的を達したとみなされるべきであり(本邦に在留する外国人は,規則3条,別表第2の定める在留期間内といえども,特定の在留期間の付与を要求する権利を有するものではなく,希望する在留期間を下回る在留期間の更新許可がなされた場合においても,その取消しを求める訴えの利益が存しないことにつき最高裁判所平成8年2月22日第一小法廷判決・集民178号279頁参照),法務大臣もそのような二重のビザを与えることはできない(仮に,法務大臣が,何らかの事情によって,既に有効なビザを与えていることを看過し,二重のビザを与えた場合には,後になされたビザ授与処分が当然無効の瑕疵を帯びるというべきである。)と解される。そうだとすると,仮に,従前の在留期間更新不許可処分が判決によって取り消されたとしても,これによって,同不許可処分後の申請に基づいてされたビザの変更許可処分が当然に違法,無効となると解する根拠はないから,被告としては判決の理由に沿った新たな在留期間更新許可処分をすることができず,従前のビザは完全に失われて復活する余地がないといわざるを得ない。したがって,上記不許可処分を取り消す利益を喪失したというべきである。
この点については,従前の在留期間更新不許可処分が判決によって取り消されれば,行訴法33条1項所定の拘束力の効果として、これと整合しないビザの変更許可処分を取り消すことによって,上記矛盾は解消できるとの見解もある。しかしながら,後者の処分は,前者の処分と相結合して一つの効果の発生を目指すもの,あるいは前者の処分と共に一連の手続を構成し,共通の違法事由を内包するもの,さらには前者の処分と表裏の関係にあるものといったように,前者の処分との間に法律上の牽連関係・依存関係が存在するものではなく,あくまでビザの変更の許可を求める申請に対する応答として行われた別個独立の処分であるから,不整合処分として取消義務の対象となるものとは解し難く,上記の見解は採用できない。
そして,以上のことは,他のビザを取得後に,再度ビザの変更を申し立てたもののこれが許可されなかったため,ビザを失った場合も同様であると解される。
(3)これを本件についてみるに,前記第2の1(3)によれば,原告は,平成15年9月3日,本件更新申請を行ったところ,平成16年1月16日,被告から,申請どおりの内容では許可できないが,申請内容を出国準備を目的とする申請に変更するのであれば,申請内容変更申出書を提出して下さいとの本件不更新通知を受けたこと,そのため,被告に対して,本件更新申請を「出国準備を目的とするビザの変更許可申請」に変更するための申請内容変更申出書を提出したこと,被告は,同日,ビザを「特定活動」,在留期間を「5月」(在留期限は平成16年2月3日)とする本件資格変更許可処分を行ったこと,被告は平成16年2月3日,本件在留資格変更不許可処分をしたこと,以上の事実が認められる。
そうすると,原告のビザは,本件不更新通知後,自らの意思により,「技能」から「特定活動」に変更されたものであり,現時点で本件不更新通知が取り消されたとしても,原告が従前のビザで在留期間の更新の許可を受ける余地はないというべきであるから,本件訴えのうち本件不更新通知の取消しを求める部分は,訴えの利益を欠く不適法なものといわざるを得ない。
(4)なお,原告は,被告(ないし法務大臣)が在留期間の更新不許可処分を行った場合,その申請者から訴訟を起こすなどと言われると,さかのぼって「短期滞在」への在留資格変更許可申請及び「短期滞在」の在留期間更新の許可申請並びに「技能」への在留資格変更の許可申請を提出させ,それらを一挙に「許可」することにより,ビザを認めてきたにもかかわらず,今回の被告の措置は,従前と180度異なるものであって,納得できない旨主張する。原告の上記主張の趣旨は必ずしも明確ではないが,平等原則違反ないし信義則違反を指摘するものと善解することができる。
しかしながら,本件全証拠によっても,被告が殊更原告のみを不利益に取扱い,あるいはその信頼を裏切って,前記本案前の主張をしているとは認められないので,上記主張は採用できない。
2 争点(2)(本案の争点-本件在留資格変更不許可処分の適法性の有無)について
(1)在留資格変更不許可処分の適法性の判断基準
ア 法20条1項は,ビザを有する外国人は,その者の有するビザの変更を受けることができることを定めているところ,同条2項は,手続要件として,当該外国人は,法務省令で定める手続によって,法務大臣(法69条の2,規則61条の2第6号によって,入国管理局長に委任されている。以下,同じ。)に対し,同変更を申請しなければならないことを,また,同条3項本文は,実体要件として,ビザの変更の申請があった場合には,法務大臣は,当該外国人が提出した文書によりビザの変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り,これを許可することができることを定めている。
実体要件である上記の「ビザの変更を適当と認めるに足りる相当の理由」の具体的意義・内容については,法によって明らかにされていないが,国際慣習法上,国家は外国人を受け入れる義務を負うものではなく,特別の条約がない限り,外国人を自国内に受け入れるかどうか,また,これを受け入れる場合にいかなる条件を付するかは,当該国家が自由に決定することができるものとされ,したがって,憲法上,外国人は我が国に入国する自由を保障されているのではないことはもちろん,在留の権利ないし引き続き本邦に在留することを要求し得る権利を保障されているものではないと解されていることを考慮すると,上記要件の具備の有無についての判断は,外国人に対する出入国の管理及び在留の規制の目的である国内の治安と善良の風俗の維持,保健・衛生の確保,労働市場の安定などの国益の保持の見地に立って,申請者の申請事由の当否のみならず,当該外国人の在留中の一切の行状,国内の政治・経済・社会等の諸事情,国際情勢,外交関係,国際礼譲など諸般の事情を総合的に勘案して的確に行われなければならないから,このような多面的専門的知識を要し,かつ,政治的配慮も必要とする判断については,国内及び国外の情勢について通暁し,常に出入国管理の衝に当たる法務大臣の広汎な裁量にゆだねられているといわざるを得ない。
したがって,当該判断の基礎とされた重要な事実に誤認があること等によりその判断が全く事実の基礎を欠くか,又は事実に対する評価が明白に合理性を欠くことによりその判断が社会通念に照らし著しく妥当性を欠くことが明らかであると認められる場合に限って,当該判断は裁量権の範囲を逸脱し又は濫用するものとして違法となると解される(最高裁判所昭和53年10月4日大法廷判決・民集32巻7号1223頁参照)。
イ もっとも,外国人からのビザの変更申請を許可するか否かの判断は,論理的に分析すると,〔1〕当該外国人がビザの変更後に行うことを予定している活動が,変更申請に係るビザの類型に該当するか否か(以下「ビザ該当性」という。)の判断と,〔2〕その他の諸般の事情を考慮し,ビザの変更を認めるのが相当であるか否かの判断の二つから成り,両者が肯定されて初めて許可処分を受けられると考えられるところ,〔1〕の判断は,基本的には事実認定に属するものであるから,法務大臣の広汎な裁量権の対象となるのは,厳密には〔2〕の判断に限られると解するのが相当である(このことは,認定された事実をどのように評価すべきかの問題が,〔2〕の判断に含まれることを否定するものではない。)。
そして,ビザ該当性の判断に当たっては,申請者の提出資料に表れた在留資格変更後における申請者の活動予定だけでなく,申請者のこれまでの在留期間中の活動実績等を踏まえて,真に変更申請に係るビザの類型に該当する活動を行う意思を有しているかという推認を行うことは避けられないというべきである。
(2)ビザ「技能」により許される活動の範囲
そこで,本件におけるビザ該当性の判断の前提として,ビザ「技能」がどのような活動を想定しているかについて検討する。
法別表第1の2によれば,ビザ「技能」によって本邦において行うことができる活動は「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動」とされ,また,規則3条及び同別表第2によれば,在留期間は3年又は1年と定められている。また,上陸審査基準によれば,「法別表第1の2の表の技能の項の下欄に掲げる活動」の基準として,「申請人が次のいずれかに該当し,かつ,日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。1 料理の調理又は食品の製造に係る技能で外国において考案され我が国において特殊なものについて10年以上の実務経験(略)を有する者で,当該技能を要する業務に従事するもの(後略)」とされている。
法別表第1の2にいう「公私の機関」とは,事業主体性を有する団体又は個人を指すと解すべきであるから,ここにいう「契約」とは,そのような事業主体を雇用主とする雇用契約ないし事業主体がその目的を達成するために一定の事項を依頼する委託契約などが想定されているというべきであり,かつ,公私の機関との契約に「基づいて」との文言からは,自らが事業主体となって行う活動ではなく,従属的な立場で当該事業に従事することを要すると解される。このことは,平成元年法律第79号による改正前の出入国管理及び難民認定法4条1項13号のビザ(本邦で専ら熟練労働に従事しようとする者)が,平成元年法律第79号の施行によって,ビザ「技能」とみなされたという沿革からも,裏付けることができる。
そうすると,ビザ「技能」においては,事業の経営判断という要素を含む活動を想定していると考えることは困難である。
(3)本件資格変更申請が許可された場合に原告が予定している活動の「技能」該当性
ア 認定事実等
前記前提事実に証拠(乙10ないし15,16及び17の各1・2,21ないし24,26ないし32)及び弁論の全趣旨を総合すると,下記の事実を認めることができる。
(ア)本件店舗の賃貸借契約の締結の経緯及び仲介業者担当者の認識等
原告は,平成15年4月20日,株式会社Jの仲介により,インド料理店の開設のため,Kとの間で,本件店舗を賃料月額21万円,賃貸期間平成15年4月21日から平成17年4月20日までとする賃貸借契約を原告名義をもって締結し,Bは,同契約に基づく原告の債務を連帯保証した(乙10,26)。
原告は,上記賃貸借契約を締結するまでに,株式会社Jの本社事務所に5回ないし6回訪れているところ,同社の担当者Lに,「自分の店を持ちたいので良い物件はないか。」と告げていたほか,終始,自分1人で立地条件や店の広さなどを確認したり,家賃や保証金等の契約に当たっての重要事項を他の人に判断を仰ぐことなく自分で決定していたことなどから,Lは,原告が本件店舗の実質的な経営者であると認識していた(乙22)。
なお,後記(エ)のような事情で,Bが原告の連帯保証人を辞退したいとの意思を表明したことから,原告は,平成15年11月14日,Kとの間で,本件店舗を賃料月額21万円,賃貸期間平成15年12月1日から平成17年11月30日までとする賃貸借契約を(再)締結し,Mが同契約に基づく原告の債務を連帯保証した(乙14)。
(イ)飲食店業の営業許可名義及び電気・ガスの契約名義
原告は,平成15年4月21日付けで,名古屋市千種保健所長から,本件店舗に係る飲食店営業の許可を受けていたが,同年7月29日付けで本件会社に対して本件店舗に係る飲食店営業が許可されるや,同年8月1日,上記保健所長に対し,原告を営業者とする営業許可について廃業届を提出した(乙11の1・2,13)。
もっとも,本件店舗に係る都市ガスの供給契約及び電気供給契約は,いずれも原告名義で締結されている(乙27,30)。
(ウ)原告名義の郵便貯金口座の状況
平成15年1月から平成16年4月9日までの間,Tの郵便貯金口座と推測される口座から原告名義の郵便貯金口座に対して合計165万3000円が送金され,逆に,Tの郵便貯金口座と推測される口座から原告名義の郵便貯金口座に対して合計107万0200円が送金されているが,いずれも送金の時期及び金額に規則性は認められないため,給料などの経費の支払のための送金や毎月の売上金の送金とは判断できない(乙31,32)。そうすると,Tからの原告への送金は,その時々に必要となった資金の援助にとどまっていたものと推認される。
(エ)Bの認識等
Bは,名古屋市千種区○○でインド料理店「N」を経営する者であるが,平成14年の秋ないし年末ころ,原告が同人の遠い親せきに当たる同店の料理長を訪れたことから,原告と面識を持つようになり,平成15年2月5日から同年3月27日までの間,同店で勤務していたコックの一時帰国の際には,原告を同店の店員として雇っていた。
Bは,同年2月ころ,原告から自分の店を持ちたいので協力してほしいと言われ,また,原告の親せきである「N」の料理長からも相談に乗ってあげてほしいと懇願されたことから,原告に協力することとした。
原告は,本件店舗の賃貸借契約を締結するに当たり,Bに対し,保証委託料月額10万円の支払と引き換えに,同契約について連帯保証人となることを申し入れたので,Bはこれに応ずることとした。なお,原告は,本件店舗の場所を決定する際に,B及び「N」の料理長とは相談をしたが,それ以外にだれか他人に相談したり判断を仰ぐことはなかった。また,Bが「自分の店を持つのだから夢を持ってやりなさい。」と励ましの言葉をかけたところ,原告は,本件店舗の名称を,他の者に相談することなく,「夢」を意味するヒンディー語の「A」と決定した。
その後,Bは,本件店舗の経営状況を原告に尋ねても一切回答がなかったこと,平成15年8月までの間の保証委託料60万円のうち20万円しか支払わなかったことから,同月ころ,原告に対して連帯保証人を辞退する意思を示し,また,Bは,原告から何ら連絡がなく,保証委託料も支払われなかったことから,本件店舗での営業を止めさせるために,同年11月6日ころ,本件店舗の出入口の鍵を取り替えた。
さらに,Bは,原告に対し,未払の保証委託料の支払を求めて支払督促を申し立て,その後通常訴訟に移行したところ,平成16年1月26日,原告との間で,原告がBに対して40万円を8回分割で支払うことを骨子とする訴訟上の和解が成立した。
なお,Bは,原告が自分の店を持ちたいと話していたこと,不動産の賃貸借契約を原告名義で締結したこと,営業に関する重要事項を1人で決めていたこと,保証委託料の請求の裁判に原告自ら出廷してきたこと,本件店舗について他に責任者がいると聞いたことはないこと,原告が本件店舗を自分の店と言っていたことなどから,本件店舗の経営者は原告であると認識している(乙10,14,15,21,23)。
(オ)Cの認識等
Cは,平成15年4月ころ,原告とは面識がなかったものの,Bから頼まれて,本件店舗開店のための店内ポップのデザイン一式を作成することとした。Cは,原告が開店前でお金がないと泣きついてきたため,原告の言い値である10万円で店内ポップを作成することとした。しかし,原告は,Cに対して,事前の打合せで確認したこととまるで違うことを言って,何度もやり直しを命じた。
Cは,本件店舗のお金と原告自身のお金との区別をしないなどのことから,原告が本件店舗の経営をしていたと認識していた(乙16の1・2)。
(カ)Sの認識等
Sは,平成15年3月中旬ころ,原告から,本件店舗を出店するための改装の依頼を受けた。原告は,本件店舗の設備配置の決定や建材の選定について,他の者から指示・注文を受けることがなかったほか,Sに対し,自分が本件店舗の社長であると告げていた。
また,原告は,同年4月10日に,Sが本件店舗の改装工事に着手した後,見積りに記載がない部分について改装を希望したり,自分のイメージと違うから代えてほしいと言ったが,他の者から指示を受けることはなかった。
Sは,以上のようなことから,原告が本件店舗の経営者であることに間違いないと認識していた。
なお,原告は,Sに対して,見積代金136万5388円及び追加工事9万円の合計145万5388円について,4月7日から同年5月30日までにかけて115万5000円を,同年11月20日に30万円を支払った(乙17の1・2,29)。
(キ)Oの認識等
Oは,本件店舗に対して酒類を卸売している株式会社Pの実質的経営者であるが,Bからの紹介で,本件店舗に酒類を納入するようになった。Oは,原告から自分がオーナーとして本件店舗を始めたと聞かされたこと,原告との間で商品等の細かい打合せを行い,原告が決定をしていたこと,看板屋とのやりとりもすべて原告が行っていたことなどから,原告が本件店舗のオーナーであると認識していた。
なお,株式会社Pと原告との間には1度も金銭上のトラブルもなく,現在も取引が続いている(乙28)。
(ク)Qへの原告の発言
原告は,平成15年10月ころ,Q(原告のかつての雇用主であって,平成14年3月6日及び5月29日の在留期間更新許可申請時の身元保証人)に対し,「自分が経営する店について,不動産屋と大家から出ていけと言われている。せっかく自分で店を出したのに,ここで出ていかなければならなくなるとすべてがパーになる。」と告げた上で,本件店舗の賃貸借契約の連帯保証人になってほしいと依頼した。
なお,Qは,原告に対し10万円ほどのお金を貸したまま返済を受けていないが,今では返済の見込みがないものとあきらめている(乙24)。
以上の事実認定に関し,原告は,被告が「原告を快く思っていなかった者らの悪意に満ちた誹謗中傷に惑わされ」た旨主張し,Bらの供述調書等の信用性を争っているので,その認定理由についてふえんするに,なるほど,B,C及びSは,原告との間で金銭的なトラブル等を抱えていたことから,原告を快く思っていないことは想像に難くなく,特に,Bについては,原告のために奔走したにもかかわらず裏切られたとの思いを抱いていることは容易に推認し得るところであり,かかる事情にかんがみれば,B,C及びSの提出に係る陳述書ないしB及びSの供述調書については,信用性を慎重に吟味する必要性がある。しかし,B,C及びSが原告に敵意を抱いていたとしても,金銭的なトラブル等に直接関係する部分はともかく,本件店舗の準備にどの程度原告が関与していたかの点について殊更に虚偽を述べる必然性は認め難いこと,かかる金銭トラブルのないL及びOも,原告が本件店舗の経営者であると認識していることなどに照らせば,上記の陳述書ないし供述調書のうち,本件店舗の営業についての原告の関与状況に関する核心部分についての信用性を疑う根拠はないというべきである。
イ 本件在留資格変更不許可処分時の本件店舗の経営者
(ア)上記認定事実によれば,原告名義で本件店舗に関する賃貸借契約やガ ス・電気の供給契約等が締結されたこと,当初は原告名義で食品衛生法上の営業許可を受けたこと,物件の選定,店名の決定,改装の間取りの決定,メニューの決定の際に原告がTに相談した形跡がないこと,L,B,C,S及びOは一致して原告が本件店舗の経営者であると認識していたこと,原告はQに対して本件店舗は自分が出した店と発言していたこと,Tから原告への送金はせいぜい資金援助にとどまっていたこと,以上のとおり要約することができる。
これらの事実を総合すれば,本件在留資格変更不許可処分の際に,本件店舗の実質的経営者は原告であると認めるのが相当である。
(イ)この点につき,原告は,本件店舗を経営していたのはTないし本件会社であると主張し,〔1〕証人Rの証言及び原告作成の書面(甲5の1)には,これに沿う部分があるほか,〔2〕本件更新申請の際に被告に提出された雇用契約書3通(乙18の1ないし3)及び本件資格変更申請の際に被告に提出された雇用契約書1通(乙20)には,いずれも雇用される労働者が原告である旨の記載があり,また,〔3〕本件資格変更申請の際に被告に提出された「建物賃貸借契約書(事業用)」(乙25)には,借主の「氏名」欄に記入された原告の署名の下の「電話」欄に本件会社の記名印が押捺されている。
そこで,まず〔1〕について検討するに,証人Rは,原告が身柄を拘束される前の金銭管理の状況や本件会社との金銭のやりとりの状況を直接には知らないと証言しており,原告の供述のみを根拠にして証言したにすぎない。そして,証人Rは,Tに雇用されているなどと主尋問において証言するにもかかわらず,この裏付けとなる客観的な書証は一切提出されていないことにかんがみると,同人の証言をもって原告の主張を認めることはできない。また,甲5の1は,Tに契約のことを頼まれ全面的に任されたなど,原告の主張に沿う内容となっているが,Bにコンサルタント料(保証委託料)を支払っていたのがTという裏付けはないほか,また,Aの収入はTと店長が管理していると記載されているが、証人Rは原告が身柄を拘束されるまでの金銭管理の状況等を直接には知らないと証言しており,甲5の1の内容をたやすく採用することはできない。
次に〔2〕について検討するに,まず,これらの雇用契約書は作成日付,雇用主等について記載が異なっている。すなわち,a乙18の1の雇用契約書の作成日付は平成15年4月20日であり,雇用主欄には本件会社の記名印の捺印があるが,雇用契約書の頭書きには,雇用主がインド料理A事業主Tである旨の記載があり,b乙18の2の雇用契約書の作成日付は平成15年4月20日であり,雇用主欄にはインド料理の店Aの記名印の捺印とTの署名があり,c乙18の3の雇用契約書の作成日付は平成15年7月13日であり,雇用主欄には本件会社の記名印の捺印があり,d乙20の雇用契約書の作成日付は平成15年7月28日であり,雇用主欄には本件会社の住所・名称・代表者名が不動文字で印刷され,本件会社の代表取締役印が捺印されている。
一般に,同一の労働者について作成日付ないし雇用主の異なる雇用契約書を複数作成するのは不自然であるところ,上記のように記載内容が異なる契約書が4通も作成されていることについて原告は合理的な理由を何ら説明していない。また,乙18の1の雇用契約書は,雇用者が本件会社であるが,作成日は同社の設立日である平成15年7月14日の3か月近く前の平成15年4月20日となっていることから,少なくとも平成15年4月20日に作成されたものとは考えられない。さらには,乙20が平成15年7月28日に作成されたのであれば,本件更新申請の際に提出することが可能であるのに,これが提出されなかったことについて,原告は何ら合理的な理由を説明していない。
このような点に照らすと,原告は,本件店舗の経営者が原告であると,ビザ「技能」では在留することができないと考え,雇用契約書を偽造したか,あるいは,本件会社ないしTの了解のもと,虚偽の内容の雇用契約書を作成したとの疑いを払拭することはできない。
さらに〔3〕について検討するに,貸主が保管している「建物賃貸借契約書(事業用)」(乙26に添付)中の「(D)貸主及び管理人」及び「(E)借主及び緊急時の連絡先」欄は空欄であること,同契約書末尾の借主欄には原告の住所と原告の署名押印のみがあること,契印も原告の印影であること,他方,原告提出に係る乙25には,「(D)貸主及び管理人」の欄に本件会社及び代表取締役の各記名印があること,同書面末尾の借主欄には原告の住所と原告の署名押印の下に本件会社の住所と本件会社の各記名印があることなどにかんがみれば,上記契約書は,原告が本件店舗の経営主体が本件会社であることを装うために,後日,本件会社等の記名印を使用して改ざんしたものと推認することができる。以上のとおりであって,本件会社が本件店舗の経営者であるとの原告の主張は採用できず,前記認定を覆すことはできない。
ウ ビザ該当性についての判断の当否
前記のとおり,本件店舗の実質的経営者は原告であり,かつ本件店舗を開店するに当たって,原告が相当の資金や労力を費やしたと認められる以上,本件資格変更申請が許可された場合に予定している活動は,主として本件店舗の経営であると推認することができる。この点,原告は,本件資格変更申請の際,被告に対し,「二度とビザ外の行為はいたしません。」などと記載された平成16年2月1日付け理由書を提出している(乙19)が,その内容は,「契約等をしてはいけないとゆう事を知らず……あのような法律行為をしてしまいました。」とあるように,契約等の法律行為を自分名義では行わないことを表明しているにすぎないと解される上,「弟一人では大阪と名古屋の両店舗を切り盛り運営していくことはとうてい無理」であると自認していることを考慮すると,実質的な経営から離れる意思があるとは認め難く,実際にも,本件店舗は原告の経営面における関与なくして維持できないと考えられるから,上記判断を覆すことはできない。
そうすると,原告は本件店舗を実質的に経営する傍ら,調理等の業務に携わることも予定しているとしても,なお,ビザ「技能」が想定している活動を超える活動を企図していると判断することができるから,原告について「技能」のビザ該当性を認めなかった被告の判断に,事実誤認の違法があるとは認められない。
したがって,被告のした本件在留資格変更不許可処分は,その余について検討するまでもなく,適法といわざるを得ない。
3 よって,本件訴えのうち本件不更新通知の取消しを求める請求に係る部分は不適法であるから同部分を却下し,本件在留資格変更不許可処分の取消しを求める原告の請求には理由がないからこれを棄却し,訴訟費用の負担につき,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。
名古屋地方裁判所民事第9部
裁判長裁判官 加藤幸雄
裁判官 舟橋恭子
裁判官 尾河吉久
松村総合法務事務所
ビザ総合サポートセンター
DNA ローカス大阪オフィス
〒540-0012
大阪市中央区谷町2 丁目5-4
エフベースラドルフ1102
TEL:06-6949-8551
FAX:06-6949-8552