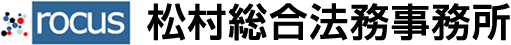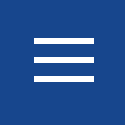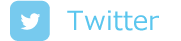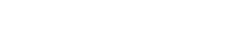判例集2019.02.05
退去強制令書発付処分取消請求事件
判例集2019.02.05
東京地方裁判所平成16年9月17日 判決
主 文
一 被告東京入国管理局長が原告に対して平成15年4月9日付けでした出入国管理及び難民認定法49条1項に基づく原告からの異議の申出は理由がない旨の裁決を取り消す。
二 被告東京入国管理局主任審査官が原告に対して平成15年4月10日付けでした退去強制令書発付処分を取り消す。
三 訴訟費用は被告らの負担とする。
事実及び理由
第一 請求
主文1、2項と同旨(訴状「請求の趣旨」欄1項記載の「10日」は「9日」の誤記と認める。)
第二 事案の概要
一 事案の骨子
本件は、法務大臣から権限の委任を受けた被告東京入国管理局長(以下「被告東京入管局長」という。)から出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)49条1項に基づく異議の申出は理由がない旨の裁決を受け、被告東京入国管理局主任審査官(以下「被告主任審査官」という。)から退去強制令書の発付処分を受けた原告が、原告に在留特別許可を認めなかった前記裁決には、被告東京入管局長が裁量権の範囲を逸脱又は濫用した違法があり、同裁決を前提としてされた退去強制令書の発付処分も違法である旨主張して、同裁決及び同発付処分の取消しを求める事案である。
二 前提となる事実
証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実は、その旨記載した。それ以外の事実は当事者間に争いがない。
1 身分事項等
原告は、昭和48年(1973年)4月21日、中華人民共和国(以下「中国」という。)遼寧省において出生した中国国籍を有する外国人である。
2 原告の入国及び在留状況等
(一)原告は、平成6年(1994年)4月4日、新東京国際空港に到着し、入国審査官から、入管法別表第一に定めるビザ「留学」、在留期間「1年」とする上陸許可を受けて、本邦に上陸した。
(二)原告は、東京都杉並区長に対し、平成6年4月8日、外国人登録法(以下「外登法」という。)に基づく新規登録申請をし、外国人登録証明書の交付を受けた。
(三)原告は、平成7年3月、同8年3月及び同9年2月に、東京人国管理局(以下「東京入管」という。)において、法務大臣に対し、在留期間更新許可申請をし、いずれも、在留期間「1年」とする許可を受けた。
(四)原告は、平成7年4月及び同11年1月に、それぞれ居住地変更登録をした。
(五)原告は、平成9年12月18日、本邦において、乙太郎と婚姻した。乙太郎は、中国国籍を有する外国人であった。
(六)原告は、平成9年12月26日、東京入管において、法務大臣に対し、入管法別表第一に定めるビザ「留学」から入管法別表第一に定めるビザ「家族滞在」へ変更する旨の在留資格変更許可申請をし、平成10年1月19日、入管法別表第一に定めるビザ「家族滞在」、在留期間「1年」とする許可を受けた。
(七)原告は、平成10年12月11日、東京入管において、法務大臣に対し、在留期間更新許可申請をし、同月25日、在留期間「1年」とする許可を受けた。
(八)原告は、平成12年1月6日、東京入管において、法務大臣に対し、在留期間更新許可申請をし、同月17日、在留期間「3年」とする許可を受けた。この許可に係る在留期限は、平成15年1月19日であった。
(九)原告は、平成12年7月4日、東京都板橋区長に対し、居住地を東京都板橋区(以下「板橋区」という。)《住所略》(現住所地である。以下、同所で居住している貸室を「本件マンション」という。)とする居住地変更登録をした。
(十)原告は、平成14年2月27日、乙太郎と離婚した。
(十一)原告は、平成14年4月24日、東京入管において、法務大臣に対し、入管法別表第一に定めるビザ「家族滞在」から入管法別表第一に定めるビザ「人文知識・国際業務」へ変更する旨の在留資格変更許可申請(以下「第一次申請」という。)をした。法務大臣から権限の委任を受けた被告東京入管局長は、同年9月2日、第一次申請について、不許可処分をした。
3 退去強制令書発付処分に至る経緯
(一)原告は、平成15年1月16日、東京入管において、法務大臣に対し、入管法別表第一に定めるビザ「家族滞在」から入管法別表第一に定めるビザ「人文知識・国際業務」へ変更する旨の在留資格変更許可申請(以下「第二次申請」という。)をした。法務大臣から権限の委任を受けた被告東京入管局長は、同年2月25日、第二次申請について、不許可処分をし、同年3月12日、これを東京入管に出頭した原告に通知した。
これにより、原告は、在留期限である同年1月19日を超えて本邦に不法に残留することとなり、入管法24条4号ロ(在留期間の更新又は変更を受けないで在留期間を経過して本邦に残留する者)に該当することとなった。
(二)東京入管入国警備官は、平成15年3月12日、原告が入管法24条4号ロに該当すると疑うに足りる相当の理由があるとして、被告主任審査官から収容令書の発付を受け、同日、同令書を執行し、原告を東京入管収容場に収容した。東京入管入国警備官は、同月13日、原告を東京入管入国審査官に引き渡した。
(三)東京入管入国審査官は、平成15年3月25日、原告が入管法24条4号ロ(不法残留)に該当する旨認定し、原告にこれを通知した。原告は、同日、この認定につき、特別審理官による口頭審理を請求した。
(四)東京入管特別審理官は、平成15年4月7日、原告に係る口頭審理をし、前記(三)における入国審査官の認定に誤りはない旨判定し、原告にこれを通知した。原告は、法務大臣に対し、同日、この判定につき、入管法49条1項に基づく異議の申出をした。
(五) 法務大臣から権限の委任を受けた被告東京入管局長は、平成15年4月9日、原告からの前記(四)の異議の申出について理由がない旨の裁決(以下「本件裁決」という。)をした。同日本件裁決の通知を受けた東京入管主任審査官は、原告に対し、同月10日、本件裁決を告知するとともに、退去強制令書発付処分(以下「本件退令処分」という。)をした。
4 本件裁決及び本件退令処分後の経過(一)東京入管入国警備官は、平成15年5月20日、原告を入国者収容所大村入国管理センター(以下「大村センター」という。)へ収容した。
(二)日本人である丙川松夫(昭和42年12月21日生。以下「丙川」という。)は、平成15年5月22日、板橋区長に対し、丙川と原告が婚姻する旨の届出をした。
(三)原告は、平成15年7月9日、本件訴えを提起した。
(四)原告は、平成16年6月18日、仮放免された。その後、原告は、本件マンションで、丙川と同居して生活している。
三 争点
1 本件裁決の適法性について
被告東京入管局長は、原告につき、特別に在留を許可すべき事情があるとは認められないとして、本件裁決をしているが、この判断は、同被告の有する裁量権を逸脱するなどしてされた違法なものか。
2 本件退令処分の適法性について
本件裁決が違法であるから、これを前提とする本件退令処分も違法か。
四 当事者の主張の要旨
1 原告の主張
(一)争点1(本件裁決の適法性)について
(1)憲法上外国人に入国の自由が認められないとしても、そのことから直ちに、いったん我が国に入国した外国人に在留する権利が保障されていないと帰結することはできない。憲法22条1項が「何人も」居住、移転の自由を有すると規定し、同条2項が「何人」も外国に移住する自由を侵されない旨規定していることや、例えば、移転の自由はその権利の性質上外国人に限って保障しないとする理由は見当たらないことから明らかなように、日本国憲法は、個人の尊厳に立脚し、個人がいかなる幸福を追求するかを個人の決定にゆだねるべきであり、国家はそれを追求する諸条件・手段を保障しようとするものであるという個人主義思想に立脚していることからすれば、外国人であろうと、日本国籍を有する者であろうと、差別される理由はない。在留特別許可の制度において法務大臣等に広範な裁量権があることを前提に、その裁量権の逸脱又は濫用の場合に初めて、裁決が違法となると解することは、法の支配を排除しようとすることにほかならない。
憲法が国民のみならず外国人に対しても居住・移転の自由を保障し、市民的及び政治的権利に関する国際規約(以下「B規約」という。)21条においても同様の規定があることにかんがみれば、不法滞在者であっても、個人として尊重すべきであり、人生設計の全面的なやり直しを迫る退去強制という手段は、人道上も人権上も問題であるから、特別の事情がある場合には、在留を認めようとするのが、在留特別許可の制度である。このような制度の趣旨を念頭におけば、在留特別許可をすべきか否かの判断基準は、すべての移住労働者とその家族構成員の権利保護に関する国際条約(以下「国連移住労働者条約」という。)69条2項を参考に、入国の状況、在留期間及びその他関連する事項、特に家族の状況に関する適切な配慮がされているか否かに求めるべきであり、これを念頭において、不法滞在者が市民として我が国に定着しているか否かという観点から、在留特別許可を認めるかどうかを判断すべきである。
(2)ア 原告は、平成6年4月4日、国費留学生として来日し、丁原専門学校、次いで戊田専門学校幼児教育学科、さらに同校の幼稚園教諭・保母養成学科でまじめに就学し、学業に専念して、すべての課程を修了し、保母資格及び幼稚園教諭二種免許を取得して、平成10年3月、同校を卒業した。
イ ところが、原告は、恋愛関係にあった乙太郎との子供を妊娠したため、自分の夢を捨てて乙太郎との婚姻を決意した。乙太郎は、両親の反対を秘して、平成9年12月、強引に原告との婚姻に踏み切った。
ウ 原告は、中国に帰国して長女乙一江を出産した後、日本に戻った。原告は娘を含む三人での生活を望んでいたが、乙太郎が仕事に専念したいなどという理由で、これに反対したため、原告は、やむなく中国の原告の両親に娘を預け、仕送りをしながらやがて家族で生活することを夢見ていた。ところが、乙太郎は、職場を転々としており、そのため、収入も月25万円程度であって、それほど多くはなかった。原告は、中国の地方出身者で、夫を立てなければならないと教わって育ってきており、生活が苦しいときは仕事を見つけ収入を得て夫を助けなければならないと考え、乙太郎の仕事が不安定で乙太郎の収入が多くなく、中国への送金もままならない状態であった平成11年5月に、株式会社甲田(以下「甲田社」という。)に就職して、乙太郎を助け、乙一江に送金するために、必死で働いた。このときの上司が丙川である。その後、乙太郎は、乙野社に入社したが、原告も、誘われて、同年10月ころ、甲田社を退職し、乙野社に就職した。原告は、入社後約3か月が経ったころに、同社の繁忙期が過ぎた上、乙一江に会いたい気持ちが強くなったので、乙野社を退職し、いったん中国に帰国した。原告は、平成12年5月、日本に戻って、丙山株式会社(以下「丙山社」という。)の旅行部門に就職した。このとき、資格外活動許可を得た。
エ ところが、乙太郎は、平成12年5月、両親が来日すると、原告を残したまま両親と旅行に出かけ、同年7月ころには乙野社を退職し、両親とともにそのまま中国に帰国し、日本に来ようとはしなかった。原告は、不安定な生活が続く中で、必死で働き、仕事上のことで分からないことがあると、電話で丙川に質問するなどして、旅行業に精通するようになり、顧客の立場で旅行計画を立案して、顧客から信頼されるようになるとともに、会社においても、マナーを守り、日本の風習を習得し、日本人以上に日本人らしく振る舞い、上司や同僚からは原告の手腕が買われるようになった。原告は、乙太郎を迎えに中国に行き、日本でもう一度将来を考えるため、二人で日本に帰国した。しかし、乙太郎は、ほぼ無職の状況が続いた。原告は、必死に働き、家庭を守ってきたが、夫婦の溝は深まり、原告と乙太郎は、平成14年2月、離婚した。しかし、乙太郎は、仕事がなく、行き場もなかったので、離婚後も、本件マンションで生活を続けた。
オ 原告は、丙山社で懸命に働き、売上げもトップを走っていたが、独立するといううわさが流れ、平成14年1月、同社を解雇された。原告は、丁川株式会社(以下「丁川社」という。)の社長に請われ、就労ビザを取得すると約束してくれたので、同社に就職した。原告は、別れた夫と同居するという極めて不自然な生活を続けるうちに、帰宅するのが嫌になり、結局、早朝から深夜遅くまで働き、人相が変わるほどやつれた。
カ 丙川は、平成14年2、3月ころに、原告が丁川社で働いていることを知った。その後、丙川は、数回、仕事上のことで原告と電話で話したり、会うなどしたが、その際、原告に対し、「今度食事でもしよう。」と誘った。原告は、イタリアンレストランで丙川と会ったが、このとき、乙太郎との離婚、その後の乙太郎との同居、中国にいる乙一江のことなど、これまでの事情をすべて話し、鬱積した苦悩を打ち明けた。丙川は、原告の生活や苦悩を知って、原告に同情した。丙川は、原告から、夫を支え、家族を守るために必死に働いてきたことを聞かされ、日本人以上に日本人らしく振る舞っていた原告をいとおしく思う感情を抑えることができず、原告を助けてあげたいという衝動に駆られた。
キ その後、原告と丙川は、頻繁に会うようになり、週に数回デートを重ね、週末も一緒に過ごすようになり、急速に親しくなっていった。丙川は、これまで付き合ってきた日本人の女性にはない優しさや、老人や子供に対するいたわりが原告にあることに惹かれ、原告は、丙川に対する尊敬の念から、原告の苦悩を理解しすべてを受け入れてくれる一人の男性として思いを募らせるようになってきた。原告は、離婚後、丁川社の社長から、週6日間の労働を強要され、「ビザはあってもないのと同じだ。」などと言って、給与を不当に引き下げるなどの嫌がらせを受けるようになったが、丙川は、原告をかばい、原告を支えた。
ク 原告が足にけがをして1、2日入院した後通院するということがあったが、丙川は、原告の傍らにいて看病することができない自分に腹立たしさと無力感を覚えるようになり、原告との婚姻を意識するようになった。原告も、丙川を心底信頼するようになり、丙川との婚姻を心から望むようになった。丙川と原告は、平成14年8月に、婚姻して、将来中国にいる乙一江を日本に呼び寄せ、一緒に生活することを誓うようになった。しかし、親思いの丙川は、自分が一人っ子であること、原告には離婚歴があり、中国に子供がいること、別れた夫が本件マンションに居座っている状況であることなどから、すぐには原告との婚姻の意志を両親に伝えることができず、原告と相談の上、環境を整えた上で両親を説得することにした。
ケ 環境整備の一環として、原告は、丙川の紹介で、株式会社戊原(以下「戊原社」という。)に就職し、新しい住まいを探すようになった。しかし、そのころ、乙太郎が中国に送還されることになったので、原告は、引っ越しを断念し、本件マンションで丙川と二人で生活する決意を固めた。原告と丙川は、平成14年12月にヨーロッパ旅行に出かけた。このように、原告と丙川は、同月には、事実婚の意志を固めていたということができる。原告と丙川は、帰国後、事実上の婚姻生活をするようになり、家賃と光熱費等は原告が負担し、丙川が、生活費として5万円を渡し、外食や買物の費用も丙川が負担していた。丙川は、平成15年1月初旬ころから、原告が日本に永住することができるようビザの変更の手続をするよう助言し、その手伝いもしていた。原告も丙川も、丙川の両親から祝福された状態で正式な婚姻をしたいと考えていたが、丙川は、まだ両親に原告を紹介していなかった。そのため、丙川は、両親との関係を悪化させないよう配慮して、週に数日は実家に戻っていた。
コ その後、丙川は、原告が収容された時点で、原告に対し、入籍を求めたが、原告は、強制退去の危険があるのにこれ以上丙川に迷惑をかけることはできないという思いと、収容された直後に入籍するのは責任逃れのように勘違いされるという思いから、入籍にはちゅうちょを覚えた。しかし、丙川は、退去強制令書が発付される可能性が高くなった段階に至って、原告との別離は二人の生活を根本的に破壊し、計り知れない精神的ダメージを与えることになると悟り、原告に対し、強く入籍を求めた。原告は、丙川の愛情の深さに心を打たれて、これに同意した。
丙川は、両親を説得して、平成15年5月22日、原告との入籍を果たした。丙川は、原告との生活の場所であった本件マンションで暮らし、原告との面会を続けた。丙川の給与は、手取りで月約25万円から26万円くらいであったにもかかわらず、丙川は、預金を取り崩しながら、原告が大村センターに収容された後も、月に二回から四回大村センターを訪れて、原告と面会した。原告も、丙川に対し、数百通に及ぶ手紙を出した。
(3)原告は、資格外活動をしたことがあるが、平成13年8月17日以前は法的無知が原因であり、その違法性は低い。原告が平成14年11月3日に入社した戊原社については資格外活動の許可を受けていないが、ビザの変更によって就労の場を確保しようとしていたのであり、やはり違法性は低い。外国人に対する過重な就労制限に批判の目が向けられている現在の状況の下では、特別の理由がない限り、資格外活動それ自体を理由に在留特別許可をしないことは許されないというべきである。そして、本件では在留特別許可をしないとする特別な理由も存しない。
また、第二次申請の申請書には虚偽の記載があるが、これは、行政書士にすべて依頼して手続をしたところ、生じたものであり、原告には、悪意はなく、違法性の意識もなかった。
(4)以上の経緯によれば、原告は、国費留学生として来日し、勉学にいそしみ、業務に専念し、夫婦として丙川と深い愛情に結ばれ、善良な市民として日本の社会に定着しており、原告と丙川との仲を引き裂くのは、人倫に反し、正義の観念に著しく反するのであって、原告に在留特別許可を認めるべきである。
仮に、在留特別許可の制度において裁量権を認めるとしても、以上の事情によれば、被告東京入管局長は、原告が在留期間の経過によって不法滞在となったという形式的理由により本件裁決をしたもので、裁量権を逸脱又は濫用したものとして違法であることは明らかである。
(二)争点2(本件退令処分の適法性)について
本件退令処分は、本件裁決を前提とするものであり、本件裁決の違法性を承継している。前記のとおり、本件裁決は違法であるから、本件退令処分も同様に違法である。
2 被告の主張
(一)争点1(本件裁決の適法性)について
(1)原告は、在留期限である平成15年1月19日を超えて本邦に不法に残留するものであり、入管法24条4号ロに該当する。したがって、被告東京入管局長に対する異議の申出は理由がない。
(2)そもそも、国家は、外国人を受け入れる義務を国際慣習法上負うものではなく、特別の条約又は取り決めがない限り、外国人を自国内に受け入れるかどうか、また、これを受け入れる場合にいかなる条件を付するかを自由に決することができる。我が国は、国連移住労働者条約を批准していない。B規約は、13条において法律に基づいて行われた決定によって外国人が強制退去されることを前提とした規定を設けていることからも明らかなとおり、外国人を受け入れるかどうか、及びこれを受け入れる場合にいかなる条件を付するかは専らその国家の立法政策にゆだねられているという国際慣習法を前提とする条約であるから、B規約が憲法の諸規定による人権保障を超えた利益を保護するものではないことは明らかである。
また、憲法上も、外国人は、我が国に入国する自由を保障されているものでないことはもちろん、在留の権利又は引き続き本邦に在留することを要求する権利を保障されているものでもない。我が国に適法に在留し、期間更新についても申請権も付与されている在留期間更新の許否についてさえ、我が国への入国・在留が憲法上当然に保障されたものではなく、国家の自由な裁量に任されていることに基づき、それを前提として入管法が立法されていることによるものと考えられ、更新事由の有無の判断は法務大臣の裁量に任されているとされているのであり、在留特別許可は、入管法上、退去強制事由が認められ退去されるべき外国人に恩恵的に与え得るものにすぎず、当該外国人に申請権すら認められていないものである。
そして、在留特別許可の許否を的確に判断するには、外国人に対する出入国の管理及び在留の規制目的である国内の治安と善良な風俗の維持、保健・衛生の確保、労働事情の安定など国益の保持の見地に立って、当該外国人の在留中の一切の行状等の個人的な事情のみならず、国内の政治・経済・社会等の諸事情、国際情勢、外交関係、国際礼譲など諸般の事情が総合的に考慮されなければならないのであり、このような見地から、入管法は、在留特別許可の付与を国内及び国外の情勢について通暁する法務大臣等の裁量にゆだねたものであり、この点からも、その裁量の範囲は極めて広範なものであることが明らかである。
以上のとおり、在留特別許可は、在留期間更新許可における法務大臣等の裁量の範囲よりも質的に格段に広範なものであるから、これを付与しないことが違法となる事態は容易に考え難く、極めて例外的にその判断が違法となり得る場合があるとしても、それは、在留特別許可の制度に設けられた入管法の趣旨に明らかに反するなど極めて特別な事情が認められる場合に限られる。
(3)ア 原告は、本件裁決時には、乙太郎と離婚しており、乙太郎は中国に送還され、原告と乙太郎との間の子である乙一江は中国に居住し、丙川とは婚姻関係になかったのであるから、原告に対してビザを付与する理由は何らも存在せず、在留特別許可を与える前提を欠いていた。
イ 原告は、平成14年2月27日、乙太郎と離婚して、入管法別表第一に定めるビザ「家族滞在」に該当しなくなったにもかかわらず、在留資格変更許可を受けることなく在留を継続し、また、乙太郎は、同年11月15日、中国に強制送還されていたにもかかわらず、原告は、戊原社への就職が決まったとして、平成15年1月16日、在日親族欄に乙太郎の氏名を記入して在留資格変更許可を求める第二次申請をした。また、原告は、平成14年11月から戊原社において資格外活動の許可を受けることなく就労していた。以上のような在留状況に照らし、被告東京入管局長は、原告に対し、平成15年2月25日、提出書類の信ぴょう性に疑義が認められ在留状況が不良と認められることを理由に、第二次申請について不許可処分をしたのである。
この事実からすると、原告が善良な市民として日本の社会に定着していたなどとは到底いうことができない。
ウ 原告名義のみずほ銀行新宿西口駅前支店の預金口座(口座番号《略》)には平成9年5月9日から同年12月18日まで合計約451万円が入金されており、これは、原告が本邦において稼ぎ出したものであるが、これがすべて正業により得られたものとは考え難く、仮に、正業による収入であったとしても、原告が入管法19条1項に違反して長時間労働していたことは明らかである。また、原告は、平成7年9月22日から平成10年7月27日まで、郵便局に約300万円もの貯金を有しており、これも正業による収入とは考え難く、仮に、正業による収入であったとしても、原告が入管法19条1項に違反して長時間労働していたことは明らかである。
以上によれば、原告が、学生の当時、勉学にいそしんでいたということはできない。
エ 丙山社は、原告が売上金の一部を着服したことを理由に、原告を解雇している。また、丁川社は、原告が会社に無断でテレホンカードを仕入れて販売しその利益を自分のものにしたり、虚偽の売上げを報告して売上金の一部を横領したりするなどして、会社に損害を与えたことを理由に、原告を解雇している。以上によれば、原告がまじめに稼働して、業務に専念していたということはできない。
オ 原告は、足にけがをして平成14年8月23日から同年9月10日まで休業したことを理由に損害保険会社から損害保険金として20万4397円の支払を受けている。しかし、原告は、休業期間中である同年8月23日、同月26日、同月28日、同月29日及び同月30日にそれぞれ出勤しており、5日分の損害保険金の支払を不正に受けたものと認められる。
乙太郎名義のシティバンク赤坂支店の口座には、平成10年6月29日から同年9月3日までに約2900万円が入金されており、このうち1300万円が同年10月8日に原告名義のシティバンク池袋支店の口座に入金されている。この約2900万円が正業により得られたものとは考え難く、原告がこの金員の取得に全く関与していなかったとは考えられない。
以上によれば、原告の在留状況には問題があったというべきである。
カ (1)原告は、東京入管入国警備官に対し、平成15年3月12日、本邦に在留を希望する理由について、本邦において仕事を続けたい旨供述し、丙川との同居を継続し婚姻を予定していることなど全く供述していないこと、(2)原告から丙川あての同月21日付けの手紙の内容からすると、原告は、丙川に結婚を求めたものの、丙川がこれに応じなかったため、中国への帰国をほのめかしたことがうかがわれること、(3)原告は、同月25日、東京入管入国審査官の違反審査において、本邦での在留を希望する理由について、日本の生活に慣れたこと、今の会社の仕事が好きであることなどを挙げ、できればずっと日本にいたい旨供述し、丙川については「好きな人も日本にいる」という程度の供述であったことによれば、前記違反審査の時点までには、原告と丙川との間に婚姻関係を形成する具体的な合意など存在しなかったものと認められる。
原告は、同年4月7日の口頭審理において、丙川の立会いの下に、丙川と婚姻してその面倒をみて支えていきたい旨述べ、同月2日又は同月3日に中国にいる母親に対し、婚姻手続に必要な書類を日本に送るよう依頼した旨述べていることからすれば、前記口頭審理の時点に至って、ようやく、原告と丙川との間に婚姻関係を形成する合意が形成されたものというべきである。
したがって、収容される以前から原告と丙川との間に婚姻の合意があったかのような原告の主張は、失当である。
キ (1)原告は、前記口頭審理において、「本年2月以降収容されるまではほとんど同居している状態ですが、1日くらい自分の家に帰るときもありました。」旨供述しているが、丙川は、同日、東京入管特別審理官から、原告と同居しているのかと問われて、「同居はしていません。週2、3日ぐらいでしょうか、仕事が遅くなったときには彼女の家に泊まり出勤しています。」旨述べて、明確に同居の事実を否定していること、(2)丙川の自宅は、横浜市青葉区であり、勤務先は、東京の北青山であり、原告の住所は、東京都板橋区であることからすると、丙川は、仕事で帰りが遅くなった際に自宅に帰らず、原告宅で寝泊まりしていたにすぎないものというべきである。
したがって、原告と丙川が同居していた事実はない。
ク 丙川は、東京入管特別審理官から、原告に生活費を支給しているのかと問われて、「たまにお米を買ってあげる程度で、家賃、光熱費、生活費の支給はしていません。」と述べ、原告も、「家賃と光熱費で月10万円くらいを私が自分で払っています。」と述べていることからすると、原告と丙川は、生計を別々にしていたというべきである。
ケ 仮に、原告と丙川が交際していたとしても、前記キ及びクの程度の交際関係があったというだけでは、本邦での在留を認めるべき特別な事情に当たるということはできない。
コ 原告が丙川と婚姻した事実は、本件裁決後の事情であり、これを本件裁決の適法性を判断するに当たってしんしゃくすることはできない。
サ 原告は、中国で出生し、同所で育ち、同所で教育を受け、同所で生活を営んできたものであって、本邦に入国するまで、我が国とは何ら関わりのなかった者である。そして、原告は、稼働能力を有する成人であるところ、中国には両親、弟及び子が居住しており、資産として約800万円があるというのであるから、中国に帰国したとしても、帰国後の生活に特段の支障があるとは認められない。
(4)以上によれば、原告について在留特別許可を付与しないことが在留特別許可制度に設けられた入管法の趣旨に明らかに反するなど極めて特別な事情があるとは認められないから、本件は、在留特別許可を付与しなかったことが例外的に違法となる場合にも当たらない。
(1)争点2(本件退令処分の適法性)について
被告主任審査官は、退去強制手続において、法務大臣から権限の委任を受けた被告東京入管局長から「異議の申出が理由がない」との裁決をした旨の通知を受けた場合、退去強制令書を発付するにつき全く裁量の余地はない(入管法49条5項)。したがって、前記通知があった以上、本件退令処分も適法である。
第三 争点に対する判断
一 原告は、乙第28号証から第37号証までには、被告らが従前から入手していた証拠が含まれており、原告本人尋問の実施後に提出しているので、時機に後れた攻撃防御方法として却下を求める旨主張するので、以下、判断する。
1 弁論の全趣旨によると、次の事実(ただし、当裁判所に顕著な事実を含む。)が認められる。
(一)本件訴訟の手続においては、当事者双方において争点に関する主張を尽くした上で人証の証拠調べが実施されたが、被告らは、その証拠調べの手続が終了した後であって、口頭弁論を終結する予定であった第六回口頭弁論期日(平成16年7月27日)の11日前である同月16日に、乙第28号証から第37号証までの写しを当裁判所に送付した。
(二)乙第28号証から第36号証までには、原告名義の銀行預金及び郵便貯金の口座の出入金の流れを証する書面(乙第28号証及び第29号証)、乙太郎名義の銀行預金の口座の出入金の流れを証する書面(乙第30号証)、原告が勤務していた丙山社の代表者が原告を解雇した理由を説明して原告を非難する陳述書(乙第31号証)、原告が勤務していた丁川社の代表者が原告を解雇した理由を説明して原告を非難する陳述書(乙第32号証)並びにこれらに関連する書証(乙第33号証から第36号証まで)が含まれている。そして、被告らの平成16年7月27日付けの準備書面(2)によると、被告らは、前記第二の四2(一)(3)ウの主張を証する書証として、乙第28号証から第30号証までを提出し、同エの主張を証する書証として、乙第31号証から第36号証までを提出しようとしたものであるが、前記第二の四2(一)(3)ウの主張も、同エの主張も、前記準備書面において初めてされたものである。なお、乙第37号証は原告の仮放免の事実を証するものであって、その提出に格別の問題はない。
また、平成16年5月10日の証拠調べの際の証人丙川及び原告本人の各主尋問における供述の内容は、原告の従前の主張事実及び甲第11及び第12号証における陳述内容と格別異なるものではないから、乙第28から第36号証までが、上記証拠調べに対する弾劾のため新たに必要となったものであるということはできない。
(三)原告は、乙第28号証から第36号証までの証明力を減殺する目的で、平成16年7月20日、甲第20号証から第30号証までの写しを当裁判所に送付した。
(四)当裁判所は、平成16年7月27日の第六回口頭弁論期日において、甲第20号証から第30号証まで及び乙第28号証から第37号証までを取り調べた。原告及び被告らは、同期日において、他に主張立証がない旨述べ、当裁判所は、同期日において、予定どおり口頭弁論を終結した。
2 民事訴訟法157条1項に規定する「時機に後れて提出した」とは、口頭弁論期日等に提出された攻撃又は防御方法をそれ以前に提出し得た場合をいうところ、前記認定事実によれば、被告らが第六回口頭弁論期日に提出した書証のうち乙第28号証から第36号証までは、時機に後れて提出されたものと見るべきであり、公平な審理手続及び集中証拠調べの趣旨に反するものであって、このような立証活動の遅れ(さらに言えば主張の遅れ)については、当裁判所としては極めて遺憾である。
しかしながら、これらの乙号各証は、即時取調べが可能である上、前記の第六回口頭弁論期日の手続経過及び後述するその証明力や本訴の争点の帰すうに対する影響等に照らすと、その提出によって本件訴訟の手続の完結を遅延させることになるものと認めることはできない。
したがって、結局のところ、乙第28号証から第37号証までを時機に後れた攻撃防御方法に当たるものとして却下することはできない。
二 前記前提となる事実に加え、《証拠略》を総合すると、以下の事実を認めることができる。
1 原告の入国、在留状況、丙川との交際状況等について
(一)原告(昭和48年4月21日生)は、満州民族であって、中国のいわゆる地方出身者であったが、勉学に努め、平成元年9月、錦州市第一師範学校幼児教育学科(中専)に入学して、平成4年7月、同校同科を卒業し、さらに選抜されて、同年9月、遼寧省芸術幼児師範学校学前教育大専に入学した。原告は、難関の試験を突破して、国費留学生に選ばれ、日本で幼児教育について勉強することとなり、平成6年4月4日(当時20歳)に来日して、入国審査官から、入管法別表第一に定めるビザ「留学」、在留期間「1年」とする上陸許可を受けて、本邦に上陸した。原告は、国費留学生として、月額約14万円の奨学金の支給を受けていた。
(二)原告は、平成6年4月8日、東京都杉並区長に対し、外登法に基づく新規登録申請をし、外国人登録証明書の交付を受けた。原告は、同月、渋谷区内にある丁原専門学校日本語学科に入学して、日本語及び日本の文化・習慣の勉強を始めた。原告は、本邦に上陸前に遼寧省芸術幼児師範学校の卒業に必要な単位をすべて取得していたので、同年7月、同校の卒業証書を授与された。原告は、平成7年3月8日、丁原専門学校日本語学科を卒業した。
原告は、同月23日、東京人管において、法務大臣に対し、在留期間更新許可申請をし、同年4月12日、在留期間「1年」とする許可を受けた。原告は、同月、板橋区内にある戊田専門学校幼児教育学科に入学し、勉学にいそしんだ。原告は、同月19日、板橋区長に対し、居住地変更登録をした。
原告は、平成8年3月26日、東京入管において、法務大臣に対し、在留期間更新許可申請をし、同年5月31日、在留期間「1年」とする許可を受けた。
原告は、平成9年2月26日、東京入管において、法務大臣に対し、在留期間更新許可申請をし、同年4月23日、在留期間「1年」とする許可を受けた。原告は、同年3月19日、戊田専門学校幼児教育学科を卒業し、保母資格証明書及び幼稚園教諭二種免許状を授与された。原告は、国費留学生としての期間が同月で終了したが、更に日本での勉強を続けたいと考え、同年4月、私費留学生となって、戊田専門学校幼稚園教諭保母養成専攻科に入学した。
(三)原告は、本邦に上陸して1年を経過したことから、日本語を学び日本社会に溶け込むためとともに、貯金を貯めようと考えて、週末等に、レストランやイトーヨーカドーなどでアルバイトをするようになった。それによって得た所得や奨学金等を蓄えていた分は、平成9年4月当時で、原告の1年分の生活費に近いほどに達していた。
(四)乙太郎は、中国国籍を有する外国人であって、北京市出身の漢民族であり、中国の難関大学である清華大学を卒業後、日本での留学を経て、日本で就職し、入管法別表第一に定めるビザ「人文知識・国際業務」により本邦に在留していた。原告は、来日直後である平成6年から、乙太郎とは知り合いであったが、平成9年ころ、乙太郎と恋愛関係となり、同年12月、乙太郎の子を妊娠していることに気付いた。原告と乙太郎は、話し合った結果、婚姻することを決め、同月18日、乙太郎の両親の承諾を得ることなく、本邦において婚姻した。原告は、つわりがひどかったので、中国に戻って出産することにした。
原告は、同月26日、東京入管において、法務大臣に対し、入管法別表第一に定めるビザ「留学」から入管法別表第一に定めるビザ「家族滞在」へ変更する旨の在留資格変更許可申請をし、平成10年1月19日、入管法別表第一に定めるビザ「家族滞在」、在留期間「1年」とする許可を受けた。原告は、再上陸の許可を受けた上で、同年2月10日ころ、中国に向けて出国し、北京市内にある乙太郎の実家に身を寄せたが、このとき初めて、乙太郎の両親が原告と乙太郎との婚姻に反対していることを知った。原告は、同年7月1日、長女乙一江を出産した。原告は、出産後、原告の実家に戻って、乙一江の面倒をみていたが、乙太郎が乙一江を日本に連れてくることに強く反対したため、原告は、同年9月、乙一江を原告の実家に預けたまま、本邦に再入国した。
原告は、中国に滞在中の同年3月23日、戊田専門学校幼稚園教諭保母養成専攻科を卒業した。
(五) 原告は、平成10年12月11日、東京入管において、法務大臣に対し、在留期間更新許可申請をし、同月25日、在留期間「1年」とする許可を受けた。原告は、平成11年1月11日、板橋区長に対し、居住地変更登録をした。原告は、東京入管において、法務大臣に対し、再入国許可申請をし、同年2月5日、有効期限を「平成12年1月19日」までとする許可を受けた上、平成11年2月10日、乙太郎とともに、成田から北京に向けて出国し、乙一江と再会し、同年3月10日、乙太郎とともに、本邦に再入国した。原告は、出産後、平成10年9月に本邦に帰国してから、上記出国前の平成11年1月末まで、レストランでアルバイトをしていた。(六)原告は、平成11年4、5月ころ、資格外活動の許可を得ずに、旅行業を営む甲田社に、パートタイマーとして就職した。原告は、語学と人文知識にはたけていたが、旅行業については、学んだことはなかった。しかし、原告は、同社における上司であった丙川の指導の下、熱心に旅行業に関する知識を吸収した。原告は、一生懸命な仕事ぶりと気配りのよさにより同僚の評判も良かった。なお、その間、原告は、同年6月25日、成田から北京に向けて出国し、同年7月5日、本邦に再入国した。
(七)原告は、平成11年11月、乙太郎が就職した乙野社の旅行部の仕事を手伝うため、甲田社を退職し、同年12月ころから三か月ほど、資格外活動の許可を得ずに、乙野社で働いた。
原告は、平成12年1月6日、東京入管において、法務大臣に対し、在留期間更新許可申請をし、同月17日、在留期間「3年」とする許可を受けた。この許可に係る在留期限は、平成15年1月19日であった。
原告は、東京入管において、法務大臣に対し、再入国許可申請をし、平成12年2月21日、有効期限を「平成15年1月19日」までとする許可を受けた。原告は、平成12年3月2日、北京に向けて出国し、乙一江と再会し、同年5月18日、乙太郎の両親を連れて、成田に到着し、本邦に再入国した。
原告は、平成12年7月4日、板橋区長に対し、居住地を本件マンションの所在地とする居住地変更登録をした。
(八)原告は、平成12年7月、資格外活動の許可を得ずに、旅行業を営む丙山社に就職した。乙太郎は、そのころ、乙野社を退職し、同年10月ころ、両親とともに、中国に向けて出国した。原告は、平成13年1月18日、成田から北京に向けて出国し、同年2月1日、乙太郎とともに、本邦に再入国した。しかし、乙太郎は、日本で就職することができず、アルバイト等をしていた。
原告は、株式会社甲川の「国際予約短期コース」を受講し、同年5月11日、そのコースを修了した。
原告は、同年8月17日、東京入管において、法務大臣に対し、勤務先を丙山社、週間稼働時間を25時間とする旨の資格外活動許可申請をした。法務大臣は、原告に対し、同月28日、「丙山社において旅行関連業務全般に従事する活動」につき、「平成15年1月10日」の期限で許可をした。原告は、丙山社において、週の半分くらい出勤して一生懸命に働き、航空券の売上げも一位となったが、独立するといううわさが流れたことなどから、平成14年1月、丙山社を解雇された。
(九)原告は、乙太郎との性格の不一致や、乙太郎が就職しないこと、中国のいわゆるエリートである乙太郎の両親等が原告のことをよく思ってくれないこと、乙太郎が子供である乙一江を日本に呼び寄せてくれないことなどから、乙太郎との生活に行き詰まり、平成14年初めに、乙太郎との離婚を決意した。原告は、離婚して、中国で生活することも選択肢の一つと考えながら、同年2月4日、中国に帰国して、親族に離婚のあいさつをするとともに、就職の可能性等を調べた。しかし、錦州市等において、保母等として働くことは難しいと判断し、日本での生活を続けていくことを決め、同月25日、本邦に再入国し、同月27日、乙太郎と協議離婚した。しかし、乙太郎には、就職先も、住むところもなく、乙太郎が「在留期限である同年10月上旬には中国に帰国する。」と言うので、原告と乙太郎は、離婚後も、本件マンションの別々の部屋で同居を続けた。
(十)原告は、旅行業を営む丁川社の社長である乙原竹子(以下「乙原」という。)から、「就労ビザを取得してあげる。」などと誘われて、平成14年3月、同社に就職し、同社の池袋支店長に就任した。原告は、同月29日、東京入管において、法務大臣に対し、勤務先を丁川社、週間稼働時間を25時間とする旨の資格外活動許可申請をした。法務大臣は、原告に対し、同年4月12日、「丁川社において旅行関連業務全般に従事する活動」について、期限を「平成15年1月19日」とする許可をした。
(十一)原告は、平成14年4月24日、東京入管において、法務大臣に対し、在日親族を「乙太郎」として、入管法別表第一に定めるビザ「家族滞在」から入管法別表第一に定めるビザ「人文知識・国際業務」へ変更する旨の在留資格変更許可を求める第一次申請をした。法務大臣から権限の委任を受けた被告東京入管局長は、同年9月2日、原告の専門学校での専攻と職務内容に関連性がないことと、原告から提出された履歴書に記載された遼寧省芸術幼児師範学校学前教育大専の卒業年月と同校の卒業証明書に記載された卒業年月が食い違っていることを理由に、第一次申請について、不許可処分をした。なお、原告は、同年4月26日、成田から北京に向けて出国し、同年5月6日、本邦に再入国した。
(十二)原告は、離婚した乙太郎が本件マンションに居座っていること等から、精神的に疲弊し、平成14年4月ころから、原告が甲田社に勤務していたときの上司であった丙川と会うようになっていった。原告は、丙川にそれまでの事情や思いを話すようになり、話を聞いた丙川は、原告に同情し、同年のゴールデンウィークの後ころから、二人は、親しく交際するようになった。
(十三)丙川は、平日、原告と夕食を食べに行くことが増え、週末も、二人で会うようになった。原告は、平成14年7、8月ころから、丙川と結婚したいと考えるようになり、丙川も、そのころから、原告との結婚を意識した交際をするようになった。そして、同年8月末ころ、原告と丙川は将来の結婚を約束した。
(十四)原告は、平成14年8月23日、転倒事故により、左顔面打撲、左前腕打撲血腫及び左下肢打撲裂傷の傷害を受け、同日から同年9月10日まで、病院で七針縫うなどの治療を受けた。原告は、同年8月23日から同年9月10日までの16日間欠勤したことを理由に、損害保険会社から、20万4397円の支払を受けた。もっとも、原告は、自分が担当していた顧客に対する請求予定の書面をファックスにより顧客あてに送信するなどのために、短時間だけ出社したことがあり、また、同月28日以降は、会社では出勤扱いになっていないものの、病院に行った後、勤務先に寄り、相当時間、その業務を行っていた。
原告は、第一次申請についての不許可処分後、乙原社長が、逆に、出勤日の増加を求めたことなどから、勤務条件をめぐって、乙原社長との間でトラブルが生じ、同年10月、丁川社を退職した。原告は、同年11月、丙川の紹介で、同じく旅行業を営む戊原社にパートタイマーとして就職した。原告は、戊原社でも、一生懸命に働き、成績も優秀であった。
(十五)原告と丙川は、平成14年10月ころから、離婚した乙太郎も住んでいる本件マンションから原告が引っ越すための転居先を探し始めた。しかし、乙太郎は、その後、在留期限を経過した後も本邦に不法残留していることを理由に、東京入管に収容され、原告は、同年11月7日に、乙太郎からの連絡でそのことを知った。乙太郎は、同月15日、中国に強制送還された。そのため、原告と丙川は、原告の転居先を探すのを取りやめた。
(十六)原告と丙川との関係は、乙太郎がいなくなったため、更に確固としたものとなり、平成14年12月からは、丙川は、本件マンションに頻繁に泊まっていくようになった。丙川は、原告と二人でイタリアとフランスヘ旅行することを計画した。丙川は、当時、両親に、結婚を前提に交際している女性がいることを告げていたが、この旅行に際して、その相手が中国人女性であることを両親に教えた。原告と丙川は、同月27日、成田からヨーロッパに向けて出国し、平成15年1月8日、ヨーロッパから帰国した。原告と丙川は、その間、将来のことを話したり、楽しく過ごした。丙川は、ヨーロッパから帰国した後は、週の半分以上、本件マンションに泊まり、週末等に実家に帰るようにし、衣類等も、少しずつ本件マンションヘ運び込み、大家の了解も得て、いわば半同居といった生活を送っていた。丙川は、家賃、光熱費等を負担したり、原告と共同で生計を維持していたわけではなかったが、二人の飲食代を負担したほか、一部の買物代金を負担するなどしていた。また、丙川と原告は、婚姻後に乙一江を日本に呼んで三人で暮らそうと話していた。
しかし、丙川は、一人っ子の長男であって、両親とも仲が良く、これまで主に実家で暮らしていたため、外国人であって、離婚歴があり、子供もいる原告との結婚を両親等に承諾してもらうためには、手順と時間が必要であると考えており、平成15年3、4月ころに原告を両親や親族に合わせ、それから結婚式の日取り等を決めようと考えていた。丙川の頭の中には、同年6月ころの結婚という考えもあったが、丙川及び原告は、同年2、3月当時は、まだ、正式な結婚に至る具体的な手順や日程を決めていなかった。
(十七)原告は、平成15年1月16日、行政書士の指導に従い、法務大臣に対し、在日親族を「乙太郎」として、入管法別表第一に定めるビザ「家族滞在」から入管法別表第一に定めるビザ「人文知識・国際業務」へ変更する旨の在留資格変更許可を求める第二次申請をした。原告と丙川は、これにより、原告の日本での在留が安定し、結婚へと進むことができると考えていたが、法務大臣から権限の委任を受けた被告東京入管局長は、同年2月25日、乙太郎とは第二次申請以前に離婚し、同人が中国に帰っていたのに、在日親族として「乙太郎」を記載したこと、及び原告から提出された履歴書に記載された遼寧省芸術幼児師範学校学前教育大専の卒業年月と同校の卒業証明書に記載された卒業年月が食い違っていることを理由に、第二次申請につき不許可処分をし、同年3月12日、これを東京入管に出頭した原告に通知した。
これにより、原告は、在留期限である同年1月19日を超えて本邦に不法に残留することとなった。
(十八)原告は、流ちょうに日本語を話すことができ、日本語の読み書き能力も十分な程度に達している。また、一般人文知識や旅行業について相当の知識を有している。
2 原告の収容、退去強制手続、丙川との関係等について
(一)東京入管入国警備官は、平成15年3月12日、被告主任審査官から原告に対する収容令書の発付を受けた。原告は、東京入管の求めに応じて、同日、東京入管に出頭したところ、東京入管入国警備官は、出頭した原告に対し、収容令書を執行し、原告を東京入管収容場に収容した。
(二)丙川は、原告が東京入管収容場に収容された後、本件マンションで暮らしながら、2日に一回は、原告と面会するために東京入管収容場を訪問した。原告は、日本でのビザを得るため、丙川に対し、平成15年3月20日ころ、「婚姻してほしい。」旨申し入れた。丙川は、原告がまじめな人間であって、丙川とも愛し合っていたため、いずれ釈放されて、再び二人で暮らすことができるはずであると安易に即断していたことや、収容中の原告を両親に紹介することはしたくなかったため、いったんは、直ちに入籍することを断った。その後、丙川は、中国へ帰る旨記載された同年3月21日付けの原告の手紙(甲10の三)を読んで、事態の深刻さを理解し、収容中でも入籍することを決め、同年4月初めころの面会の際に、その旨を原告に伝えた。
(三)東京入管入国審査官は、平成15年3月25日、原告の違反審査をしたが、その際の審査調書(乙11)には、原告の供述として、「身元保証人が必要であれば、恋人の丙川にお願いします。」、「彼とは去年の8月ころから恋人として交際しています。」、「彼とはうまくいったら結婚します。具体的に結婚がいつになるかは分かりません。日本に残るために結婚すると思われるのが嫌なのです。」、「私はずっと日本にいて日本の生活に慣れています。私は今の会社の仕事も好きだし、周りの人とも仲良くやっています。できればずっと日本にいたいです。私の人脈はすべて日本にあります。中国にはありません。私は日本が本当に好きです。自分の夢があるし、好きな人も日本にいます。だからこれからも日本の社会に一人の女性として日本にいたいです。私は日本と中国のかけはしになりたいです。このまま中国に帰ると自分の人生が中途半端なものになってしまいます。」、「私が日本にこのままいられるようお願いします。」などとの記載がある(なお、原告は、本人尋問において、「恋人」とは、婚約者の意味で述べたものであると供述している。)。
東京入管特別審理官は、平成15年4月7日の原告に係る口頭審理に先だって、丙川を呼び出して質問をした。丙川は、担当職員から公的なものではないというような話をされ、自分の供述内容が原告への処分結果に影響するなど、この事情聴取の重要性を説明されていなかったため、雑談的なものと思い、入籍する前に女性と寝食を共にしていたと認めることは恥ずかしいと考えて、原告が恋人であって婚姻予定であることは答えたものの、半ば同居していたことなど、丙川と原告との正確な交際状況については供述しなかった。
(四)その後、東京入管特別審理官は、原告に係る口頭審理(その審理調書が乙13である。)を実施したが、原告は、丙川の立会いの下、「日本には恋人がいます。恋人と結婚して、夫の面倒を見て、支えていきたいと思っています。」、「恋人の仕事は日本にあるため、私たちは中国に行って生活することができません。」、「好きな日本で好きな人と結婚して頑張っていきたいと思います。」、「1日でも早く許可していただき、外に出て、お互いの親にあいさつしたいと思いますので、是非よろしくお願いいたします。」、「2002年12月27日から2003年1月8日には二人でイタリアとパリに海外旅行をしました。その後は、週末だけでなく、より頻繁に会っています。」、「本年2月以降貴局に収容されるまではほとんど同居している状態ですが、1日ぐらい自分の家に帰る時もありました。」、「平成15年4月2日か、3日には母に依頼して、丙川との婚姻手続のために必要な原告の出生証明書及び家族証明書を中国から取り寄せ中である。」旨述べた。東京入管特別審理官は、改めて丙川を尋問したり、あるいは別途供述調書を作成することはしなかった。
(五)そのころ、丙川は、中国大使館に赴いて、原告との婚姻の手続を進めた。丙川は、丙川の両親に事情を打ち明けて、当初は原告との婚姻に反対した両親を説得し続けた結果、両親も原告との婚姻に賛成した。また、原告も、中国の母に対し、前記口頭審理の直前ころ、丙川との婚姻手続のために必要な書類の取り寄せを依頼した。
(六)原告は、平成15年4月9日に本件裁決を、同月10日に本件退令処分を受けた後、同年5月20日、長崎県の大村センターに移収された。
3 本件裁決及び本件退令処分の処分後の事情について
(一)原告は、板橋区長に対し、平成15年5月22日、丙川と原告が婚姻する旨の届出をした。
(二)丙川は、原告が大村センターに移収された後も、多数のテレフォンカードを買って、原告に与え、原告は毎日、丙川と連絡を取った。また、丙川は、月に、二回から四回も長崎県の大村センターにまで赴いて、原告と面会したり、日常品を送るなどしていた。これらによる丙川の出費は多額に上ったが、丙川は、精神的に不安定になり、健康状態も余り良くなかった原告を支えるため、後述の仮放免まで約1年一か月の間、このような面会と電話連絡等を継続した。
(三)丙川の両親も、原告についてよく知るにつれ、原告を長男の嫁として好ましく思うようになり、大村センターも訪問した(訪問は当裁判所に顕著な事実である。)。
(四)原告は、平成16年6月18日、仮放免され、丙川と一緒に本件マンションで暮らすこととなった。
(五)原告と丙川は、現在も、同居しているが、その夫婦関係は良好である。
(六)原告は、日本で、丙川及び乙一江とともに、丙川の妻及び乙一江の母として暮らしていくことを強く希望している。丙川も、これに賛成している。
(七)原告の長女乙一江は、現在、中国にいる原告の母によって育てられており、その養育状況に格別の問題はない。原告は、収容前から、乙一江に丙川のことを「日本のパパ」として知らせており、日本語の勉強をさせるなどして、来日の準備もしている。
(八)原告が勤務したことがある丙山社の代表取締役である丁梅夫は、原告について、売上金の一部を着服したから原告を解雇した旨、原告を強く非難する陳述書(乙31)に署名押印しており、また、原告が勤務したことがある丁川社の社長である乙原は、原告について、会社に無断でテレホンカードを仕入れて販売しその利益を自分のものにしたり、虚偽の売上げを報告して売上金の一部を横領したりするなどして、会社に損害を与えた旨、原告を強く非難する陳述書(乙32)に署名押印している。
他方、原告が東京入管収容場に収容されるまで勤務していた戊原社の代表者である丁野春子を始めとして同社の社員は、原告をまじめで優しい人物であると評価しており、原告の周囲の中国人や日本人の原告に対する評判は悪くない。
(九)原告は、資格外活動をしたことや、入管法による各種申請を適正にしなかったことにつき、現在では深く反省しており、今後は、法的知識を得た上、法令に従った行動を取ることを誓っている。
4 原告の資産等について
原告は、東京入管収容場に収容された平成15年3月12日の時点において、現金として218万1076円、みずほ銀行西池袋支店の預金、富士銀行(現在の名称はみずほ銀行)新宿西口支店の預金、さくら銀行(現在の名称は三井住友銀行)新宿新都心支店の預金及び住友銀行(現在の名称は三井住友銀行)新宿支店の預金として、合計110万5319円、郵便貯金として650万円を有していたこと。これらは、原告が平成6年4月4日に本邦に上陸した以降に得た奨学金や日本において稼働するなどして得た所得と、乙太郎と婚姻していた期間中に乙太郎が稼働するなどして得た所得ないし離婚時の給付等を蓄えていたものである。このうち郵便貯金については、原告は、平成15年3月20日、これを解約し、651万6702円の払戻しを受け、これを中国にいる原告の母あてに乙一江の養育費として送金した。以上のほかには、日本にも、中国にも、原告のめぼしい資産はない。
5 賞罰等について
原告は、中国又は日本において、有罪判決を受けたり、警察に逮捕されるなど刑事捜査の対象となったことはない。
三 事実認定に関する補足説明(原告と丙川の同居状況及び婚約に関する事実について)
1 平成14年12月ころから原告の収容された平成15年3月12日までの原告と丙川との関係については、丙川は、前述のように、口頭審理前に、東京入管特別審理官から聴取を受けた際に、本件マンションにおいて原告と同居しているとか、半ば同居しているなどとは述べていないことが認められる。
また、婚約の事実についても、丙川が、上記聴取の際に、平成14年8月末に結婚を約したとか、原告と近々結婚すると明確に述べたことを認めるに足りる証拠はなく、むしろ述べていない可能性がある。原告の平成15年3月25日の違反審理の際も、前記認定事実に照らすと、丙川が恋人であって、結婚を考えていることは述べたものの、近々結婚するとまでは述べていないものと認められる。また、丙川は、いったん入籍を断ったこともある。
2 しかし、平成14年4月ころから平成15年5月22日の入籍に至るまでの原告と丙川の交際や同居状況、結婚に対する考え方の推移等に関する丙川及び原告の各陳述書(甲11、12、平成15年4月7日の口頭審理における原告の供述(乙13)並びに証人丙川の証言と原告本人尋問の結果は、具体的で詳細なものであり、婚姻に関する両名の心理の動きや、丙川が半ば同居状態にあったことを東京入管の担当職員に述べなかった心理状況も、十分理解し得るところである。そうすると、上記各証拠のほか、原告が東京入管収容場に収容されていた時及び大村センターに収容されていた際の丙川と原告との極めて頻繁な音信、面会状況や、前記口頭審理の当時、原告及び丙川が既に入籍の準備を開始していたこと、現に、平成15年5月22日に入籍が実現していること、丙川の両親の対応等を総合勘案すると、上記入籍前から、原告と丙川との間には、極めて濃密な関係が成立しており、前記認定のように、平成14年8月末ころに婚姻の約束をして、それが徐々に具体化し、平成15年1月8日以降、半同居の状態となっていったと認めるのが相当である。
第四 争点1(本件裁決の適法性)について
1 判断枠組みについて
被告東京入管局長に権限の委任をしている法務大臣の裁量権について検討する。
(一)憲法22条1項は、日本国内における居住・移転の自由を保障するにとどまっており、憲法は、外国人の日本へ入国する権利や在留する権利等について何ら規定しておらず、日本への入国又は在留を許容すべきことを義務付けている条項は存在しない。このことは、国際慣習法上、国家は外国人を受け入れる義務を負うものではなく、特別な条約がない限り、外国人を受け入れるかどうか、受け入れる場合にいかなる条件を付するかについては、当該国家が自由に決定することができるとされていることと考えを同じくするものと解される。したがって、憲法上、外国人は、日本に入国する自由が保障されていないことはもとより、在留する権利ないし引き続き在留することを要求する権利を保障されているということはできない。このように外国人の入国及び在留の許否は国家が自由に決定することができるのであるから、我が国に在留する外国人は、入管法に基づく外国人在留制度の枠内においてのみ憲法に規定される基本的人権の保障が与えられているものと解するのが相当である(最高裁昭和五三年一〇月四日大法廷判決・民集32巻7号1223頁、同昭和三二年六月一九日大法廷判決・刑集11巻6号1663頁参照)。
(二)入管法2条の2、7条等は、憲法の前記の趣旨を前提として、外国人に対して原則として一定の期間を限り特定の資格により我が国への上陸、在留を許すものとしている。したがって、上陸を許された外国人は、その在留期間が経過した場合は当然我が国から退去しなければならないことになる。そして、入管法21条は、当該外国人が在留期間の更新を申請することができることとしているが、この申請に対しては法務大臣が「在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。」ものと定められている。これらによると、入管法においても、在留期間の更新が当該外国人の権利として保障されていないことは明らかであり、法務大臣は、更新事由の有無の判断につき広範な裁量権を有するというべきである(前掲昭和53年最高裁判決参照)。
(三)また、入管法50条1項3号は、49条1項所定の異議の申出を受理したときにおける同条3項所定の裁決に当たって、異議の申出が理由がないと認める場合でも、法務大臣は在留を特別に許可することができるとし、入管法50条3項は、この許可をもって異議の申出が理由がある旨の裁決とみなす旨定めている。
しかし、(1)前記のように外国人には我が国における在留を要求する権利が当然にあるわけではないこと、(2)入管法50条1項柱書及び同項3号は、「特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき」に在留を特別に許可することができると規定するだけであって、この在留特別許可の判断の要件、基準等については何ら定められていないこと、(3)入管法には、そのほか、前記在留特別許可の許否の判断に当たって考慮しなければならない事項の定めなど上記の判断をき束するような規定は何も存在しないこと、(4)在留特別許可の判断の対象となる者は、在留期間更新の場合のように適法に在留している外国人とは異なり、既に入管法24条各号の規定する退去強制事由に該当し、本来的には退去強制の対象となる外国人であること、(5)外国人の出入国管理は、国内の治安と善良な風俗の維持、保健・衛生の確保、外交関係の安定、労働市場の安定等、種々の国益の保持を目的として行われるものであって、このような国益の保持の判断については、広く情報を収集し、時宜に応じた専門的・政策的考慮を行うことが必要であり、時には高度な政治的判断を要することもあり、特に、既に強制退去されるべき地位にある者に対してされる在留特別許可の許否の判断に当たっては、このような考慮が必要であることを総合勘案すると、前記在留特別許可を付与するか否かの判断は、法務大臣の極めて広範な裁量にゆだねられていると解すべきである。そして、その裁量権の範囲は、在留期間更新許可の場合よりも更に広範であると解するのが相当である。したがって、これらの点からすれば、在留特別許可を付与するか否かについての法務大臣の判断が違法とされるのは、その判断が全く事実の基礎を欠き又は社会通念上著しく妥当性を欠くことが明らかであるなど、法務大臣が裁量権の範囲を逸脱し又は濫用した場合に限られるというべきである。
(四)これに対し、原告は、憲法22条1項、同条2項等を根拠に、我が国に入国した外国人に在留する権利が憲法上保障されていると主張し、それを前提に、B規約21条、国連移住労働者条約69条2項等を参考に、不法滞在者が市民として我が国に定着しているか否かという観点から、在留特別許可を認めるかどうかを判断すべきである旨主張する。
しかし、我が国に入国した外国人に在留する権利が憲法上保障されていないことは、前記のとおりであるから、原告の主張は、その前提を欠いており、その余の点について判断するまでもなく、採用することができない。
2 裁量権の逸脱又は濫用の判断について
そこで、以上の判断の枠組みに従って、法務大臣から権限の委任を受けて、原告に在留特別許可を付与しないとした被告東京入管局長の判断に裁量権の逸脱又は濫用があるといえるか否かについて検討する。
(一)(1)前記前提となる事実及び前記認定事実によると、(1)原告は、本邦に上陸した当初の目的である幼児教育の勉強については既にこれを達成していること、また、(2)原告は、幼児教育の勉強のために通っていた専門学校の卒業後も乙太郎とともに本邦に在留して続けるために、ビザを「留学」から「家族滞在」に切り替えたものの、平成14年2月27日には、乙太郎と離婚し、同年11月15日に乙太郎が中国に帰ったのであるから、もはや、本邦に在留を続ける理由がなくなったにもかかわらず、原告は、その後も、既に実体を欠いているビザ「家族滞在」により本邦に在留を続けていたこと、(3)原告は、第二次申請の際に既に離婚して帰国していた乙太郎のことを「在日親族」であると虚偽の記載をしたこと、(4)原告は、本邦に在留していた9年近くの間のうち約7年にわたって、アルバイト、パートタイマー、あるいは正規従業員として就労していたことが認められる。殊に、専門学校卒業後、資格外活動の許可を得ずに、あるいはその許可を得る前から複数の旅行業の会社で長時間勤務していたことは、入管法19条1項に違反する行為の反復継続として、目に余る行為であるといわざるを得ない。
(2)そうすると、原告が本邦に上陸した当初の目的である幼児教育の勉強については既にこれが達成されている上、原告の本邦における在留中の素行には不良な点もあり、これは、在留特別許可を付与すべきではない事情としてしんしゃくすべきであるということができる。
(3)もっとも、前記認定事実に照らすと、原告の学生時代の就労は、軽易なアルバイト程度のものであり、また、専門学校卒業後の就労についても、《証拠略》によると、当初は法的無知が原因であり、その後は、資格外活動の許可やビザの変更が得られるものと信じて、就労の場を確保しようとしたものと認められ、日本の入管行政や法令に敵対的な考えの下に、これらを強行したり、あるいは隠れて実行していたわけではないというべきである。
また、《証拠略》によると、在留資格変更許可を求める第二次申請の申請書の「在日親族」の記載については、行政書士の指示に従ったものであって、原告には悪意はなく、違法性の意識も乏しかったことが認められる。
(4)以上によれば、原告が前記のような資格外活動等を行ったことは看過することはできないものの、本件は、当初から就労目的を秘して違法に本邦に入国したり、隠れて専ら就労を継続していたような事案とは大きく異なり、当該活動の内容や、資格外活動の許可歴、原告の反省、他の点ではまじめに生活し、周囲の評判もよいこと等を勘案すると、前記(1)の点のみを過度に重視することは不相当というべきである。
(二)他方、前記認定事実によると、(1)原告は、これまで、日本及び中国において、警察に逮捕されたり、捜査を受けるなど、刑事事件を引き起こしたことはないこと、(2)原告の本邦への入国は適法なものであり、それから3年数か月の間、まじめに学業にいそしんだこと、(3)原告の約9年間に及ぶ本邦での滞在のうち、不法残留は、平成15年1月19日からであって、収容までは二か月未満の期間である上、この不法残留は、原告のした在留資格変更許可申請の不許可(同年3月12日通知)によって明らかとなったものであり、原告は、収容された日でもある同日までは、不法残留を認識していなかったこと、(4)平成6年4月4日に20歳で来日してから、本件裁決及び本件退令処分の時まで約九年間日本に滞在し、中国での就労経験はなく、成人後の大半の期間を日本で過ごしてきたこと、(5)原告は、日本語会話がたん能であって、日本語の読み書きもでき、幼児教育はもちろん、一般人文知識や旅行業についても、相当の知識を有していること、(6)原告は、予期しない妊娠から、結婚することとなって、家庭を持ち、その後、資格外活動も見られるが、同年3月12日に収容されるまでの原告の生活は、おおむね勤勉かつまじめなものであり、周囲の中国人や日本人の評判も、一部トラブルとなった雇用主を除けば、良好であること、(7)原告は、本件裁決及び本件退令処分当時、日本に在留して、結婚を約した丙川と幸せな家庭を築きたいと、真しに希望していたこと、(8)原告と丙川は、平成15年8月末ころに将来の結婚を約し、平成16年1月8日以降は、半ば同居の状態にあったこと、(9)本件裁決の時点において、原告と日本人である丙川は、近々入籍することを決めて、その手続を開始していたことを認めることができる。
また、在留特別許可が年間1000件を超える規模で行われており、平成15年においては、1万3000件を超えていること、在留特別許可が発せられる一つの典型例が日本人の配偶者の場合であることは、当裁判所に顕著な事実である。
もっとも、原告と丙川が正式な入籍を決めたのは、原告が東京入管収容場に収容された後のことであって、本件裁決の直前である上、処分時である本件裁決の時点においては、入籍していなかったものであるが、前記のとおり、その前後の事実経過も勘案すると、本件裁決の時点において、現に原告と丙川との関係は、極めて濃密なものであり、正式な婚姻の上、通常の夫婦生活が継続される可能性が極めて高かったと推認するのが相当である。そして、前記認定事実によると、原告が、中国に強制送還された場合、婚姻した丙川と我が国において同居することが不可能となり、また、両者が中国において同居して生活することも困難であることが認められ、この点は、在留特別許可を付与するか否かの判断に当たって慎重に考慮すべき事情というべきである。
(三)ところが、被告東京入管局長は、平成15年4月7日の口頭審理の2日後の同月9日に異議に理由はない旨の本件裁決をしており、弁論の全趣旨によれば、その際、被告東京入管局長は、原告と丙川は、収容前には同居ないし半同居の状態になく、結婚の約束もしておらず、結婚の可能性も不分明であるとの前提の下、原告と丙川との関係を考慮の対象から外して、本件裁決をしたことが認められる。
しかし、既に判示したところに照らせば、原告は、本件裁決当時において、国費留学生として来日し、適法に本邦に上陸して、勉学にいそしみ、勤勉かつまじめに暮らし、丙川と深い愛情に結ばれて、夫婦同様の生活をし、近々法律上の婚姻をする予定であり、前述のような素行不良な点もあるものの、おおむね善良な市民として日本の社会に定着していたということができる。そうすると、このような丙川との関係及び原告の第二次申請の不許可によって初めて不法残留が明確化したものであって、不法残留期間が短いこと等を考えると、被告東京入管局長が原告の丙川との婚姻可能性やその夫婦関係の安定性等を適正に認定していれば、同被告は、原告に在留特別許可を付与した可能性が高いと認めることができる。そうすると、原告に在留特別許可を付与しなかった本件裁決は、その判断が全く事実の基礎を欠き又は社会通念上著しく妥当性を欠くことが明らかである。
したがって、前記のとおり、在留特別許可を付与するか否かについて法務大臣から権限の委任を受けた被告東京入管局長に与えられた裁量権が極めて広範なものであることを前提としても、原告に在留特別許可を付与しなかったことは、裁量権の逸脱又は濫用に当たるというべきである。
3 補足説明
(一)原告の預貯金等について
(1)被告らは、原告の名義の預金口座に平成9年5月9日から同年12月18日まで入金されていた合計約451万円は原告が正業により得たものとは考え難く、原告が平成7年9月22日から平成10年7月27日まで郵便局に有していた約300万円もの貯金も原告の正業による収入とは考え難いと主張し、また、平成10年6月29日から同年9月3日までにシティバンク赤坂支店の乙太郎名義の口座に入金されている約2900万円も正業により得られたものとは考え難く、原告がその取得に全く関与していなかったとは考えられない旨主張する。
(2)そこで検討するに、《証拠略》によると、次の事実が認められる。
ア シティバンク池袋支店には、平成10年10月8日、原告名義の普通預金口座とマルチマネー口座が開設され、同日、シティバンク赤坂支店に開設されていた乙太郎名義のマルチマネー口座(円建て)から1300万円が出金され、これが、同日、シティバンク池袋支店の原告名義のマルチマネー口座(円建て)にされた。同日、同口座(円建て)に入金されていた612万7500円(5万米ドル)が同口座(外貨建て)に移し替えられた。同月9日、同口座(外貨建て)に入金されていた4万9999米ドル(604万9879円)が同口座(円建て)に移し替えられ、同日、同口座(円建て)に入金されていた596万7500円(5万米ドル)及び694万8400円(5万8000米ドル)が同口座(外貨建て)にそれぞれ移し替えられた。平成11年1月18日、同口座(外貨建て)に入金されていた3万700○米ドルが北京市内にある中国銀行の支店(支店名は北京市宣武区支行)の原告名義の口座に送金された。同月27日、シティバンク池袋支店の原告名義のマルチマネー口座(外貨建て)に入金されていた3万七○○○米ドルが中国銀行の前記北京市内の支店の原告名義の口座に送金された。同月28日、シティバンク池袋支店の原告名義のマルチマネー口座(外貨建て)に入金されていた3万4044・58米ドルが中国銀行の前記北京市内の支店の原告名義の口座に送金された。
イ シティバンク赤坂支店の乙太郎名義の普通預金口座には、平成10年6月29日から同年9月3日までの間に、合計2932万1062円が入金されており、同日、その全額が出金されている。シティバンク赤坂支店の乙太郎名義のマルチマネー口座(外貨建て)には、平成11年1月21日現在で8万6210・46米ドルが入金されていたが、同月27日、同口座(外貨建て)に入金されていた3万7000米ドルが原告名義の海外の預金口座に送金され、同月28日、シティバンク赤坂支店の乙太郎名義のマルチマネー口座(外貨建て)に入金されていた3万7000米ドルが原告名義の海外の預金口座に送金された。同月29日、シティバンク赤坂支店の乙太郎名義のマルチマネー口座(外貨建て)に入金されていた1万2220・07米ドルが原告名義の海外の預金口座に送金された。
ウ 郵便局には、平成7年9月22日、原告名義で、24万円の定額郵便貯金、3万円の定期郵便貯金、266万円の定期郵便貯金及び14万円の定期郵便貯金が預け入れられ、平成10年7月27日、その全額である307万円が払い戻された。シティバンク赤坂支店の乙太郎名義の普通預金口座には、同日、100万円ずつ七回及び73万9000円、合計773万9000円が入金されている。
エ 口座番号《略》の銀行預金の口座には、平成9年5月9日から同年12月18日までに合計約451万円が入金されたが、この口座は、平成11年3月11日に10万4000円が払い戻された後は、平成14年4月12日から同年5月13日までの間に8万円及び28万円の各入金、同額の各出金、並びに利息の支払を除いては、出入金がされていない。
(3)金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律が平成15年1月6日に施行される以前の平成2年10月から、金融機関等における口座の開設者については、同法3条1項に規定する本人確認が行われていたことは、当裁判所に顕著な事実であるから、シティバンク池袋支店の原告名義の普通預金口座及びマルチマネー口座並びに郵便局に平成7年9月22日に開設された原告名義の口座の開設には、原告が関与していた可能性が高いと認められる。また、シティバンク池袋支店の原告名義のマルチマネー口座(外貨建て)に入金されていた金員が平成11年1月18日、同月27日及び同月28日の三回にわたり北京市内にある中国銀行の支店の原告名義の口座に送金されたこと並びにシティバンク赤坂支店の乙太郎名義のマルチマネー口座(外貨建て)に入金されていた金員が同月27日、同月28日及び同月29日の三回にわたり原告名義の海外の預金口座に送金されたことについては、いずれも原告が関与していた可能性もあり得るものと考えられる。
しかし、原告が、シティバンク池袋支店の原告名義の普通預金口座及びマルチマネー口座が実質的にも原告の口座であることを否定していること、シティバンク池袋支店の原告名義のマルチマネー口座(円建て一に平成10年10月8日に入金された1300万円は、シティバンク赤坂支店の乙太郎名義のマルチマネー口座(円建て)から出金されたものであること、シティバンク池袋支店の原告名義のマルチマネー口座(外貨建て)から平成11年1月に三回にわたり送金された際の送金先である原告名義の口座は北京市内にある中国銀行の支店に開設されており、乙太郎の実家は北京市内にあることからすれば、シティバンク池袋支店の原告名義の口座が実質的には乙太郎の口座である可能性も十分に考えられるところである。
そうすると、前述した(1)シティバンク池袋支店の原告名義の普通預金口座及びマルチマネー口座並びに郵便局に平成7年9月22日に開設された原告名義の口座の開設に原告が関与したこと、(2)シティバンク池袋支店の原告名義のマルチマネー口座(外貨建て)に入金されていた金員が平成11年1月に三回にわたり北京市内にある中国銀行の支店の原告名義の口座に送金されたこと及び(3)シティバンク赤坂支店の乙太郎名義のマルチマネー口座(外貨建て)に入金されていた金員が同月に三回にわたり原告名義の海外の預金口座に送金されたことについて原告が関与していた可能性があり得ることだけでは、シティバンク池袋支店の原告名義の普通預金口座及びマルチマネー口座が実質的にも原告の口座であることを認めるには足りないというべきである。
また、原告が、郵便局に平成7年9月22日に開設された原告名義の口座が実質的にも原告の口座であることを否定していること、郵便局に平成7年9月22日に開設された原告名義の口座に預け入れられていた307万円は平成10年7月27日にすべて払い戻され、他方、シティバンク赤坂支店の乙太郎名義の普通預金口座に、同日、合計773万9000円が入金されていること、原告が本邦に上陸した直後である平成6年には乙太郎と知り合っていることも勘案すれば、郵便局に平成7年9月22日に開設された原告名義の口座が実質的には乙太郎の口座である可能性も考えられる。そうすると、前記(1)ないし(3)だけでは、郵便局に平成7年9月22日に開設された原告名義の口座が実質的にも原告の口座であることを認めるには足りないというべきである。
以上によれば、その余の点について判断するまでもなく、郵便局に平成7年9月22日に開設された原告名義の口座に同日から平成10年7月27日まで預け入れられていた約300万円の貯金が原告の正業による収入とは考え難いということはできない。
また、乙太郎が本邦に在留中の活動状況の詳細が明らかにされていない本件においては、その金額の大きさのみから、シティバンク赤坂支店の乙太郎名義の口座に平成10年6月29日から同年9月3日までに入金された約2900万円が正業により得られたものではないとか、原告がその取得に関与していたとかいう事実を認めるには足りず、他にこれを認めるに足りる証拠はないから、結局のところ、原告がその取得に不正に関与していたことを認めることはできない。
(4)口座番号《略》の銀行預金の口座が、仮に、被告らが主張するように、みずほ銀行新宿西口駅前支店の原告名義の口座であったとすれば、原告は、その口座の開設に関与しているものということができる。
しかし、原告が、口座番号《略》の銀行預金の口座が実質的にも原告の口座であることを否定していること及び前記(3)で認定、説示したことに照らせば、口座番号《略》の銀行預金の口座が実質的には乙太郎の口座である可能性も考えられないではないのであって、原告が口座番号《略》の銀行預金の口座の開設に関与したといえることだけでは、同口座が実質的にも原告の口座であることを認めるには足りないというべきである。また、口座番号《略》の銀行預金の口座において平成14年4月から同年5月までの間に合計28万円の入出金があったことだけでは、その期間には乙太郎も在日していたのであるから、同口座が実質的にも原告の口座であることを認めるには足りないというべきである。
したがって、その余の点について判断するまでもなく、同口座に平成9年5月9日から同年12月18日まで入金されていた合計約451万円が原告が正業により得たものとは考え難いということはできない。
(5)以上によれば、被告らの前記(1)の主張は採用することができない。
(二)原告の横領等の疑いについて
(1)ア 被告らは、丙山社が、原告が売上金の一部を着服したことを理由に、原告を解雇し、また、丁川社は、原告が会社に無断でテレホンカードを仕入れて販売しその利益を自分のものにしたり、虚偽の売上げを報告して売上金の一部を横領したりするなどして、会社に損害を与えたことを理由に、原告を解雇している旨主張する。
イ しかし、原告は、その陳述書(甲11、30)及び本人尋問において、丙山社及び丁川社を退職した理由について、被告らの前記主張と全く異なる事実経過を陳述又は供述している。そして、前記認定事実によれば、両社からの退職の経緯が円満なものではなく、殊に、丁川社の乙原社長とは、感情的対立を残して退職していることが認められる。そうすると、両社において、原告への誤解やあるいは中傷が生ずることもあり得るところである。
以上によれば、十分な裏付けを伴わない乙第31ないし第36号証だけでは、丙山社において原告が売上金の一部を着服したこと及び丁川社が被告の主張に係る理由により原告を解雇したことを認めるには足りないというべきであり、他にこれらを認めるに足りる証拠はない。
ウ したがって、被告らの前記アの主張を在留特別許可の許否の判断においてしんしゃくすることはできない。
(2)ア 被告らは、原告は、足にけがをして平成14年8月23日から同年9月一○日まで休業したことを理由に損害保険会社から損害保険金として20万4397円の支払を受けているが、休業期間中である同年8月23日、同月26日、同月28日、同月29日及び同月30日にそれぞれ出勤しており、5日分の損害保険金の支払を不正に受けた旨主張する。
イ《証拠略》によると、原告が担当していた顧客に対する請求予定の書面がファックスにより顧客あてに送信されたのは、平成14年8月23日15時18分、同月26日10時○三分、同月28日11時36分、同日16時○六分、同日16時16分、同日16時29分、同日16時29分、同月29日17時○六分、同月30日12時57分、同日18時15分、同日18時21分であることが認められる。また、原告本人は、平成16年5月10日の尋問期日において、平成14年8月23日15時18分に送信された書面の日付「14」「八」「23」及び同月26日10時○三分に送信された書面の日付「14」「八」「26」は、いずれも原告が記載し、その余は、一部又は全部を原告が作成した旨供述している。
しかしながら、同供述は、同尋問期日において、被告らが突然、後に提出する予定であるとして担当量の未整理の書証写しを原告本人に提示し、かつ、その提示の仕方にも相当の混乱があった中で得られた供述である上、当日は、原告が発熱し、体調の悪い中で、服薬して尋問を実施したことは、当裁判所に顕著な事実である。そうすると、字体の異同といった細やかな事項につき正確な供述が得られたかは、はなはだ疑わしいといわざるを得ない。また、事柄の性質上、原告が不在であっても、原告担当の顧客関係の書面について、他の従業員が記入、処理することも、十分考えられることである。これらの事実関係に《証拠略》を加えて総合考慮すると、原告は、前記認定事実のとおり、自分が担当していた顧客に対する請求予定の書面をファックスにより顧客あてに送信するなどのために短時間だけ出勤したことがあり、同月28日以降は、会社では出勤扱いになっていなかったものの、相当時間出勤したはずであったと認めることができるが、それ以上に、被告ら主張の日に正規の勤務をしていたとまで認めることはできない。
ウ そうすると、原告は、損害保険金の支払を一部不正に受けた可能性があるが、原告のけがに対する治療の具体的内容、原告の通院の状況、原告の勤務先における給与の支払状況等が十分明らかにされていない本件においては、上記程度の損害保険金の不正受給の疑いをもって、在留特別許可を付与すべきではない事情としてしんしゃくすべきであるということはできない。
エ よって、被告らの前記アの主張は採用することができない。
4 小括
以上によれば、原告に在留特別許可を付与しなかった本件裁決は、違法というべきである。
第五 争点2(本件退令処分の適法性)について
法務大臣から権限の委任を受けた被告東京入管局長は、入管法49条1項による異議の申出を受理したときには、異議の申出が理由があるかどうかを裁決して、その結果を被告主任審査官に通知しなければならず(同条3項)、被告主任審査官が、被告東京入管局長から異議の申出に理由がないと裁決した旨の通知を受けたときには、速やかに当該容疑者に対し、その旨を知らせるとともに、入管法51条の規定する退去強制令書を発付しなければならない(入管法49条5項)。
そうすると、本件裁決が違法である以上、これに従ってされた本件退令処分も違法であるといわざるを得ない。
第六 結論
以上のとおり、原告の請求は、いずれも理由があるからこれを認容し、訴訟費用の負担につき、行政事件訴訟法7条、民事訴訟法61条、65条1項本文を適用して、主文のとおり判決する。
裁判長裁判官 菅野博之
裁判官 鈴木正紀
裁判官 馬場俊宏
松村総合法務事務所
ビザ総合サポートセンター
DNA ローカス大阪オフィス
〒540-0012
大阪市中央区谷町2 丁目5-4
エフベースラドルフ1102
TEL:06-6949-8551
FAX:06-6949-8552