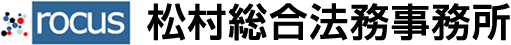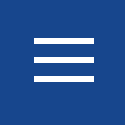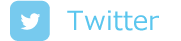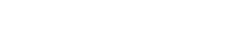判例集2019.02.05
在留資格変更不許可処分取消請求事件
判例集2019.02.05
東京地方裁判所判決平成11年10月15日 判決
【事案の概要】原告は 韓国国籍を有する外国人女性である。日本人男性と婚姻関係にある原告が,入管法2条の2及び「短期滞在」のビザをもって我が国に在留していた。その後,法20条に基づき,被告東京入管局長に対し,法2条の2及び「日本人の配偶者等」へのビザの変更許可申請をしたところ,被告が,不許可とした。原告は,これを不服として,処分の取消しを求めた。
【判旨】原告は,「日本人の配偶者等」のビザに該当するものではないとはいえないが,処分において,被告の裁量権の逸脱又はその濫用があるということはできない。したがって,原告についてビザの変更を適当と認めるに足りる相当な理由がないとの被告の判断に違法はない(不法入国、過去の偽装結婚歴や、子供が韓国に居住し、配偶者が収監されていることから資格変更を認めるべき相当の理由がないという入管局長の判断に違法はなく、短期滞在からの資格変更に必要な「やむを得ない特別の事情」の有無は判断するまでもない)。
主 文
一 原告の請求を棄却する。
二 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第一 請求
被告が、原告に対し、平成9年2月4日付けでしたビザの変更を許可しない旨の処分を取り消す。
第二 事案の概要
本件は、大韓民国(以下「韓国」という。)国籍を有する外国人で、日本人男性と婚姻関係にある原告が、出入国管理及び難民認定法(平成元年法律第79号による改正後のもの。以下、右改正前の出入国管理及び難民認定法を「旧法」といい、右改正後の同法を「法」という。)2条の二及び別表第一の三所定の「短期滞在」のビザをもって我が国に在留していたが、法20条に基づき、被告に対し、法2条の二及び別表第二所定の「日本人の配偶者等」へのビザの変更許可申請をしたところ、被告が、平成9年2月4日付けでこれを不許可としたため、原告が、これを不服として、右処分の取消しを求めた事案である。
一 前提となる事実(以下の事実のうち、証拠を掲記したもの以外は、当事者間に争いがない事実である。)
1 原告の国籍等
原告は、昭和○年(19××年)○月○日、韓国において出生した韓国国籍を有する外国人女性である。
2 原告の韓国における婚姻状況等
原告は、昭和55年3月○日、韓国において、Aと婚姻し、昭和63年3月○日、離婚した(乙59号証の三)。
3 原告がBと婚姻する以前の原告の出入国状況等
(一)第一回目の入国
原告は、昭和63年12月13日、東京入国管理局成田支局入国審査官から、旧法4条1項4号所定のビザ(以下、「ビザ4-1-4」という。)、在留期間30日とする上陸許可を受けて、本邦に上陸した。
原告は、平成元年1月10日、東京入国管理局(以下「東京入管」という。)において、在留期間更新許可申請を行い、同日、在留期間90日とする更新許可を受けた。
原告は、平成元年5月22日、東京入管において、右ビザから、旧法4条1項16号及び平成2年法務省令15号による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下、改正前のものを「旧規則」といい、改正後のものを「規則」という。)2条3号所定のビザ(以下、「ビザ4-1-16-3」という。)への在留資格変更許可申請を行い、同日、ビザ4-1-16-3、在留期間6月とするビザの変更許可を受けた。
原告は、平成元年10月7日、東京入管において、右ビザ4-1-16-3での在留期間更新許可申請を行い、同日、在留期間を3月とする更新許可を受けた。
原告は、平成元年○月○日、鎌ヶ谷市長に対し、日本人C(昭和○年○月○日生。)との婚姻届を提出し、同月16日、東京入管において、ビザ4-116-3から旧法4条1項16号及び旧規則2条1号所定のビザ(以下、「ビザ4-1-16-1」という。)への在留資格変更許可申請を行い、同日、ビザ4-1-16-1、在留期間6月とするビザの変更許可を受けた。
原告は、平成元年12月18日、東京入管において、再入国許可期限を平成2年6月16日とする再入国許可を受けて、同月31日、新東京国際空港から出国した。原告は、平成2年1月10日、右再入国許可により新東京国際空港から入国した。
原告は、平成2年○月○日、鎌ヶ谷市長に対し、Cとの協議離婚届を提出した。その後、原告は、同年○月○日、鎌ヶ谷市長に対し、再度、Cとの婚姻届を提出した。
原告は、平成2年5月29日、東京入管において、在留期間更新許可申請を行い、同日、在留期間6月とする更新許可を受けた。
原告は、平成2年12月14日、東京入管において、在留期間更新許可申請を行い、また、同月○日、Cと再度離婚した。被告は、平成3年3月25日、右申請を不許可とした。
原告は、平成3年8月5日、東京入管において、ビザ「短期滞在」への在留資格変更許可申請を行い、同日、ビザ「短期滞在」、在留期間90日(同年3月16日までの分)とするビザの変更許可を受けた。さらに、原告は、同日、同ビザで、二回分の在留期間更新許可申請を行い、同日、それぞれ在留期間を90日とする更新許可を受けた。これにより、原告の最終の在留期限は平成3年9月12日となった。
(二)第二回目の入国
原告は、平成3年10月18日、新東京国際空港から新規入国(ビザ「短期滞在」、在留期間15日)し、同年11月3日、在留期間更新許可(ビザ「短期滞在」、在留期間15日)を受け、同日、新東京国際空港から出国した。
(三)第三回目の入国
原告は、平成3年11月5日、新東京国際空港から新規入国(ビザ「短期滞在」、在留期間15日)し、同月20日、新東京国際空港から出国した。
(四)第四回目の入国
原告は、平成3年11月28日、新東京国際空港から新規入国(ビザ「短期滞在」、在留期間15日)し、同年12月13日、新東京国際空港から出国した。
(五)第五回目の入国
原告は、平成3年12月16日、新東京国際空港から新規入国(ビザ「短期滞在」、在留期間15日)し、同月31日、新東京国際空港から出国した。
(六)第六回目の入国
原告は、平成4年1月13日、新東京国際空港から新規入国(ビザ「短期滞在」、在留期間15日)し、同月28日、新東京国際空港から出国した。
(七)第七回目の入国
原告は、平成4年2月12日、新東京国際空港から新規入国(ビザ「短期滞在」、在留期間15日)した。
(八)第八回目の入国
原告は、平成7年7月18日、新東京国際空港から新規入国(ビザ「短期滞在」、在留期間15日)し、同年8月2日、新東京国際空港から出国した。
(九)第九回目の入国
原告は、平成7年8月22日、新東京国際空港から新規入国(ビザ「短期滞在」、在留期間15日)し、同年9月6日、在留期間更新許可申請をし、同日、更新許可を受け(ビザ「短期滞在」、在留期間15日)、その後、同月21日、新東京国際空港から出国した。
(十)第10回目の入国
原告は、平成7年10月3日、新東京国際空港から新規入国(ビザ「短期滞在」、在留期間15日)し、同月18日、新東京国際空港から出国した。
(十一)第11回目の入国1
原告は、平成7年10月23日、新東京国際空港から新規入国(ビザ「短期滞在」、在留期間90日)し、同年11月13日、居住地を東京都新宿区αとする外国人登録をし、さらに、平成8年1月23日、在留期間更新許可申請をし、同日、更新許可を受け(ビザ「短期滞在」、在留期間15日)、同日、新東京国際空港から出国した。
(十二)第12回目の入国
原告は、平成8年2月3日、新東京国際空港から新規入国(ビザ「短期滞在」、在留期間15日)し、同月18日、新東京国際空港から出国した。
(十三)第13回目の入国
原告は、平成8年2月21日、新東京国際空港から新規入国(ビザ「短期滞在」、在留期間15日)し、同年3月7日、新東京国際空港から出国した。
(十四)第14回目の入国
原告は、平成8年3月10日、新東京国際空港から新規入国(ビザ「短期滞在」、在留期間15日)し、同月24日、新東京国際空港から出国した。
4 原告とBの婚姻と原告のその後の出入国状況等
(一)原告は、平成8年3月26日、ビザ「短期滞在」、在留期間15日として新東京国際空港から日本に入国した。その後、原告とBは、同年4月10日、世田谷区長に対し、婚姻の届出をした。原告は、同日、新東京国際空港から出国した。なお、Bは、同日まで別の女性と婚姻関係にあったものであるが、同日付けで、右女性との協議離婚届を届け出ている。
(二)原告は、平成8年4月18日、ビザ「短期滞在」、在留期間15日として新東京国際空港から入国し、同年5月3日、新東京国際空港から出国した。
(三)原告は、韓国においても、Bとの婚姻手続を行った(その時期には争いがあり、原告は平成8年5月3日以降であると主張し、被告は、同年4月12日であると主張する。)。
(四)原告は、平成8年5月15日、ビザ「短期滞在」、在留期間90日として新東京国際空港から入国した。入国の際、原告は、外国人入国記録の日本滞在先欄に「東京都新宿区α」、日本滞在予定期間欄に「90日」と記載して上陸許可を申請し、ビザ「短期滞在」、在留期間90日とする上陸許可を受けて、本邦に上陸した。なお、渡航目的欄には「こんやく」と記載されている(乙四)が、原告が記載したか否かについては争いがある。
(五)Bは、平成8年5月17日、東京都新宿区βB方居宅において、覚せい剤取締法違反の容疑で現行犯逮捕され、同罪名で同年6月5日、起訴され、その後、同月28日には、銃砲刀剣類所持等取締法違反で追起訴された。Bは、同年8月9日、東京地方裁判所において、覚せい剤取締法違反及び銃砲刀剣類所持等取締法違反により懲役4年6月及び罰金100万円の判決の宣告を受け、同判決は、同月24日に確定した。現在Bは横浜刑務所に服役中である。
(六)Bは、平成8年4月30日、東京都世田谷区γから府中市δ地へ住民票を異動していたが、その後、Bが勾留中の同年6月13日に、府中市δから東京都新宿区αへ住民票が異動された。そして、原告は、同月14日、新宿区長に対し、居住地を「東京都新宿区α」、世帯主の氏名を「B」、勤務所又は事務所の名称を「なし」と記載して外国人登録申請を行い、同年7月11日に右外国人登録に係る外国人登録証明書が交付された。
5 本件処分に至る経緯
原告は、ビザ「短期滞在」で日本に在留していたところ、平成8年8月1日、東京入管において、在留資格変更許可申請書の「希望するビザ」欄に「日本人配偶者」、「変更の理由」欄に「同居」、「在日身元保証人又は連絡先」欄の「氏名」、「住所」、「職業」欄にそれぞれ「B、新宿区α、私設秘書、営業」と記載して、Bが身元保証した日付のない身元保証書、Bの住民票、同年6月10日付けで世田谷区長が認証したBの戸籍謄本、同年4月13日付けの原告の韓国の戸籍謄本、Bの平成7年分の給与所得の源泉徴収票、Bの在職証明書、回答を記載した質問書を提出してビザの変更許可申請をした(以下「本件申請」という。)。
被告は、平成9年2月4日、原告の右申請に対し、ビザの変更を適当と認めるに足りる相当の理由がないとして在留資格変更許可申請を不許可とする処分(以下「本件処分」という。)を行い、同月5日、同通知書を原告あてに送付した。
二 争点及びこれに対する当事者の主張
本件の争点は、原告が「日本人の配偶者等」というビザに該当するかどうか(争点1)、短期滞在のビザをもって在留する者がビザの変更の申請をした場合には、「やむを得ない特別の事情」に基づくものでなければビザの変更を許可しないものとされている(法20条3項ただし書)ところ、本件申請に「やむを得ない特別の事情」があるかどうか(争点2)、本件処分に被告の裁量権の逸脱があるかどうか(争点3)であり、各争点に関する当事者の主張は、次のとおりである。
1 争点1(原告が「日本人の配偶者等」というビザに該当するかどうか)について
(被告の主張)
(一)ビザ該当性と活動の要件との関係について
法別表のビザは、それ自体が独立して存在するものではなく、その資格に基づく活動と一体となって要件として定立されているものである。
すなわち、法2条の二第2項で「ビザは、別表第一又は第二の上欄に掲げるとおりとし」と規定されているとともに、同項は、「別表第一の上欄のビザをもって在留する者」については、「当該ビザに応じそれぞれ本邦において同表の下欄に掲げる活動」をも要件とし、また、同様に、「別表第二の上欄のビザをもって在留する者」についても、「当該ビザに応じそれぞれ本邦において同表の下欄に掲げる身分若しくは地位を有する者としての活動」を行うことができる旨規定している。そして、別表第一の上欄のビザを付与されるためには、その行う活動が「当該ビザに応じそれぞれ本邦において同表の下欄に掲げる活動」に該当することが、また、別表第二の上欄のビザを付与されるためには、その者が「当該ビザに応じそれぞれ本邦において同表の下欄に掲げる身分若しくは地位を有する者としての活動」を行うことがそれぞれ必要である。
また、法は、我が国にとって有益な外国人はできるだけ円滑にこれを受け入れるが、他方、我が国にとって不都合なあるいは有害な外国人はこれを排除し、もって我が国の利益を守るという趣旨に基づき、本来、無限に近い広がりを有する人の社会生活上の活動をビザ及びそれに基づく活動という類型化により、我が国社会にとって有益な外国人と不都合あるいは有害な外国人とを振り分け、前者に限ってこれを受け入れようとするものである。その場合に判断の要点となるのは、ビザがいかなるものかという観点とともに、当該ビザに基づいて外国人が我が国で行おうとする活動、すなわち、「その外国人が我が国で何をしようとしているのか」ということが重要となることはいうまでもない。このような視点に立って、法は、右のような法整備をしているのであり、かような出入国管理は、我が国に限ったことではなく、国際的には一般的に行われているものである。
さらに、実務上も、空港等における入国審査官の入国審査を例にとると、単なる形式的な身分、地位等を有することのみを基準として入国の可否を判断するならば、当該外国人の入国の目的も入国後の活動内容も分からず、したがって、その必要性も判断できないことから、国家としての外国人の出入国管理の用をなさないということになる。その典型は、国際的な窃盗組織の一員が犯罪行為を目的として入国しようとする場合であり、その者がいかに一定の地位や身分を有していたとしても、国家としては、その行おうとする活動が我が国社会の秩序や利益を害するおそれがある以上、その入国を拒否する必要があることはいうまでもない。
右のような観点から、法2条の二第2項は、我が国に在留する外国人は、それぞれのビザが予定している一定の「活動」を行って我が国に在留するものであることを、法7条1項2号は、我が国に上陸しようとする外国人が上陸のための申請を行う場合、入国審査官が審査しなければならない上陸のための条件として「別表・・・に掲げる・・・活動のいずれかに該当」すべきことを規定しているのである。
(二)ビザ「日本人の配偶者等」が認められるための「活動」の要件
(1)以上の観点に立って、法2条の二及び法別表第二に基づくビザ「日本人の配偶者等」についてみれば、法律上の婚姻関係が存在することに加え、「日本人の配偶者としての活動」、すなわち、日本人の配偶者である外国人が、民法752条に基づき我が国においてその配偶者である日本人と同居し、互いに協力し、扶助しあって社会通念上の夫婦共同生活を営むという活動実態が必要であると解すべきである。
まず、法2条の二第2項において「日本人の配偶者」という資格についてのみ、その身分又は地位を有する者としての「活動」が不要であるとする規定の構造にはなっていないことは右に述べたとおりである。
また、法が「日本人の配偶者」というビザを認めたのは、日本人と婚姻した外国人が、その配偶者である日本人と我が国において社会通念上夫婦としての共同生活を営むために我が国に入国し在留することを可能にしようとするという行政目的から設けられたものである。このことは、法6条2項の委任を受けた規則6条及び別表第三が、「日本人の配偶者等」として入国・在留しようとする際には、上陸の審査のために提出すべき書類として、「当該日本人の住民票の写し」及び「本邦に居住する当該日本人の身元保証書」の提出を要求し、かつ、法20条2項の委任を受けた規則20条2項及び別表第三が、「日本人の配偶者等」への在留資格変更を申請する場合には、被告が変更を適当と認めるに足りる「相当の理由」があるか否かを審査するために、当該外国人に対し、「当該日本人との婚姻を証する文書及び住民票」、「当該外国人又はその配偶者の職業及び収入に関する証明書」及び「本邦に居住する当該日本人の身元保証書」の提出を要求していることからも明らかである。
そして、入国審査官も、上陸審査において、単に「日本人の配偶者」という身分のみで審査することはしておらず、右各書類に基づき、その者が我が国において行おうとする活動が「日本人の配偶者」の身分を有する者としての活動に該当するか否かについても審査しており、右に述べた解釈は、入国審査の実務にもかなった取扱いなのである。
特に、近年における我が国の経済事情、なかんずく高水準の円高や高賃金から、機会があれば我が国において就労活動に従事することを希望する外国人は極めて多数に上る。しかしながら、そうした外国人の入国を無原則・無制約に認めた場合には、我が国の労働市場のみならず、我が国社会の各方面に様々な問題を惹起するであろうことは容易に推測でき、法も、前述のとおり、外国人が法別表第一の下欄に掲げる活動以外の就労活動を行うことを認めていない。そして、「日本人の配偶者等」については、法別表第二の上欄に掲げるビザであって、法別表第一の上欄に掲げるビザをもって在留する者とは異なり、その活動につき特段の制限がなく、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うについて法19条2項に規定する許可を要しないことから、日本人の配偶者としての活動に加えて就労することも制限されない。この結果、昨今、本邦での就労活動を行うことを目的とする外国人が、このビザを隠れみのとして悪用する例が後を絶たない状況にある。
右状況下において、仮に、日本人との間に法律上の婚姻関係はあるが、社会通念上の夫婦共同生活を営むという実態を欠いている外国人に対してもビザ「日本人の配偶者等」を付与しなければならないとすると、我が国での就労活動を目的とする外国人がブローカーを介在させる等して日本人との婚姻を偽装し、あるいは、短期間のうちに夫婦生活を放棄したり、もはや婚姻を継続する意思はないのに離婚せず、形式的に法律上の婚姻関係を継続させたまま、専ら本邦での就労活動に従事するという事例が大量に発生することを容認することとなる。そして、本件婚姻のように、いわゆる偽装婚か否かは事柄の性質上外見的には判別が困難である。
このような事態は、前述のような、外国人の無制約な就労が日本人の労働市場を侵害する等の不都合をもたらすこととなり、在留外国人に対する公正な管理という重要な行政作用を阻害し、出入国管理秩序を根底から破壊するものであって、外国人の出入国管理行政に責任を有する被告にとって到底容認できない事態といわなければならない。さらには、かかる事態は、その配偶者たる日本人が偽装婚によっていわゆる「籍を貸す」といった行為を招来し、我が国の善良な婚姻秩序をびん乱することにもつながるものといわなければならないのである。
(2)これに対し、原告は、別表第二で定められている「永住者」、「日本人の配偶者等」、「定住者」等は、その活動内容に着目して付与されるビザではなく、一定の身分又は地位に基づいて付与されるビザであり、法も別表第一に掲げられたビザと、これら法別表第二に掲げられたビザと峻別していると主張する。
しかし、法は、別表を規定するに際して、別表第一とともに別表第二においてもそれぞれ下欄を定め、法2条の二第2項においても、前述のとおり、「別表第二の上欄の・・・引用する・・・同表下欄に掲げる身分若しくは地位を有する者としての活動を行うことができる」と規定し、各表の下欄で各ビザに伴う「活動」に着目しているのである。
なお、法が別表第一と同第二に分けて規定したのは、前述のとおり、別表第一については、上欄のビザが予定する活動に着目していることから、これを整理したものであり、別表第二においては上欄のビザの身分又は地位に着目して整理したものであり、規定の整理という法制上の問題にすぎない。そして、前に述べたとおり、別表第二のビザにおいても、「活動」が要件とされているのである。
そして、原告も別表第一について活動内容を判断対象とする点を認める以上、別表第二においても同様に、該当ビザに基づき、法2条の二第2項に規定するように「同表下欄に掲げる身分若しくは地位を有する者としての活動」を検討せざるを得ないはずである。
法2条の二第2項で「ビザは、別表第一又は別表第二の上欄に掲げるとおりとし」と規定されているのは、法が我が国にとって有益な外国人はできるだけ円滑にこれを受け入れるものの、前に述べたとおり、我が国にとって不都合なあるいは有害な外国人はこれを排除し、もって、我が国の利益を守るという趣旨に基づき、ビザは別表第一又は別表第二の上欄に掲げる場合にのみ許容し、別表第一又は別表第二の上欄に掲げられなければ他の事由をもっても在留は認められないという、いわば制限列挙であることを明らかにしたにすぎない。
そして、法7条における入国審査においても、前に述べたとおり、同条1項2号は、我が国に上陸しようとする外国人が上陸のための申請を行う場合、入国審査官が「申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものでな」いこと及び「別表第二の下欄に掲げる身分若しくは地位・・・を有する者としての活動のいずれかに該当」することを審査すべきである旨規定しており、現にそのとおり入国審査がなされているのである。
仮に、原告の右主張が正当であるならば、ビザである各別表の上欄のみを規定すれば足りるのであるし、また、あえて法2条の二第2項のような規定の仕方をする必要もないはずである。
(3)原告は、現在我が国で施行されている税法、社会福祉法等のあらゆる法制の中で、「配偶者」に法律上有効に婚姻している者以上の意味内容を付している法令は存在せず、また、所管官庁の解釈により、「配偶者」該当性を限定するような取扱いもしていないにもかかわらず、入管行政においてのみ、「配偶者」該当性を所管庁が判断できるような取扱いは、我が国法体系全体からみても、著しく不整合であると主張する。
しかし、ビザとしての「日本人の配偶者等」の要件としては、前に述べたとおり、「法律上有効な婚姻関係が存すること」とともに、「日本人の配偶者としての活動」が必要であり、前者の法律上の解釈には議論があるにしても、後者の要件が必要であることには変わりがない。
なお、「配偶者」の定義についても、社会保障法たる農林漁業団体職員共済組合法24条1項での遺族給付を受けるべき「配偶者」の解釈、国家公務員等共済組合法2条1項における同様の解釈のように、各法令の趣旨、目的等に従って解釈されるべきものである。
(4)原告は、仮に「日本人の配偶者等」のビザについて法律上有効な婚姻関係があるだけでなく、当該外国人が本邦において行おうとする活動が必要だとしても、その活動内容は必ずしも同居を要するものではないと主張する。
しかし、「日本人の配偶者としての活動」とは日本人の配偶者である外国人が、民法752条に基づき、我が国においてその配偶者である日本人と同居し、互いに協力し、扶助しあって社会通念上の夫婦共同生活を営むという活動実態をいうものである。
すなわち、法2条の二第2項では、その身分又は地位に基づく活動の内容は明記されていない。
そして、通常配偶者は、同居して夫婦の共同生活を維持し家庭生活を継続していくものであり、同居は配偶者という身分又は地位に基づく活動の基礎となるものである。このことは、民法752条においても、活動実態の基礎を夫婦の同居、相互の協力、扶助に求められているところである。したがって、法2条の二第2項及び別表第二の下欄が右のとおり日本人の配偶者という身分又は地位に基づく活動を具体的に規定しなかったのは、そうした活動の基礎として夫婦が同居して生活することを前提にし、また、全法令体系の中でそのよりどころとなる民法の右規定を当然に予定していたものということができるのである。
(三)原告の場合
(1)原告とBとの本件婚姻は、それが双方の真意に基づくものであるかは多大の疑問が残るところであるが、この点をおくとしても、少なくとも、原告は、本件申請時にBと同居することは不可能であったのである。したがって、「日本人の配偶者」としての「活動」の重要な要件の一つである「同居」が実現していない以上、夫婦共同生活の実現は不可能又は著しく困難であって、そもそも法2条の二第2項に該当しない。それにもかかわらず、本件申請は、ビザの変更を求めているものであって、不適法であり、そのように取り扱った本件処分は適法である。
(2)仮に、「日本人の配偶者」としての「活動」として認められるために「同居」が必要とされない場合があり、配偶者として認められるそれ以外の活動があれば、それで、足りると解するとしても、本件では、その程度の活動さえ存しないというべきである。
すなわち、「日本人の配偶者等」としての活動は、法がそれに基づきビザを付与するという効果の観点から、それにふさわしい程度の活動が必要である。そして、本件をみると、原告は、Bとの面会、差し入れ及び手紙のやりとり、Bの持ち物の保管、Bの知人からの連絡への対応等しかしていない。しかし、これらの行為は、原告に「日本人の配偶者等」のビザを与えなければできないような活動ではなく、原告自身が行わなければならない活動でもない。したがって、原告が主張するような活動の程度では、原告が主張するような「配偶者としての活動」にも足りないというべきである。
なお、原告は、Pビルの契約更新の手続をしたり、家賃や公共料金を支払ったりする活動も挙げている。しかし、Pビルは、Bとの婚姻以前から原告が自らのために賃借を継続してきたものであり、原告が現在我が国に残留するために使用している住居にほかならない。家賃や公共料金の支払いについても、自らが居住していることに伴う費用にすぎない。
また、原告は、「日本人の配偶者等」の活動として、Bが、原告の存在を支えにして受刑していることをあげている。しかし、原告がそうした精神的支えになることが精神的支援の域を超えて日本人の配偶者としての「活動」と直ちに結びつくものではないし、また、そのこと自体が「日本人の配偶者等」のビザを取得させてまで認めるべき活動ともいえない。
したがって、原告の主張を前提にしても、「日本人の配偶者等」というビザが認められるものではない。
(原告の主張)
(一)日本人の配偶者としての活動が「日本人の配偶者等」のビザ該当性の要件とはならないこと
法別表第二の「日本人の配偶者等」に該当するには、法律上有効な婚姻関係のみが存在すれば足り、被告が主張するような「日本人の配偶者としての活動」までをも要するものではない。
被告は、法別表第二に掲げられた「日本人の配偶者等」について、そのビザを付与されるためには、「『当該ビザに応じそれぞれ本邦において同表の下欄に掲げる身分若しくは地位を有する者としての活動』」がなければならないことの根拠として、「法別表のビザはそれ自体が独立して存在するものではなく、その資格に基づく活動と一体となって要件として定立されている」ということを挙げている。
しかし、法2条の二第2項は、単に「ビザは、別表第一又は別表第二の上欄に掲げるとおりとし」とするのみである。つまり、法別表第一、第二の上欄に該当する者については、直ちにビザ該当性が認められるのである。
もっとも、法別表第一記載のビザについては、本邦における活動内容に応じて付与されるものであるから、当該ビザ該当性を判断するに当たっては、その活動内容を判断せざるを得ない。つまり、法別表第一記載の各ビザは、本邦入国後の活動内容に着目して、その内容に応じて付与されるビザであって、これらでは、本邦での活動内容によりビザの種類及びこれを付与するか否かが決定される。
これに対し、法別表第二で定められている「永住者」、「日本人の配偶者等」、「定住者」等は、その活動内容に着目して付与されるビザではない。これらは、一定の身分又は地位に基づいて付与されるビザであり、だからこそ、法は法別表第一に掲げられたビザと、これら法別表第二に掲げられたビザとを峻別しているのである。
よって、法別表第二のビザについては、上欄に掲げられている身分又は地位さえあれば、直ちに当該ビザの該当性が認められるものである。そして、法は法別表第二の「日本人の配偶者等」につき、特に別途定義規定を置いているわけではないから、法律上の婚姻関係さえあれば、「日本人の配偶者等」のビザ該当性も認められると解すべきである。
この点につき、現在我が国で施行されている税法、社会福祉法等のあらゆる法制の中で、「配偶者」に法律上有効に婚姻している者以上の意味内容を付している法令は存在せず、所管官庁の解釈により、「配偶者」該当性を限定するような取扱いもしていないのであって、入管行政においてのみ、「配偶者」該当性を所管庁が判断できるような取扱いは、我が国法体系全体からみても、著しく不整合であるといわざるを得ない。
以上からすると、法別表第二の「日本人の配偶者等」に該当するには、法律上有効な婚姻関係のみが存在すれば足り、法はそれ以上の要件を付加していないと解すべきである。
そして、本件では、原告はBの法律上有効な配偶者であり、この点は当事者間に争いはないのであって、原告は「日本人の配偶者等」のビザに該当するというべきである。
(二)日本人の配偶者としての活動の内容について
仮に、被告が主張するように、「日本人の配偶者等」のビザ該当性について、法律上有効な婚姻関係があるだけではなく、当該外国人が本邦において行おうとする活動が、日本人の配偶者としての活動に該当することが必要だとしても、その活動内容としては、必ずしも同居を要するものではない。
すなわち、法が法別表第一の下欄に掲げるビザについて、当該下欄に我が国において行うことができる活動を個別具体的に規定しているのと異なり、法別表第二の「日本人の配偶者等」の下欄には、我が国において有する身分又は地位として、「日本人の配偶者」と規定するのみで、日本人の配偶者としての活動内容を個別的・具体的に定めておらず、その他その活動の内容及び範囲を具体的に認識できるような規定も存在しない。そこで、「日本人の配偶者としての活動」についても、社会通念に従って、その内容及び範囲を確定していくほかはないことになるが、単に同居の事実がないからといって、社会通念上、「日本人の配偶者等」としての活動に該当しないということはできない。例えば、夫が長期単身赴任しているような場合に、留守宅を守っている戸籍上の妻を「配偶者ではない」というのが、社会通念に反することは明らかである。
この点、被告は、規則20条2項及び規則別表第三が、「日本人の配偶者等」への在留資格変更を申請する場合に、「当該日本人との婚姻を証する文書及び住民票」、「当該外国人又はその配偶者の職業及び収入に関する証明書」、「本邦に居住する当該日本人の身元保証書」の提出を要求していることなどから、「日本人の配偶者としての活動」は、民法752条に基づき我が国においてその配偶者である日本人と同居し、互いに協力し、扶助しあって社会通念上の夫婦共同生活を営むという活動実態が必要であると主張する。しかし、これらの手続要件は、ビザの認定を適正に行うためのものであって、右の要件が定められていることをもって、「日本人の配偶者等」のビザが認められるためには、夫婦としての同居・協力・扶助の関係が現実に存在しなければならないものと限定的に解することは相当ではない。
以上から、仮に「日本人の配偶者等」のビザ該当性について、「日本人の配偶者等」としての活動が必要だとしても、必ずしも同居を必要とするものではなく、社会通念上、配偶者としての活動と認められるものがあればよい。
(三)これを本件についてみるに、以下に述べるとおり、原告は、日本人であるBと実際に婚姻生活を営む意思で婚姻をし、かつ、現在も日本人の配偶者としての活動を行っているので、原告は、日本人の配偶者等のビザに該当するといえる。
(1)原告は、昭和63年12月、日本語を学ぶため来日し、翌平成元年より、日本語学校に入学した。そして、原告は平成3年5月ころ、原告が電話ボックスに忘れたハンドバッグをBが拾ったことがきっかけで、Bと知り合い、食事をしたり、電話で連絡を取り合うようになった。
なお、原告はBと知り合う前に、Cと二度婚姻と離婚をしているが、本件処分から7年も遡ることであって、本件処分の違法性を判断するに当たっては全く関連性のないことである。
原告はBと知り合った後、同人と交際をするようになった。原告は日本と韓国を行き来しながら、日本滞在中はBと一緒に新宿御苑に行ったり、Bから日本の文化を教わったり、Bの紹介で着物の教室に通ったりして、交際を深めていった。しかしながら、当時Bが前妻と正式に離婚していなかったこと及び原告とBの年齢が離れていることを理由に、原告の母親が結婚に反対したことから、原告とBは婚姻せず、次第に両者の仲は疎遠になった。
(2)原告はBとの交際が中断した後、平成5年ころ、Dと知り合い、交際をするに至った。そして、同人と結婚をするつもりで平成7年1月、原告が現在居住しているPビルのアパートを借りたが、Dは右Pビルから失踪し、同年4月自殺をしてしまった。そこで、原告はBに連絡をし、相談をするうち、再度同人との交際が始まった。
(3)原告はBとの交際が復活してから、短期滞在のビザの許可を受けつつ、日本と韓国を何度も行き来し、原告が日本に滞在している間は、右PビルにおいてBと生活をした。具体的には、Bは右αから仕事に出かけ、仕事が終わった後の夜には同ビルに戻り夕食を一緒に食べ、同じベッドで眠りにつき、セックスもそこでするという生活だった。原告は、部屋の掃除、夕食の準備や後かたづけ、入浴の準備等、一般家庭における日常家事を担当していた。当然のことながら、原告及びBの着替えもすべて右αに置いてあった。そして、ときには近所のトンカツ屋に外食に行ったり、休日にはドライブをしたり、新宿御苑、上野公園、明治神宮などに遊びに行ったりもした。
また、原告はBのことを「パパ」等と、Bは原告のことを「N」とお互いに呼び合い、Pビルの家賃を含めた生活費や原告の渡航費はBが負担するなど、籍を入れていないことを除けば、正に「夫婦」そのものの日常生活を行っていた。
なお、Bは、平成8年4月、住民票をEの住所地に異動させている。これは、BとEとの金銭的なトラブルから、場合によってはBがE宅に居住することを予定していたためであるが、実際にBが右住所地に居住した事実はない。
そして、平成8年4月10日、Bが前妻と正式に離婚できたことから、同日、原告とBは婚姻届を提出した。
(4)婚姻届を提出した日に、原告はいったん韓国に帰国し、平成8年4月18日来日して、再び同年5月3日には帰国し、その後同月15日に短期滞在のビザ(在留期間90日間)で来日した。この点、原告が韓国で日本人の配偶者としてのビザ証明書を取得せず、短期滞在のビザで来日したのは、短期滞在のビザで来日した後、日本においてビザの変更を行うことができるとの在韓日本大使館職員のアドバイスを受けたからである。そして、原告の入国時にも、成田空港で来日目的を結婚したBと生活をすることである旨入国審査官に説明したところ、同審査官において入国記録の渡航目的欄に「こんやく」と記載した上で、短期滞在の許可のスタンプをパスポートに押したのである。
(5)しかし、平成8年5月17日、Bは逮捕され、同年8月9日に懲役4年6月及び罰金100万円の判決を受け、同人は横浜刑務所で服役することとなった。原告は、Bの妻として、Bの逮捕後現在に至るまで、拘置所及び刑務所に頻繁に面会のために訪問したり、新聞等を差し入れたりするとともに、Bの罰金を立て替えた者に対し、月3万円ないし5万円ずつを返済している。そして、原告は、Bの妻として、同人の衣服、靴、パスポートや書類等、Bの所持品を前記のαにおいて現在も保管し、同人が出所して家に戻ってくるのを待ち続けているのである。
他方で、Bも原告に対し、頻繁に手紙を書いている。手紙の中で、Bは、自らの所持品を原告に送付し、その管理、処分を依頼したり、原告及びBの住居の契約の心配をしたり、差し入れの希望をしたり、Bが被害を受けた交通事故の示談手続を依頼するなど、Bが刑務所に在監していることから行い得ないことを妻である原告に依頼している。これらは、仮に原告が韓国に帰国していたとしたら到底なし得ない日本人の配偶者としての活動である。また、原告が日本にいて、面会に度々訪れたことが、Bが受刑生活を送る上で最大の精神的支えになっていることを見て取ることができるし、Bは、出所後には原告とのコミュニケーションをより円滑に行うべく、韓国語の勉強に励んでいるのである。さらに、Bが仮釈放されるためには、身元保証人の存在が不可欠であるが、Bは他の家族とは疎遠になっており、妻である原告が本邦に滞在して、身元保証人となることが必要なのである。
(6)このような受刑中のBを、物心共に支えている原告の活動が、社会通念上、日本人の配偶者としての活動に該当することは明白である。
(四)以上から、原告に「日本人の配偶者等」のビザが認められることは明らかである。
2 争点2(原告の在留資格変更申請にやむを得ない特別の事情があるかどうか)について
(被告の主張)
(一)本件のように、ビザを「短期滞在」から変更する場合には、法は、ビザの変更について、「短期滞在のビザをもって在留する者の申請については、やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しないものとする。」と規定している(法20条3項ただし書)。
この「やむを得ない特別の事情」とは、事柄の性質上、「短期滞在」のビザを受けて入国した後あるいは「短期滞在」のビザで在留中に、新たにビザの変更を必要とするような事情が発生し、かつ、当該申請者がいったん出国してしまうと、その変更許可申請に係る在留目的で再度入国することが極めて困難である場合や人道上の必要性等がある場合等の特別の事情をいうと解され、このような特別の事情が認められない場合には、やはり、ビザの変更は許可されないのである。
(二)「短期滞在」のビザを有する者からの変更許可申請について、右のような特別の事情が要件とされるのは以下の理由によるものである。
すなわち、「短期滞在」のビザは、「本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動」(法別表第一の三の表)を行おうとする者に付与されるものであり、これらの者は、目的達成に要する期間が短期であり、その後速やかに本邦から出国することが予定されていることからこそ、一般的には、査証の発給に当たっても、在外公館限りで比較的容易に査証が発給され、簡便な入国手続により入国を認めているのである。
他方、外国人が長期在留を希望し、あるいは、職業活動に従事しようとするような場合には、その者の入国が国内の経済・社会等に及ぼす影響が大きくなるので、入国・上陸しようとする者がいかなる外国人であり、その者の入国や上陸後の活動により我が国の経済・社会等に好ましくない影響を与えるおそれがないかどうかを事前に十分に調査し把握する必要が高く、加えて、その判断を行うための情報や資料はその外国人の本国や居住地でなければ収集困難であることを考慮して、入国・上陸の前にあらかじめ外国人の本国等にある在外公館において査証を申請させ、その外国人に関する情報や資料を当該在外公館において収集した上、その者の入国・在留について問題がないかどうかを慎重に判断することとしている。そして、このことは、本邦に入国しようとする外国人の上陸の審査においても同様なのであって、長期滞在や就職を目的とする場合には、特に慎重な審査を行っているのである。
(三)このような趣旨から、法は、短期滞在のため入国した者のビザの変更について、法務大臣に対して「やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しないものとする」という制約を課しているのである。そして、「短期滞在」のビザで在留する者がその目的すなわち在留活動の変更(ビザの変更)を希望する場合には、当初から長期在留等を目的として入国しようとする者との公平を図り、また出入国管理上の秩序を維持するなどの見地から、これらの者に対する入国審査と同じ審査を経させる必要があることになる。
結局、「短期滞在」からの在留資格変更許可は、「やむを得ない特別の事情」がある場合に限ることと規定されているのは、このような「短期滞在」というビザの性質から来る当然の制約ということができるのである。仮にこのような制限がなければ、長期在留や就職、事業の経営等を真の目的とする外国人の多くは、まずは「短期滞在」のビザで入国し、なし崩し的に既成事実を積み上げ、その後にビザの変更を申請して許可を受けようとする事態を生ずるが、これが容認されれば、外国人の公正な入国管理に重大な支障を及ぼすこととなるのは必至である。
(四)原告は、申請書の記載欄・提出資料上「やむを得ない特別の事情」を記載すべきことは求められていないこと、在留資格変更許可申請全体に対する不許可の率は低いものであることから、「やむを得ない特別の事情」の有無は、実務上はほとんど審査されておらず、本件のみ「やむを得ない特別の事情」がないことを理由に本件処分を行うことは平等原則に違反すると主張する。
しかし、前述のように、「やむを得ない特別の事情」とは、「短期滞在」のビザを受けて入国した後、あるいは「短期滞在」のビザで在留中に、新たにビザの変更を必要とするような事情が発生し、かつ、当該申請者がいったん出国してしまうと、その変更許可申請に係る在留目的で再度入国することが極めて困難である場合や人道上の必要性等がある場合等の特別の事情をいうものである。そして、このような特別の事情の有無は、専ら申請人の主張に係る「変更の理由」について、そのような事情があるか否かに基づいて判断されるところ、申請書に「やむを得ない特別の事情」を記載する欄がなく、規則20条及び別表第三が提出書類として殊更に「やむを得ない特別の事情」を立証する資料を提出すべき旨定めていないからといって、被告が「やむを得ない特別の事情」の有無を考慮していないということはできない。
(五)なお、原告は、外国人が本邦在留中に婚姻し、同居生活のために本邦に引き続き在留を希望する場合や、当初から長期間本邦に滞在することを目的としていながら「短期滞在」のビザで入国し、その後「日本人の配偶者等」のビザへの在留資格変更申請を行う日系二世の場合と比較して、本件処分が平等原則に違反する旨主張するようである。しかし、これらはいずれも本件と比較する例としては失当である。
すなわち、原告は本邦入国以前から日本に長期間滞在することを予定していたものであると認められ、また、原告の本邦への出入国状況からも本来意図する在留目的に適合する査証を本国で取得した上で長期滞在が可能なビザに基づき入国することが可能であった者である。また、「やむを得ない特別の事情」の有無は、専ら申請人の主張に係る「変更の理由」について審査されるところ、本件申請では、変更の理由として「同居」とあるのみであり、この「同居」は、当面の間実現不可能であったものである。このような本件の特殊性からすれば、原告が主張するような日系二世との比較の対象とならないことは明らかであるし、そもそも平等原則に違反するものではないのである。
(六)本件における「やむを得ない特別の事情」の有無について
原告は、「やむを得ない特別の事情」を考慮するものとしても、種々の事情を挙げて、本件は当該要件に該当すると主張する。
しかし、原告は、本来であるならば、ビザ認定証明書の交付をあらかじめ受け、適切な査証を取得し「日本人の配偶者等」のビザをもって本邦に上陸することも十分可能であったものであり、入国後、新たに「日本人の配偶者等」へのビザの変更を必要とするような事情が発生したものでもない。また、原告が、横浜刑務所において同所職員の立会いの下に月一回認められるBとの面会を行いたいというのであれば、ビザ「短期滞在」での在留で足り、Bが出所して同居が可能となってからでも新規入国の手続をとれば十分足りるのであって、Bが受刑している間、我が国に滞在する必要はないのである。また、いったん韓国に帰国して日本人の配偶者として来日する場合、原告の主張するように入国までに手続に時間がかかるとしても、そのことからBとの面会が不可能となるものではなく、原告においてビザ「短期滞在」で入国すれば面会は可能である。
よって、原告に「やむを得ない特別の事情」は存在しない。
(原告の主張)
(一)被告の解釈の不当性
(1)被告は、法20条3項ただし書にいう「やむを得ない特別の事情」とは、「『短期滞在』のビザを受けて入国した後あるいは『短期滞在』のビザで在留中に、新たにビザの変更を必要とするような事情が発生し、かつ、当該申請者がいったん帰国してしまうと、その変更許可申請にかかる在留目的で再度入国することが極めて困難である場合や人道上の必要性がある場合等」をいうと主張する。
しかし、「やむを得ない特別の事情」が認められるためには、必ずしも、被告が主張するように、短期滞在での入国若しくは在留中に、新たにビザの変更を必要とするような事情が発生する必要はない。このことは、立法当時から予定されていたものである。
(2)また、右の要件は、実務においてはほとんど審査されておらず、形骸化若しくは極めて緩やかに解釈されて運用されているのであり、右主張を不許可の理由とすることは、著しく平等を失する。
すなわち、そもそも「短期滞在」からの資格変更について、法20条3項ただし書の制約を課している趣旨は、短期滞在においては、簡便な入国手続により入国を認めているところ、長期滞在や就職を目的とする場合には、慎重な審査を行っていることとの公平を図り、もって、適正な出入国管理を実現するなどの観点によるものとされる。しかし、短期滞在から他のビザへの変更申請手続においても、変更を希望するビザに該当するかどうかについて、最初からその資格で入国するのと同様の慎重な審査がなされている。もし、法の趣旨に忠実になるのであれば、「やむを得ない特別の事情」の存否のみを判断し、それが認められなければ、手間と時間のかかるビザ該当性の審査など経ずに、直ちに不許可の判断ができるはずであるのに、そのような取扱いはしていない。
さらに、短期滞在からの変更許可申請書と、その他のビザからの変更許可申請書とは区別がされていないことも、形骸化の現れの一つである。すなわち、この変更申請書の書式には、「変更の理由」欄はあるものの、わずか一行半のスペースがあるのみで、その他、特に「やむを得ない特別の事情」を記載する欄は存在しない。原告が申請時に提出した質問書も同様であり、専らビザ該当性のみが審査の対象となっているのである。また、規則20条も、規則別表第三も、短期滞在から他の資格への変更を申請する際に、「やむを得ない特別の事情」を立証するための資料の提出を殊更に求めていない。さらに、平成9年1月29日に、入国審査官が原告に電話をしたときにも、その質問内容は専らBの所在という、被告がビザ該当性の要件としてとらえている「日本人の配偶者としての活動」に関することのみで、「やむを得ない特別の事情」については、一顧だにしていない。
(3)そして、平成8年中の在留資格変更に関する既済数は全国で7万3656件、うち許可がされているのが7万1173件と実に97パーセントにも上り、この割合からしても、「やむを得ない特別の事情」については、形骸化若しくは実務の運用上は極めて緩やかに解釈されていることが推測できる。
(4)このように、法の趣旨とは全く異なる取扱いがなされているのが現状なのであって、原告に対してのみ、厳格な要件の具備を要するかのような主張をすることは、平等原則に反する。原告についても、他の申請者と同様の基準によるべきである。
(二)「やむを得ない特別の事情」の存在
また、仮に「やむを得ない特別の事情」を被告主張のごとく解するとしても、以下のとおり、本件は右要件に該当する。
すなわち、原告は平成8年4月10日、日本において婚姻届を提出し、同月18日、再度日本に入国して日本の戸籍謄本を入手し、同年5月3日、韓国に帰国し、韓国において正規の婚姻手続を行った。その後、同月15日、原告は日本に入国した。しかるに、同月17日Bが逮捕され、身体を拘束された後、同年8月9日実刑判決を受け横浜刑務所に服役した。
この点、原告としては、在韓日本大使館の職員のアドバイスにより「短期滞在」の資格で入国したものの、Bの身体が拘束されてしまったため、Bに面会・差し入れをしたり、同人の身辺整理をしたり、あるいは同人の財産を管理したり、同人に対する連絡を受け、それをBに伝える等の必要性が生じたのである。その意味で、原告にとって、「短期滞在」のビザで在留中に、新たにビザの変更を必要とするような事情が発生したというべきである。
また、1(原告の主張)(三)で前述したごとく、原告がBの配偶者としての活動をするためには、日本に在留し続けることが必要であり、かつそのことがBにとって何ものにも代え難い、大きな精神的支えとなっているのである。
さらに、原告につき、短期滞在から「日本人の配偶者等」へのビザの変更が認められないとすると、原告はいったん韓国に帰国し、日本人の配偶者として来日するためのビザ認定証明書の交付を受けてから入国しなくてはならない。しかし、右手続をとるには、長い時間と多大な労力が必要である。これにより原告の事務的な負担や、旅費・交通費・通信費等の経済的負担が増加することとなる。
以上の点からすると、本件においては、在留資格変更を認めるべき人道上の必要性が高いというべきである。
(三)そして、本件は「やむを得ない特別の事情」が存する典型例とされる、日本人の婚約者を訪問する目的で短期滞在のビザを取得して本邦に上陸した外国人が本邦在留中にその日本人と正式に結婚し、日本人配偶者との同居生活を営むため引き続き本邦に在留することを希望する場合と、その実質において何ら差異はない。
すなわち、原告は数年にわたり、実質的に日本人であるBの配偶者と同然の生活を送っていた。このような者が婚姻成立後に短期滞在で来日し、その後「日本人の配偶者等」への在留資格変更申請を行う場合と、右の典型例として挙げられている場合を比べれば、法が懸念する適正な出入国管理の実現を阻害するような濫用の可能性が高いのは、むしろ典型例としてあげられている場合の方である。
よって、本件では、「やむを得ない特別の事情」を認めても、何ら法の趣旨に反しない。
(四)以上のとおり、本件においては、法20条3項ただし書の「やむを得ない特別の事情」が存するものと解されるべきである。
3 争点3(本件処分に被告の裁量権の逸脱があるかどうか)について
(被告の主張)
仮に、原告が主張するように、適法な婚姻関係さえ存すれば、あるいは、原告の行っている程度の「活動」があれば、「日本人の配偶者」としてビザが認められるべきであるとしても、次のとおり、在留資格変更における被告の裁量権からして、本件においては、本件申請は認められるべきではない。
(一)国家は、国際慣習法上、外国人を受け入れる義務を負うものではなく、特別の条約ないし取決めがない限り、外国人を自国内に受け入れるかどうか、また、これを受け入れる場合にいかなる条件を付するかを、当該国家が自由に決定することができるのであり、憲法22条も右とその考えを同じくするものである。したがって、憲法上、外国人は我が国に入国する自由を保障されているものでないことはもちろん、在留の権利ないし引き続き本邦に在留することを要求する権利を保障されているものでもない。
法もかかる原則を踏まえ、我が国に在留する外国人のビザの変更について、被告がこれを適当と認めるに足りる相当の理由があると判断した場合に限り許可することとし(法20条1項、3項)、ビザの変更の許否を被告の広範な裁量にかからしめているのである。
そして、法20条3項に規定するビザの変更を適当と認めるに足りる相当の理由が具備されているかどうかについては、外国人に対する出入国及び在留の公正な管理を行う目的である国内の治安と善良な風俗の維持、保健・衛生の確保、労働市場の安定など国益の保持の見地に立って、申請者の申請理由の当否のみならず、当該外国人の在留中の一切の行状、国内の政治・経済・社会等の諸事情、国際情勢、外交関係、国際礼譲など諸般の事情を総合的に勘案して的確に判断されるべきものである。このような多面的専門的知識を要し、かつ、政治的配慮も必要とする判断は、事柄の性質上、国内及び国外の情勢について通暁し、常に出入国管理の衝に当たる被告の裁量にゆだねられているものと解される。
以上のような、法20条3項のビザの変更を適当と認めるに足りる相当の理由の有無についての判断についての被告の裁量権の性質にかんがみると、ビザの変更の許否の判断が違法となるのは、右判断が全く事実の基礎を欠き又は社会通念上著しく妥当性を欠くことが明らかである場合に限られるというべきである。したがって、裁判所は、被告の右判断について、それが違法となるかどうかを審理、判断するに当たっては、右判断が被告の裁量権の行使としてなされたものであることを前提として、その判断の基礎とされた重要な事実に誤認があること等により右判断が全く事実の基礎を欠き、又は事実に対する評価が明白に合理性を欠くこと等により右判断が社会通念に照らして著しく妥当性を欠くことが明らかであるかどうかについて審理し、それらが認められる場合に限り、右判断が裁量権の範囲を超え又はその濫用があったものとして違法であるとすることができるものと解すべきである。
このように、被告は、出入国管理行政上の見地から、当該外国人の申請の理由のみならず、生活状況、家族の状況、犯罪等善良な市民とは認められない行為の有無、国益や外交関係等を総合的に考慮し、広範な裁量権に基づき、ビザの変更の許否を決定することとなるのである。
したがって、仮にビザ該当性が一応認められる場合でも、日本人の配偶者である外国人がその配偶者と別居しているような場合には、仕事や家庭の都合で単身赴任しているとか、病気で入院しているなど、別居していることに社会通念上合理的な理由が認められる場合でない限り、合理的な理由がないのに別居しているという事実を相当の理由があるか否かの判断に当たって重要な消極的要素として考慮することも当然に裁量の範囲内とされるべきである。
(二)これを本件についてみると、被告の本件処分についての判断には事実の基礎を欠くところはなく、また、社会通念上著しく妥当性を欠くところもないのであり、本件処分は適法である。
(原告の主張)
(一)被告は、ビザ該当性が一応認められる場合でも、日本人の配偶者である外国人がその配偶者と別居しているような場合には、社会通念上合理的理由がないのに別居しているという事実を相当の理由があるか否かの判断に当たって重要な消極的要素として考慮することも当然に裁量の範囲内とされるべきであると主張する。
しかし、被告の右主張は失当である。
(二)国家の裁量権と被告の裁量権との混同
被告が法20条1項、3項をもって被告に広範な裁量権が与えられていると主張する根拠は、国家は、国際慣習法上、外国人を受け入れる義務を負うものではなく、特別の条約ないし取決めがない限り、外国人を自国内に受け入れるかどうか、また、これを受け入れる場合にいかなる条件を付するかを、当該国家が自由に決定することができること、憲法上、外国人は、在留の権利ないし引き続き本邦に在留することを要求する権利を保障されているものでもないことにあるとする。
しかし、被告の主張は、国家の裁量権と、日本国の三権のうちの一つにすぎない被告の裁量権とを混同するものである。すなわち、日本国憲法は国会を国権の最高機関と定めており(憲法41条)、国家の裁量権は第一義的に国会に属するものとして、それは立法裁量に現れることになる。その立法裁量の結果として、特定の場合には外国人に入国、在留を許可すべく行政庁に義務づけをすることもあり得るし、また、行政庁に裁量を与えつつこれに制約を課すこともあり得るが、日本国憲法の精神及び法律による行政の原則からすれば、何らの法律に基づかず、行政庁に全くの自由裁量が付与されることなどあり得ない。一定の裁量権が与えられたとしても、その根拠となる法律の目的及び趣旨等によって、羈束裁量となるのである。しかも、後述のとおり、法改正を経て審査基準の明確化が行われた現行法の下においては、法を執行する法務大臣の裁量は更に狭くなっているのである。
したがって、被告の主張は、日本国憲法及び法律による行政の原則を無視した主張であり、国家の裁量権と法務大臣の裁量権とを混同した主張といわざるを得ない。
(三)裁量の制約
さらに、被告は、広範な裁量権の根拠として、法もかかる原則を踏まえ、我が国に在留する外国人のビザの変更について、被告がこれを適当と認めるに足りる相当の理由があると判断した場合に限り許可することとしていること(法20条1項、3項)を挙げている。
しかし、仮に法20条3項が被告の裁量権を付与したものだとしても、当然のことながら、その裁量権は法の目的及び法20条3項自体の趣旨に羈束されるものであって、その限度で認められるにすぎないものである。
そして、法は「出入国の公平な管理」を目的としている(法1条)。この「出入国の公平な管理」とは、具体的には国内の治安や労働市場の安定などの公益と、国際的な公正、妥当性の実現、また憲法、条約、国際慣習、条理等により認められる外国人の正当な利益の保護を意味する。法20条3項の趣旨も、この公益目的と外国人の正当な権利・利益の調整を図ることにあり、同項が仮に被告に裁量権を付与したとしても、右趣旨の範囲内での裁量権が認められるにすぎない。
また、法は平成元年の法改正において、従前審査基準の省令による明示がなく、審査自体が不透明で公正さに欠けると批判されていたものを各ビザに関する審査基準を省令で定めてこれを公布し、もって行政庁の裁量の幅を減少させ、審査の公正を図っているのである。
これらの点から、被告の裁量権は、決して広範なものではなく、この点からも、被告の裁量に関する主張は失当である。
(四)本件における裁量権の逸脱
本件で被告が、いかなる点において裁量を問題とするのか、全く不明確であるが、仮に原告がBと同居していない事実をもってビザ該当性がないと判断したことや、原告については「やむを得ない特別の事情が存在しない」と判断したことが、裁量権の範囲内であるという主張なのであれば、それは誤りである。
右に述べたとおり、被告の裁量は公益目的と外国人の正当な権利・利益の調整を図るという限度において認められる、極めて限定的なものにすぎない。この点を本件について検討するに、原告はBの配偶者として、物心両面において、刑務所に在監中のBを支えており、原告が本邦に在留する必要性が極めて高いことは、前述のとおりである(1(原告の主張)(三)参照)。これに対し、このような原告の正当な利益をはく奪してまで守るべき公益目的がいかなるものであるのか、被告は何ら具体的に主張していないし、そのような公益目的は存在しない。
なお、前述のとおり(1(原告の主張)(三)(1))、原告とCとの関係は本件と直接の関係がない。また、本件申請を行った1996年(平成8年)8月1日の時点では、Bに対する判決の宣告は行われておらず、原告としてはBが早期に釈放されると考えていた。したがって、変更の申請書等に、目的を「同居」と記載したことも、殊更に虚偽の申述をする意図があったわけではないのである。現に、1997年(平成9年)1月29日、入管職員から原告のもとにBの所在場所について初めて問い合わせがあった際に、原告は何ら隠すことなく、Bが横浜刑務所に在監していることを申告している。よって、この点も被告の裁量に逸脱があったことにつき、何ら影響を及ぼすものではない。
このように、本件処分は、何ら合理的な理由がないにもかかわらず、一方的に原告の重大な利益を奪い、社会通念上著しく妥当性を欠く結果を生じさせることになる。よって、被告に裁量権があったとしても、その行使に逸脱があったことは明らかである。
第三 当裁判所の判断
一 争点1(原告が「日本人の配偶者等」というビザに該当するかどうか)について
1(一)本邦に在留する外国人のビザは、法別表第一又は第二に掲げられているとおりであり、別表第一の上欄のビザをもって在留する者は本邦において同表の下欄に掲げる活動を行うことができ、別表第二の上欄のビザをもって在留する者は本邦において同表の下欄に掲げる身分若しくは地位を有する者としての活動を行うことができるとされている(法2条の二第2項)。また、上陸審査においても、入国審査官は、当該外国人の申請に係る我が国において行おうとする活動が虚偽のものではなく、法別表第一の下欄に掲げる活動又は法別表第二の下欄に掲げる身分若しくは地位を有する者としての活動のいずれかに該当することを審査すべきものとされている(法7条1項2号)。これらのことからすると、法は、個々の外国人が我が国で行おうとする具体的活動内容に着目し、一定の在留活動を行おうとする者に対してのみ、その活動内容に応じたビザを与えて、その入国及び在留を認めることとしているものということができ、日本人の配偶者である外国人についてもこのことは同様に妥当するものというべきである。
したがって、日本人と法律上婚姻した外国人が「日本人の配偶者等」のビザによって我が国に在留するためには、単に、当該外国人が日本人と法律上有効な婚姻関係にあるというだけでは不十分であって、さらに、当該外国人が我が国において行おうとする活動が、日本人の配偶者としての活動に該当することが必要であると解するのが相当である。
(二)もっとも、法がその別表第一の上欄に掲げるビザについて、当該下欄に我が国において行うことができる活動を個別具体的に規定しているのと異なり、その別表第二の「日本人の配偶者等」の下欄には、我が国において有する身分又は地位として「日本人の配偶者」と規定するのみで、日本人の配偶者としての活動内容を個別的・具体的に定めておらず、その他その活動の内容及び範囲を具体的に認識できるような規定も見当たらない。したがって、結局は、社会通念に従って、その内容及び範囲を画するほかないというべきである。
この点、婚姻は夫婦としての同居・協力・扶助の活動を中核とするものであることはいうまでもなく(民法752条)、右同居・協力・扶助の関係を前提としこれを維持しつつ行われる諸活動が右に該当することは疑いがない。しかしながら、同居を伴わないすべての活動が配偶者としての活動に該当しないということはできず、例えば、日本人の配偶者である外国人がその配偶者と別居しているとしても、転勤の際に、子供の就学の関係上、夫婦の一方が単身で赴任し、その結果夫婦が別居するに至る場合や、夫婦の一方が病気で入院している場合など、別居の合理的な理由が認められれば、同居の事実がないとしても、社会通念上なお配偶者としての活動と評価できる場合もあり得るのであり、その場合には、かかる外国人について「日本人の配偶者等」のビザを認めることはできるというべきである。これに対し、法律上有効な婚姻関係にあったとしても、婚姻関係が実体を失い、形骸化しているような場合には、当該外国人には、もはや社会通念上日本人の配偶者としての活動を行う余地があるものとはいえないから、かかる外国人配偶者が我が国で行う活動は、日本人の配偶者としての活動というよりも、就労など他の目的を持った活動とみるべきであって、そのような者までを、単に日本人と法律上の婚姻関係にあるというだけで、日本人の配偶者としての活動を行う者に当たるということは困難であり、かかる外国人について、「日本人の配偶者等」のビザを認めることはできないといわざるを得ない。
(三)なお、この点に関し、原告は、日本人と法律上有効な婚姻関係にある外国人であれば、日本人の配偶者という身分を有することのみで、「日本人の配偶者等」のビザを有するものであり、たとえ配偶者である日本人と同居していないなどの事情があったとしても、法律上有効な婚姻関係がある以上、それだけで「日本人の配偶者等」のビザが認められるべきである旨主張する。
しかし、前示のとおり、法は、個々の外国人が我が国で行おうとする活動内容に着目し、一定の在留活動を行おうとする者に対してのみ、その活動内容に応じたビザを与えることとした趣旨と解すべきであり、「日本人の配偶者等」のビザも、当該外国人が、我が国でその身分を有する者としての活動として社会通念上予想される活動を行うことに着目して、これを認めることとしたものとみるのが相当である。
したがって、原告の主張は法の趣旨に合致せず、採用することができない。
2 原告は、「日本人の配偶者等」のビザを認められるためには、日本人の配偶者の身分を有する者としての活動が必要であるとしても、原告の在留は、日本人の配偶者の身分を有する者としての活動のためのものであるといえる旨主張し、被告はこれを争うので、次に原告の日本における在留状況、原告とBの婚姻関係等についてみるに、前記第二の二記載の事実に証拠(原告本人、証人Bのほか、各文末尾掲記の書証)を併せれば、以下の事実が認められる。
(一)原告は、昭和61年3月19日、韓国において、Aと婚姻し、昭和63年3月7日、離婚した。この間、一子をもうけたが、原告は、今回来日するに際して、原告の母親にこの子の養育を託した(乙59の3)。
(二)原告は、昭和63年12月13日、東京入管成田支局入国審査官から、ビザ4-1-4、在留期間30日とする上陸許可を受けて、本邦に上陸した。原告は、平成元年1月10日、東京入管において、在留期間更新許可申請を行い、同日、在留期間90日とする更新許可を受けた。
原告は、同年5月22日、東京入管において、右ビザから、ビザ4-1-16-3への在留資格変更許可申請を行い、同日、ビザ4-1-16-3、在留期間6月とするビザの変更許可を受けた。原告は、同年10月7日、東京入管において、右ビザ4-1-16-3での在留期間更新許可申請を行い、同日、在留期間を3月とする更新許可(在留期限平成2年1月12日)を受けた。
原告は、平成元年1月10日から同年10月9日までの間、明生外語アカデミーに在籍していたが、卒業せずに、中途で退学した(甲70)。
(三)原告とCの婚姻及び原告の出入国状況
(1)原告は、平成元年12月11日、鎌ヶ谷市長に対し、日本人Cとの婚姻届を提出し、同月16日、東京入管において、ビザ4-1-16-3からビザ4-1-16-1への在留資格変更許可申請を行い、同日、ビザ4-1-16-1、在留期間6月とするビザの変更許可を受けた。
原告は、同年12月18日、東京入管において、再入国許可期限を平成2年6月16日とする再入国許可を受けて、平成元年12月31日、新東京国際空港から出国し、平成2年1月10日、右再入国許可により新東京国際空港から入国した。
原告は、平成2年3月12日、鎌ヶ谷市長に対し、Cとの協議離婚届を提出したが、その後、同年4月17日、鎌ヶ谷市長に対し、再度、Cとの婚姻届を提出した。
原告は、同年5月29日、東京入管において、在留期間更新許可申請を行い、同日、在留期間6月とする更新許可を受け、さらに、同年12月14日、東京入管において在留期間更新許可申請を行ったが、被告は、平成3年3月25日、右申請を不許可とした。
その間、原告は、平成2年12月28日、Cとの二回目の離婚届を提出している。
(2)原告とCが結婚している間、原告とCが同居した事実はない。原告は、当時、東京都新宿区ζ(以下「ζ」という。)に居住していた。原告は、韓国のミョンドン(明洞)においてブティックを経営しており、平成元年10月9日に明星外語アカデミーをやめたあとは、韓国から洋服を通関手続をとらずに持ち込んで韓国人のホステスや在日韓国人に洋服を売る仕事をしたり、スナックでアルバイトをしたりして収入を得ていた。洋服を売る仕事では、月に平均して15万円から20万円位の収入があった。
また、原告が、Cと一度離婚して再度婚姻をした理由は、日本に滞在し続けたかったという気持ちがあったからである。
(3)原告は、平成3年8月5日、東京入管において、ビザ「短期滞在」への在留資格変更許可申請を行い、同日、ビザ「短期滞在」、在留期間90日(同年3月16日までの分)とするビザの変更許可を受けた。さらに、原告は、同日、同ビザで、二回分の在留期間更新許可申請を行い、同日、それぞれ在留期間を90日とする更新許可を受けた。これにより、原告の最終の在留期限は平成3年9月12日となった。
(4)右許可日から、平成3年10月18日までの間の原告の出国に係る記録は見当たらない(乙24、41の1、2)。
(四)原告は、平成2年5月30日ころか又は平成3年5月30日ころ、原告がεの公衆電話ボックスにハンドバッグを置き忘れて、それをBが拾ったことからBと知り合った(甲53、54、乙11)。
原告がBと知り合った当時、BはFと婚姻していた(甲一)。
原告とBは、知り合ってから、食事をしたり、電話で連絡を取り合ったりするようになり、原告が韓国に戻っているときにBが韓国に観光旅行に来たり、原告が日本に来たときにBから日本古来の文化を教えてもらうなどして、交際を深めたが、BがFと離婚していなかったこと、原告とBは、年齢が15歳以上も離れており、原告の母親が結婚に反対していたことから、原告とBとの関係は次第に疎遠になっていった(甲53、54)。
(五)その間の原告の出入国状況は、次のとおりである。なお、この間、原告は、Cとの婚姻中から住んでいたζの賃借を継続しており、日本滞在中は、ζに滞在していた。
(1)原告は、平成3年10月18日、新東京国際空港から新規入国(ビザ「短期滞在」、在留期間15日)し、同年11月3日、東京入管成田空港支局において在留期間更新許可(ビザ「短期滞在」、在留期間15日)を受け、同日、新東京国際空港から出国した。
(2)原告は、平成3年11月5日、新東京国際空港から新規入国(ビザ「短期滞在」、在留期間15日)し、同月20日、新東京国際空港から出国した。
(3)原告は、平成3年11月28日、新東京国際空港から新規入国(ビザ「短期滞在」、在留期間15日)し、同年12月13日、新東京国際空港から出国した。
(4)原告は、平成3年12月16日、新東京国際空港から新規入国(ビザ「短期滞在」、在留期間15日)し、同月31日、新東京国際空港から出国した。
(5)原告は、平成4年1月13日、新東京国際空港から新規入国(ビザ「短期滞在」、在留期間15日)し、同月28日、新東京国際空港から出国した。
(6)原告は、平成4年2月12日、新東京国際空港から新規入国(ビザ「短期滞在」、在留期間15日)した。
原告の在留期限は、同年2月27日であったが、右入国日から、次に入国する平成7年7月18日までの間の原告の出国に係る記録は見当たらない(乙24、47)。
(六)原告は、平成5年ころDと知り合い、結婚を前提として、交際を始めた。このころも、原告は、ζの賃借を継続しており、日本に滞在するときには、ζに滞在していた。Dは、原告と結婚した後の生活場所とするため、平成7年1月17日に、現在原告が居住している東京都新宿区α(以下「α」という。)を借りた。しかし、Dは、平成7年4月○日に死亡したため、原告とDは結婚できず、したがって、αで同人と同居するまでに至らなかった。原告は、Dが死亡したことを韓国で知った(甲49、51、53、乙66、67)。
(七)原告は、Dが死亡したころから、Bと再び交際を始めた(甲53、54)。
なお、Bは、平成7年5月11日に韓国へ出国し、同月14日に韓国から帰国している(乙63)。
原告は、平成7年以降、以下のとおり出入国を繰り返している。
(1)原告は、平成7年7月18日、新東京国際空港から新規入国(ビザ「短期滞在」、在留期間15日)し、同年8月2日、新東京国際空港から出国した。
(2)原告は、平成7年8月22日、新東京国際空港から新規入国(ビザ「短期滞在」、在留期間15日)し、同年9月6日、東京入管において在留期間更新許可申請をし、同日、更新許可を受け(ビザ「短期滞在」、在留期間15日)、その後、同月21日、新東京国際空港から出国した。
(3)原告は、平成7年10月3日、新東京国際空港から新規入国(ビザ「短期滞在」、在留期間15日)し、同月18日、新東京国際空港から出国した。
(4)原告は、平成7年10月23日、新東京国際空港から新規入国(ビザ「短期滞在」、在留期間90日)し、同年11月13日、居住地を東京都新宿区αとする外国人登録をし、さらに、平成8年1月23日、東京入管成田空港支局において、在留期間更新許可申請をし、同日、更新許可を受け(ビザ「短期滞在」、在留期間15日)、同日、新東京国際空港から出国した。
(5)原告は、平成8年2月3日、新東京国際空港から新規入国(ビザ「短期滞在」、在留期間15日)し、同月18日、新東京国際空港から出国した。
(6)原告は、平成8年2月21日、新東京国際空港から新規入国(ビザ「短期滞在」、在留期間15日)し、同年3月7日、新東京国際空港から出国した。
(7)原告は、平成8年3月10日、新東京国際空港から新規入国(ビザ「短期滞在」、在留期間15日)し、同月24日、新東京国際空港から出国した。
(八)原告は、この間、αを賃借し続け、日本に滞在中は、αに滞在した。αには、原告とともに、Gが間借りして生活していた。他方、Bは、従前渋谷区に居住していたが、平成8年2月ころから、東京都新宿区β(以下「β」という。)に居住するようになった。そして、原告が日本に滞在し、αに滞在しているときには、Bは、原告のいるαへ行ったこともあったが、Bは、原告が日本に滞在していないときは、αへは行かずに、βに居住し続けた。
(九)原告とBは交際をするうち、婚約をして、原告が、平成8年3月26日、ビザ「短期滞在」、在留期間15日として新東京国際空港から我が国に入国した後、同年4月10日に、原告とBは、世田谷区長に対し、婚姻の届出をした。原告は、同日、新東京国際空港から出国した。なお、Bは、同日までFと婚姻関係にあったものであるが、同日付けで、Fとの協議離婚届を届け出ている。
原告は、韓国においてもBとの婚姻手続をとるべく、平成8年4月12日に韓国においてその旨役所に届けたところ、書類の不備があったため、再度原告は、平成8年4月18日、新東京国際空港から入国し(ビザ「短期滞在」、在留期間15日)、日本の区役所において証明書を入手して、同年5月3日、新東京国際空港から出国し、韓国においてもBとの婚姻手続をとった(甲53)。
(10)原告は、平成8年5月15日、ビザ「短期滞在」、在留期間90日として新東京国際空港から入国した。入国の際、原告は、外国人入国記録の日本滞在先欄に「東京都新宿区α」、日本滞在予定期間欄に「90日」、渡航目的欄には「こんやく」と記載して上陸許可を申請し、ビザ「短期滞在」、在留期間90日とする上陸許可を受けて本邦に上陸した。
右の入国の際、原告は、既にBと婚姻関係にあったのであるから、「日本人の配偶者等」というビザで入国することもできたのであるが、「日本人の配偶者等」というビザでは上陸申請をしなかった。原告は、後から「日本人の配偶者等」へビザを変更するつもりで、「短期滞在」のビザで入国したものである。
(二)Bは、平成8年5月17日、β居宅において、覚せい剤取締法違反の容疑で現行犯逮捕され、同罪名で同年6月5日起訴され、その後、同月28日には、銃砲刀剣類所持等取締法違反で追起訴された。
Bは、同年8月9日、東京地方裁判所において、覚せい剤取締法違反及び銃砲刀剣類所持等取締法違反により懲役4年6月及び罰金100万円の判決の宣告を受け、同判決は、同月24日に確定した。現在、Bは横浜刑務所に服役中である。
Bは、平成8年4月30日、東京都世田谷区γから府中市δへ住民票を異動していたが、その後、Bが勾留中の同年6月13日に、府中市δからαへ住民票が異動された。
原告は、同月14日、新宿区長に対し、居住地を「東京都新宿区α」、世帯主の氏名を「B」、勤務所又は事務所の名称を「なし」と記載して外国人登録申請を行い、同年7月11日に右外国人登録に係る外国人登録証明書が交付された。
(12)原告は、平成8年8月1日、東京入管において、在留資格変更許可申請書の「希望するビザ」欄に「日本人配偶者」、「変更の理由」欄に「同居」、「在日身元保証人又は連絡先」欄の「氏名」、「住所」、「職業」欄にそれぞれ「B、新宿区α、私設秘書、営業」と記載して、Bが身元保証した日付のない身元保証書、Bの住民票、同年6月10日付けで世田谷区長が認証したBの戸籍謄本、同年4月13日付けの原告の韓国の戸籍謄本、Bの平成7年分の給与所得の源泉徴収票、Bの在職証明書、回答を記載した質問書を提出してビザの変更許可申請(本件申請)をした。
(13)原告は、現在、Bへ金銭及び新聞の差し入れを行い、月に一回の割合でBの収監されている横浜刑務所へ面会に行き、Bから頻繁に手紙をもらっている。また、原告は、Bの所持品をαにおいて保管し、Dの名義で賃借していたαの賃貸借契約が平成9年1月17日をもって満了することから、原告を借主として同室の賃貸借契約を更新するなど、αの留守宅の維持管理を行っている。原告は、現在は、αに、原告の弟のHと一緒に住んでいる(甲四の1、2、5ないし7、8ないし11の各1、2、12、13ないし28の各1、2、30ないし47の各1、2、48の1ないし4、50、53、54、58、59、60ないし67の各1、2、68、乙73)。
(14)原告は、日本において、韓国から持ち込んだ洋服を売る仕事を継続していたが、現在では居酒屋でも働いており、洋服を売る仕事の収入は月に15万円から20万円程度、居酒屋からの収入は月に25万円程度である。
また、原告は、新宿でホステスをしていたこともある。
3 以上の事実からすれば、原告がBと有効に婚姻したこと、原告とBは正式に同居したことはないが、αにおいて同居する予定であったこと、原告が平成8年5月15日に入国してからわずか2日後の同月17日にBが覚せい剤取締法違反により逮捕され、その後覚せい剤取締法違反等の罪で有罪判決を受けて横浜刑務所に収監されたため、原告とBは同居してないこと、Bが横浜刑務所に収監されているため、原告はBから扶養を受けられないこと、原告は現在、Bへ新聞等の差し入れを行い、月に一回の割合で面会に行っていること、Bは原告に対し頻繁に手紙を書いていること、原告は、Bの所持品をαで保管し、αの留守宅を守っていることが認められる。
そうすると、原告とBが同居をすることができず、原告がBに扶養されることができないとしても、それは、Bが覚せい剤取締法違反等の罪で逮捕・勾留され、実刑判決を受けて刑務所に収監されたからであって、原告とBが同居しないこと等については合理的な理由があるものといわざるを得ない。右のように、原告は、Bに新聞等を差し入れ、面会に行き、手紙等をもらい、また、留守宅を守ることは、夫婦としての協力の関係ということができるのであって、かかる活動が社会通念上配偶者としての活動に該当しないということはできない。
この点、被告は、日本人の配偶者等としての活動の重要な要件の一つである同居が実現していない以上、夫婦共同生活の実現は不可能又は著しく困難であるから、原告には日本人の配偶者等としてのビザ該当性がないと主張する。しかし、前述したように、同居を伴わないすべての活動が配偶者としての活動に該当しないということはできず、例えば、日本人の配偶者である外国人がその配偶者と別居しているとしても、転勤の際に、子供の就学の関係上、夫婦の一方が単身で赴任し、その結果夫婦が別居するに至る場合や、夫婦の一方が病気で入院している場合など、別居の合理的な理由が認められれば、同居の事実がないとしても、社会通念上なお配偶者としての活動と評価できる場合もあり得るのであり、その場合には、かかる外国人について「日本人の配偶者等」のビザを認めることができるというべきであるから、被告の主張は失当である。
また、被告は、右のような原告の行為は原告に「日本人の配偶者等」のビザを与えなければできないような活動ではないし、原告自身が行わなければならない活動でもないと主張するが、前示のとおり「日本人の配偶者等」のビザに該当する活動は、社会通念に従ってその範囲を画する必要があるところ、仮に「日本人の配偶者等」のビザがなくても事実上行える活動であったとしても、それが社会通念上配偶者としての活動である場合には、「日本人の配偶者等」のビザ該当性があるといえるのである。しかして、刑務所に収監された者のため、差し入れ、面会等を行い、留守宅を守ることは、その配偶者、その他の親族等が行うのが通常であり、その者とゆかりのない他人が、右のような活動を奉仕として行うことは一般に考えにくいのであって、右のような活動は、社会通念上配偶者としての活動であるというべきであり、被告の主張は失当であるといわざるを得ない。
したがって、原告が、「日本人の配偶者等」のビザに該当するものではないということはできない。
二 争点3(本件処分に被告の裁量権の逸脱があるかどうか)について
そこで、進んで、本件処分に被告の裁量権の逸脱又はその濫用があるかどうかについて検討する。
1 法20条3項によると、被告はビザの変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができるものとされているところ、ビザの変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるかどうかの判断は、国内の治安と善良の風俗の維持、保健・衛生の確保、労働市場の安定等の国益の保持の見地に立って、在留資格変更申請の理由の当否のみならず、当該外国人の在留中の一切の行状や国内外の政治・経済・社会等の情勢等、諸般の事情を総合的にしんしゃくして行われる被告の裁量にゆだねられているのであって、このような被告の裁量の性質にかんがみると、この点に関する被告の判断は、事実の基礎を全く欠き又は社会通念上著しく妥当性を欠くことが明らかである場合に限り、裁量権の範囲を逸脱し又はその濫用があったものとして、違法となると解すべきである。
2 そこで、前記一2で認定した事実に基づき、本件において、ビザの変更を適当と認めるに足りる相当の理由がないとした被告の判断に裁量権の逸脱又はその濫用があったかどうかについて検討する。
(一)前記一2で認定した事実によると、原告は頻繁に入出国を繰り返し、しかも、出国記録がないものが存在すること、右の出国記録の不存在について、原告から合理的な説明がなされていないこと、原告は、短期滞在のビザで滞在中、居酒屋で働いたり、韓国から洋服を通関手続きをとらずに持ちこんで販売するなどの営業活動を行っており、資格外活動を継続していたことが認められる。しかも、原告がDと交際していた平成5年から平成7年4月ころまで、原告はビザを有していなかったのであるから、その期間中、原告は我が国に不法残留ないし不法入国した事実があると推認せざるを得ない。
(二)また、前記一2で認定した事実によると、原告とCは平成元年12月11日に婚姻し、平成2年3月12日に離婚し、その後同年4月17日に再び婚姻し、同年12月28日に二回目の離婚をしているが、その間、原告とCは一度も同居したことがなく、原告がCとの離婚後わずか一か月後に再び同人と婚姻した理由は、日本に滞在し続けたかったという気持ちがあったからというのである。
また、証拠(乙59の1、60の1、62の1、64、65の1ないし3)によれば、原告がCと一回目に婚姻した際の婚姻届に記載されている連絡先電話番号(○○○○-○○-○○○○番)は、婚姻届が提出された平成元年12月11日当時I名義で設置されており、設置場所も神奈川県相模原市という原告らの住所地とされた千葉県鎌ヶ谷市とは遠く離れたところであること、右婚姻届に証人として署名押印のあるJ及びKは、該当する人物が住所地である横浜市泉区役所、戸塚区役所の戸籍謄本、除籍謄本、住民票、住民票除票のいずれによっても見当たらないこと、右婚姻届に証人として署名押印のあるJは、本籍地とされている千葉県千葉市花見川区役所保管の記録によっても該当する人物が見当たらないこと、原告とCの一回目の離婚届に証人として署名押印のあるLは、住所地及び本籍地とされている千葉県千葉市花見川区役所保管の記録によっても該当する人物が見当たらないこと、原告とCの第二回目の離婚届に証人として署名押印のあるMは、その住所地及び本籍地とされている千葉県印旛郡白井町役場保管の記録によっても該当する人物が見当たらないことが認められる。
さらに、C自身も東京入管入国審査官から受けた事情聴取において、原告との婚姻は真正なものではないとの趣旨の供述をしている(乙58)のであって、右の各事実に照らすならば、原告とCとの婚姻は、原告が日本に滞在すべくビザを得るための方便としてなされた偽装の婚姻であると認めるほかはない。
(三)前記一2で認定したとおり、Bは原告が韓国にいる間は専らβで生活していたものであり、原告とBが結婚する約3か月前である平成8年2月ころ、原告がαに住んでいるにもかかわらず、Bは、βに移転していることなどからして、原告とBが、婚姻前、事実上の夫婦関係ないし同せい状態にあったとは認められないところであり、また、婚姻後においても、原告が今回入国してからわずか2日後にBが逮捕され、その後現在に至るまで逮捕・勾留、収監され、そのため、Bと原告は同居して夫婦共同生活を送るに至らず今日に至っているものである。
そして、Bは服役中なので原告と同居し原告を扶養することはできない状況にあるところ、Bは、原告から金銭や新聞の差し入れをしてもらい、原告と手紙のやりとりをし、原告が月一回程度面会に来てくれることが心の支えになっており、仮出所を認められるためには身元引受人が必要であるが、身元引受人になってくれるのは原告をおいてほかにないようにいうが(証人B)、Bは前議員の私設秘書をし、あるいは株式会社御所野の相談役として建設関係の折衝等の仕事をしていたというのであり(証人B)、仕事その他の関係での知人は多くいるものと推認され、差し入れをし、身元引受人になってくれる人が原告の他に存在しないとは到底認められないし、また、既に認定したところから明らかなとおり、Bは、懲役4年6月の刑に処せられ収監されてから既に3年以上が経過しており、刑期を終えあるいは仮出所するのもそれほど遠い先のことではないから、原告と面会できないなどは受忍できる範囲内のことと考えられる。
他方、原告は従前から何度も日本と韓国の間を行き来しており、Bが出所後に再度ビザを得て日本に入国して夫婦生活を営むことは可能であると考えられ、原告は、韓国においてブティックを経営しており、また、原告には14歳位の子供が韓国にいることからすれば、原告がどうしても日本に在留しなければならないような事情はなく、原告について、ビザの変更を認めなければ酷な結果になるとは断じ難い。さらに、Bの留守宅についても、原告は元々出入国を繰り返しながら、ζやαを継続して賃借していたものであり、しかも、現在、αには、原告とともに、原告の弟のHが居住しているのであるから、原告についてビザの変更を認めなければ、Bの留守宅を維持管理することができないということはない。
(四)右の諸事情、とりわけ右に指摘した原告の本邦における在留・活動に法に抵触する部分があったこと、虚偽の婚姻によりビザを得ていたこと、Bが服役中であり、現在においては通常夫婦間で行われる同居・協力・扶助の活動ができないこと等にかんがみると、本件において、ビザの変更を適当と認めるに足りる相当の理由がないとした被告の判断が事実の基礎を欠き又は社会通念上著しく妥当性を欠くものとは認められない。
したがって、本件処分において、被告の裁量権の逸脱又はその濫用があるということはできない。
3 以上からすると、原告についてビザの変更を適当と認めるに足りる相当な理由がなかったとの被告の判断に違法はなく、その余の点について判断するまでもなく、本件処分は適法である。
第四 結論
よって、原告の本件請求は理由がないから、これを棄却することとし、訴訟費用の負担について、行政事件訴訟法7条、民事訴訟法61条を適用して主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第三部
裁判長裁判官 青 栁 馨
裁判官 谷 口 豊
裁判官 加 藤 聡
松村総合法務事務所
ビザ総合サポートセンター
DNA ローカス大阪オフィス
〒540-0012
大阪市中央区谷町2 丁目5-4
エフベースラドルフ1102
TEL:06-6949-8551
FAX:06-6949-8552