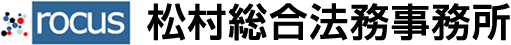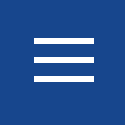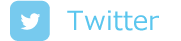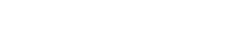判例集2019.02.15
退去強制令書発付処分取消等請求事件
判例集2019.02.15
東京地方裁判所平成19年3月23日 判決
主 文
1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。
事実及び理由
第1 請求
1 被告法務大臣が平成16年1月20日付けで原告らに対してした出入国管理及び難民認定法49条1項に基づく原告らの異議の申出は理由がない旨の裁決をいずれも取り消す。
2 被告東京入国管理局主任審査官が平成16年1月28日付けで原告らに対してした退去強制令書発付処分をいずれも取り消す。
第2 事案の概要
本件は,被告法務大臣が,平成16年1月20日付けで,出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。ただし,条文を伴う場合は,特記しない限り,平成16年法律第73号による改正前のものをいう。)49条1項に基づく原告らの異議の申出は理由がない旨の裁決を行い,続いて,被告東京入国管理局主任審査官が,同各裁決に基づいて原告らに対し,平成16年1月28日付けで退去強制令書の発付処分を行ったところ,原告らが,自分らに在留特別許可を与えないでした上記各裁決には裁量権の範囲の逸脱・濫用があること等を理由に,上記各裁決及びこれに基づく上記各退去強制令書の発付処分は違法であるとして,上記各裁決及び各処分の取消しを求めている事案である。
1 前提事実(当事者間に争いのない事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
(1)原告Aの身上及び在留状況等
ア 原告Aは,1975年(昭和50年)9月1日,トルコ共和国(以下「トルコ」という。)のアディアマン県ギョルバシュ郡において出生したトルコ国籍を有する外国人である(乙1)。
イ 原告Aは,1992年(平成4年)10月21日,トルコのガジアンテップにおいて旅券の発給を受けた(乙1)。
ウ 原告Aは,平成5年2月12日,シンガポールから新東京国際空港(以下「成田空港」という。)に到着し,東京入国管理局(以下「東京入管」という。)成田空港支局入国審査官に対し,外国人入国記録の渡航目的の欄に「HOLIDAY(観光)」,日本滞在予定期間の欄に「2weeks(2週間)」と記載して上陸申請を行い,同入国審査官から,入管法別表第1に規定するビザ「短期滞在」及び在留期間「90日」とする上陸許可の証印を受け,本邦に上陸した(乙1,2,4)。
エ 原告Aは,本邦上陸後,ビザの変更又は在留期間の更新の許可申請を行うことなく,在留期限である平成5年5月13日を超えて本邦に不法残留するに至った(乙1,4)。
オ 原告Aは,平成13年9月3日,原告Bとの婚姻届を,埼玉県鳩ヶ谷市長当てに提出した(乙105)。
(2)原告Aに対する退去強制手続
ア 平成12年12月20日,東京入管入国警備官は,原告Aを入管法24条4号ロ(不法残留)該当容疑で立件した(乙5)。
イ 東京入管入国警備官は,原告Aについて違反調査を行った結果,同原告が入管法24条4号ロに該当すると疑うに足りる相当の理由があるとして,平成13年9月11日,被告東京入管主任審査官(以下「被告主任審査官」という。)から収容令書の発付を受け,同月13日,同令書を執行して東京入管収容場に収容し,同日,同原告を入管法24条4号ロ該当容疑者として東京入管入国審査官に引き渡した(乙7,8)。
被告主任審査官は,同日,原告Aに対し仮放免を許可した(乙9)。
ウ 東京入管入国審査官は,平成13年9月13日及び同月21日,原告Aについて違反審査をし,その結果,同日,同原告が入管法24条4号ロに該当する旨の認定を行い,同原告にこれを通知したところ,同原告は,同日,口頭審理を請求した(乙10から12まで)。
エ 東京入管特別審理官は,平成15年9月22日,原告Aについて口頭審理を行い,その結果,同日,東京入管入国審査官による上記ウの認定は誤りがない旨判定し,同原告にこれを通知したところ,同原告は,同日,被告法務大臣に対し,異議の申出をした(乙13から15まで)。
オ 被告法務大臣は,平成16年1月20日,原告Aに対し,上記エの異議申出については,理由がない旨裁決し,同裁決の通知を受けた被告主任審査官は,同月28日,同原告に同裁決を告知するとともに,退去強制令書を発付し,同日,同原告を東京入管収容場に収容した(乙16から18まで)。
カ 被告主任審査官は,平成16年5月25日,原告Aに対し仮放免を許可した(乙19)。
(3)原告Bの身上及び在留状況等
ア 原告Bは,1966年(昭和41年)8月31日にフィリピン共和国(以下「フィリピン」という。)のマニラで出生したフィリピン国籍を有する外国人である(乙29)。
イ 原告Bは,1996年(平成8年)2月17日,マニラにおいて旅券の発給を受けた(乙37)。
ウ 原告Bは,平成8年11月26日,マニラから成田空港に到着し,東京入管成田空港支局入国審査官に対し,外国人入国記録の渡航目的の欄に「TO VISIT FIANCE AND SISTER(婚約者及び姉訪問)」,日本滞在予定期間の欄に「90days(90日)」と記載して上陸申請を行い,同入国審査官から,入管法別表第1に規定するビザ「短期滞在」及び在留期間「90日」とする上陸許可の証印を受け,本邦に上陸した(乙37,38)。
エ 原告Bは,平成9年2月21日,東京入管さいたま出張所で,在留期間更新申請をし,同年3月7日,在留期間を15日とする在留期間更新許可を受けた(乙37)。
オ 原告Bは,その後,ビザの変更又は在留期間の更新の許可申請を行うことなく,在留期限である平成9年3月11日を超えて本邦に不法残留した(乙37)。
(4)原告Bに対する退去強制手続
ア 平成13年6月22日,東京入管入国警備官は,原告Bを入管法24条4号ロ(不法残留)該当容疑で立件した(乙40)。
イ 東京入管入国警備官は,原告Bについて違反調査を行った結果,同原告が入管法24条4号ロに該当すると疑うに足りる相当の理由があるとして,平成13年9月11日,被告主任審査官から収容令書の発付を受け,同月13日,同令書を執行して東京入管収容場に収容し,同日,同原告を入管法24条4号ロ該当容疑者として東京入管入国審査官に引き渡した。
被告主任審査官は,同日,原告Bに対し仮放免を許可した。
(以上につき,乙42から44まで)
ウ 東京入管入国審査官は,平成13年9月13日及び同月21日,原告Bについて違反審査をし,その結果,同日,同原告が入管法24条4号ロに該当する旨の認定を行い,同原告にこれを通知したところ,同原告は,同日,口頭審理を請求した(乙45から47まで)。
エ 東京入管特別審理官は,平成15年9月22日及び同年10月21日,原告Bについて口頭審理を行い,その結果,同日,東京入管入国審査官による上記ウの認定は誤りがない旨判定し,同原告にこれを通知したところ,同原告は,同日,被告法務大臣に対し,異議の申出をした(乙48から51まで)。
オ 被告法務大臣は,平成16年1月20日,原告Bに対し上記エの異議申出については,理由がない旨裁決し,同裁決の通知を受けた被告主任審査官は,同月28日,同原告に同裁決を告知するとともに,退去強制令書を発付し,同日,同原告を東京入管収容場に収容した(乙16,52,53)。
カ 被告主任審査官は,平成16年3月18日,原告Bについて仮放免を許可した(乙54)。
(5)原告Cの身上及び在留状況等
ア 原告Cは,平成13年1月30日,原告Bの子として本邦で出生したフィリピン国籍を有する外国人である(乙60から62まで)。
イ 原告Cは,入管法22条の2第1項に基づき,ビザを有することなく本邦に在留することができる期間である平成13年3月31日を徒過した後も,引き続き本邦に残留した(乙60から62まで)。
(6)原告Cに対する退去強制手続について
ア 平成13年6月22日,東京入管入国警備官は,原告Cを入管法24条7号(不法残留)該当容疑で立件した(乙63)。
イ 東京入管入国警備官は,原告Cについて違反調査を行った結果,同原告が入管法24条7号に該当すると疑うに足りる相当の理由があるとして,平成13年9月11日,被告主任審査官から収容令書の発付を受け,同月13日,同令書を執行して東京入管収容所に収容し,同日,同原告を入管法24条7号該当容疑者として東京入管入国審査官に引き渡した(乙64,65)。
被告主任審査官は,同日,原告Cについて仮放免を許可した(乙66)。
ウ 東京入管入国審査官は,平成13年9月13日及び同月21日,原告Cについて違反審査をし,その結果,同日,同原告が入管法24条7号に該当する旨の認定を行い,原告Cの法定代理人である原告B(以下,後記オまでの原告Bの立場について同じ。)にこれを通知したところ,原告Bは,同日,原告Cに係る口頭審理を請求した(乙46,67,68)。
エ 東京入管特別審理官は,平成15年9月22日及び同年10月21日,原告Cについて口頭審理を行い,その結果,同日,東京入管入国審査官による上記ウの認定は誤りがない旨判定し,原告Bにこれを通知したところ,同原告は,同日,被告法務大臣に対し,原告Cに係る異議の申出をした(乙48,49,69,70)。
オ 被告法務大臣は,平成16年1月20日,原告Cに係る上記エの異議申出は理由がない旨裁決し,同裁決の通知を受けた被告主任審査官は,同年1月28日,原告Bに同裁決を告知するとともに,原告Cに対して退去強制令書を発付し,同日,同原告を東京入管収容場に収容した(乙16,71,72)。
カ 被告主任審査官は,平成16年1月28日,原告Cについて仮放免を許可した(乙73)。
2 争点
本件における主要な争点は, 入管法49条1項に基づく原告ら3名の異議の申出は理由がない旨の各裁決(以下「本件各裁決」という。)及びこれらに基づいてされた原告ら3名に対する各退去強制令書の発付処分(以下「本件各退令発付処分」という。)が適法か否か,特に,本件各裁決において,原告らに在留特別許可を付与しなかった点に裁量権の範囲の逸脱・濫用があったか否かという点にあり ,これらについて摘示すべき当事者の主張は,後記第3「争点に対する判断」において記載するとおりである。
第3 争点に対する判断
1 本件各裁決の適法性を巡る判断の枠組み
(1)入管法は,24条各号掲記の退去強制事由のいずれかに該当すると思料される外国人の審査等の手続として,特別審理官が,口頭審理の結果,外国人が同法24条各号掲記の退去強制事由のいずれかに該当するとの入国審査官の認定に誤りがないと判定した場合,当該外国人は法務大臣に対し異議の申出ができると規定している(同法49条1項)。そして,法務大臣がその異議の申出に理由があるかどうかを裁決するに当たっては,たとえ当該外国人について同法24条各号掲記の退去強制事由が認められ,異議の申出が理由がないと認める場合においても,当該外国人が同法50条1項各号掲記の事由のいずれかに該当するときは,その者の在留を特別に許可することができるとされており(同条1項柱書),この許可が与えられた場合,同法49条4項の適用については,異議の申出が理由がある旨の裁決とみなすとされ,その旨の通知を受けた主任審査官は直ちに当該外国人を放免しなければならないとされている(同法50条3項)。
(2)原告A及び同Bは入管法24条4号ロの,原告Cは同条7号の,それぞれ強制退去事由に該当する者である(前記前提事実(第2の1)(1)エ,(3)オ及び(5)イ)から,前記前提事実に記載した本件の経緯に照らし,本件各裁決の適法性に関しては,原告らが同法50条1項3号に該当するか否かが専ら問題となるものである。
(3)ところで,国際慣習法上,国家は外国人を受け入れる義務を負うものではなく,特別の条約がない限り,外国人を自国内に受け入れるかどうか,また,これを受け入れる場合にいかなる条件を付するかは,専ら当該国家の立法政策にゆだねられており,当該国家が自由に決定することができるものとされているところであって,我が国の憲法上も,外国人に対し,我が国に入国する自由又は在留する権利(又は引き続き在留することを要求し得る権利)を保障したり,我が国が入国又は在留を許容すべきことを義務付けたりしている規定は存在しない。
また,入管法50条1項3号も,「その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき」と規定するだけであって,考慮すべき事項を掲げるなど,その判断を羈束するような定めは置かれていない。そして,こうした判断の対象となる外国人は,同法24条各号が規定する退去強制事由のいずれかに該当し,既に本来的には我が国から退去を強制されるべき地位にある。さらに,外国人の出入国管理は,国内の治安と善良な風俗の維持,保健・衛生の確保,労働市場の安定等の国益の保持を目的として行われるものであって,その性質上,広く情報を収集し,その分析を踏まえて,時宜に応じた的確な判断を行うことが必要であり,高度な政治的判断を要求される場合もあり得るところである。
(4)以上の点を総合考慮すれば,在留特別許可を付与するか否かの判断は,法務大臣の極めて広範な裁量にゆだねられているのであって,法務大臣は,我が国の国益を保持し出入国管理の公正を図る観点から,当該外国人の在留状況,特別に在留を求める理由の当否のみならず,国内の政治・経済・社会の諸事情,国際情勢,外交関係,国際礼譲等の諸般の事情を総合的に勘案してその許否を判断する裁量権を与えられているというべきである。そして,在留特別許可を付与するか否かに係る法務大臣の判断が違法となるのは,その判断が全く事実の基礎を欠き,又は社会通念上著しく妥当性を欠くことが明らかであるなど,法務大臣に与えられた裁量権の範囲を逸脱し,又はそれを濫用した場合に限られるものと解するのが相当である。
2 本件各裁決における裁量権の範囲の逸脱又は濫用の有無
(1)上記1で述べたところに従い,法務大臣が本件各裁決をするに当たり,その裁量権の範囲の逸脱又は濫用に相当するような事情があったか否かという観点から,本件各裁決の適法性について検討を加えることとする。
(2)前記前提事実並びに原告A及び同B各本人尋問の結果並びに各項掲記の証拠によれば,次の事実を認めることができる。
ア 原告A及び同Bの本国での生活歴及び原告Cを含めた本邦での在留状況等
(ア)a 原告Aは,トルコのクルド人の村であるヒュリエット村で,6人兄弟(4男2女)の第2子として出生した。父は,羊・牛の牧畜を行っており,原告Aもこれを手伝いながら,学校に通っていたが,3年通学した後,学校をやめ,皿洗いの仕事などをしていた。やがて,原告Aは,軍に徴兵される年齢に達し,健康診断の通知が来たものの,徴兵を逃れるため,トルコから出国することを決意した。なお,原告Aは,徴兵を忌避した理由として,兵役に就いた場合,同胞であるクルド人との戦闘に駆り出されることを挙げている。(以上につき,甲85,乙11)
b 原告Aは,1992年(平成4年)10月,ブローカーを通じて親が手配した旅券や航空券を利用して,トルコを出国し来日を果たした。来日後は,日本で稼働していたいとこに稼働先を紹介してもらい,長野県伊那市の解体業者の社員となって約4年間作業を行い収入を得て,社員寮で生活していた。さらに,平成10年には,クルド人が多く住んでいるという話を聞いて埼玉県川口市に引っ越し,そこで鳶の仕事をするようになった。しかし,平成14年10月,仕事中のけがで椎間板ヘルニアとなり,仕事ができない状態になったため退職した。なお,当該疾病により労災認定を受け,約1年間,月額25万円程度の補償金の給付を得ていた。本国の家族に対しては,これまで父あてに,平成8年と平成13年の2回にわたり,合計1万9000米ドルの送金を行っている。(以上につき,甲85,乙11)
(イ)a 原告Bは,フィリピンのマニラで,5人兄弟(2男3女)の第2子として出生した。原告Bは,大学を卒業後,コンピュータ・オペレーターとして働いていたが,姉のDが日本人男性と結婚し,本邦で生活していたことから,姉夫婦の招きで,平成2年3月に初めて来日し,約2週間滞在した。そのときの経験から,日本でプログラマーとして働きたいと考え始め,平成3年7月,「短期滞在」のビザで在留期間を90日とする上陸許可を受けて来日した。このとき,ビザの変更の許可を得ようとしたもののうまくいかず,結局,上記在留期間が徒過した後,ビザの変更,在留期間の更新の許可を受けないまま,本邦に滞在を続け,工員やクリーニング店従業員等として稼働していたが,平成6年11月,入管法違反容疑で逮捕され,東京入管主任審査官から退去強制令書を発付され,その執行を受けて,成田空港からフィリピンに向けて送還された。この間の事情について,原告Bは,姉の夫から「短期滞在の資格で入国後,資格変更を行えばよい。」という説明を鵜呑みにしたが,実際には資格変更は容易でなく,家族に「日本で勉強して日本の会社で働く」旨説明していたため,帰国するのが恥ずかしく,そのまま本邦での滞在を続けたとしている。(以上につき,甲86,91,乙41,46)
b 原告Bは,1995年(平成7年)5月ころ,本国でEという日本人男性と知り合い,親しく交際するようになった。原告Bは,Eと結婚の約束をした上,同人が身元保証人となって,平成8年11月に再来日を果たしたものの,同人の家族の反対に遭い,結局,同人とは結婚することができず,別れるに至った。原告Bが,平成9年3月,在留期間の延長を申請したところ,15日間しか延長が認められなかったが,同期限を過ぎた後も本邦での滞在を続け,フィリピン人が集まるキリスト教教会の仕事を手伝うなどし,同年12月以降は,プラスチック製品工場で稼働した。この間の事情について,原告Bは,家族にはEと結婚すると説明して本国を出国しており,結婚がだめになったと言い出すのも恥ずかしいことから,帰国せず,滞在を続けることを決意したとしている。(以上につき,甲86,91,乙41,46)
(ウ)原告Aと同Bは,平成10年春ころ初めて出会い,原告Bの友人の紹介を通じて交際を始めた。原告Bは,稼働していた工場に入国管理局の調査が入るといううわさを聞いて,その工場での仕事をやめ,フィリピン人の友人,姉の家を転々としていたところ,友人と同じアパートに原告Aが住んでおり,その友人と原告Aとが知り合いだったこともあって,原告Bが同Aの部屋を貸してもらうこともあった。
平成10年7月ころ,原告Bの父が死亡したときに原告Aに慰めてもらったこと等から,両名は親しい間柄となり,平成11年2月ころからは,同居して生活するようになった。原告Bは同居後しばらくは稼働せず,同Aの収入で生活していたが,平成12年5月からは,新たにタイル工場での稼働を始めた。そのころ,原告Bは妊娠し,平成13年6月に,原告Cを出産してから後は仕事を辞めた。原告Cの出生を契機として,原告Aと同Bは,結婚することを決意し,必要書類を入手した上,平成13年9月に,鳩ヶ谷市役所及びフィリピン大使館に婚姻の届出をした。なお,原告Aが兵役を逃れている状態にあったことから,トルコ大使館への届出はしなかった。また,原告Cの出生についても,川口市役所及びフィリピン大使館には届け出ているが,トルコ大使館への届出はされていない。
(以上につき,甲85,86,乙11,46)
(エ)a 原告Aは,平成12年12月に難民認定申請を行っており,その際に,東京入管において入管法違反容疑で立件され,退去強制の手続が開始された。平成14年4月には,上記申請に係る難民不認定処分を受け,これに対してした異議申出も平成15年1月16日付けで棄却されている。また,同年3月に2回目の難民認定申請を行っているが,同年8月に難民不認定処分を受け,これに対してした異議申出も同年12月12日付けで棄却されている。さらに,平成16年1月に3回目の難民申請をしている。(以上につき,乙4,20から28まで)
b 原告B及び同Cは,平成13年6月に東京入管に出頭して入管法違反の事実を申告した(原告Cについては,同Bが手続を代理したもの。以下同じ。)ことから,入管法違反容疑で立件され,退去強制の手続が開始された。原告B及び同Cは,平成15年6月に難民認定申請を行っているが,平成16年1月に難民不認定処分を受け,これに対してした異議申出も同年3月23日付けで棄却されている。また,原告B及び同Cは,同年5月に2回目の難民認定申請を行っている。(以上につき,乙40,56から59まで,62,74から77まで,103,104)
(オ)原告らは,平成16年1月28日,いずれも退去強制令書により収容されたが,原告Cについてのみ,即日,仮放免が許可され,埼玉県上尾市の児童相談所に入所した。姉Dは同月30日原告Cを自宅に引き取り,原告Bの仮放免が許可されるまで,同原告及び原告Aとの面会に同行するなどした。原告Bが仮放免された後も,原告Bと同Cは,姉夫婦方にとどまり,原告Aが仮放免されてから,家族3人で自宅に戻った。原告Cは,収容によって両親と引き離されたことに強い衝撃を受けており,児童相談所にいる間やD方へ移動した当初はほとんど食事を取らない状態が続いて,体重もいったん7キログラム減少し,平成16年12月の時点でも,精神的抑うつ状態にあると診断されている。もっとも,その時点において,発育状況に異常はなく,運動障害も存せず,栄養状態は良好であるとも診断されている。(以上につき,甲77,79,91)
(カ)仮放免された後,原告Aは,クルディスタン日本友好協会のボランティア活動等を行っており,同Bは,在日フィリピン人支援のボランティア団体及びキリスト教教会でのボランティア活動等を行っている。また,原告Cは,幼稚園に通園している。
原告ら家族内の会話は,日本語で行っており,原告A及び同Cは,タガログ語及び英語を話すことができず,原告B及び同Cは,トルコ語及びクルド語を話すことができない。
(以上につき,甲85,86)
(キ)トルコには,原告Aの父母及び計5名の兄弟妹が暮らしており,父は畜産業を営み,兄は教職に就いている。すぐ下の弟は兵役に就いた後,平成13年1月,本邦への入国を試みたが許可されず,本国へ帰国している。他の弟妹は学校に通っている。フィリピンには,原告Bの母と弟2人がいるが,弟らは既に独立している。また,妹は,現在ロンドンに在住している。(以上につき,乙6,56)
イ トルコの一般情勢等
(ア)トルコは,ムスタファ・ケマル(アタテュルク)を大統領として1923年10月29日に共和国として独立し,イスラム教を基礎とするスルタン・カリフ制を廃止する一方,欧州列強勢力に対抗して独立を守るため,トルコ民族の統一を強調する政策をとった(甲27,乙80)。
(イ)1970年代にテロが多発して治安が悪化し,1980年9月12日,ケナン・エヴレン将軍が無血クーデターで政権を掌握すると,1982年11月7日には治安維持や国民の一体性を重視した内容の憲法であるトルコ共和国憲法(以下,その後改正されたものを含め,「共和国憲法」という。)が制定された(甲27,乙80)。
(ウ)アブドゥラ・オジャラン率いるクルド労働者党(PKK)は,1984年以来,トルコ南東部における分離独立闘争を行い,政府軍と激しく衝突した。1987年には,南東部の10県が非常統治下におかれ,その範囲は漸次縮小していったものの,2県の非常事態が最後に解かれたのは2002年11月であった。オジャランは,1998年10月,滞在していたシリアから強制送還され,反逆罪によって訴追されて,1999年6月には,死刑判決を受けたが,2002年8月の死刑廃止を受けて,仮釈放のない終身刑に変更された。この間,オジャランは和平の呼び掛けを行い,1999年8月には,これを受けてPKKは,軍事行動を停止することを確認し,政府とPKK間の武力闘争は事実上終結したとされる。2000年10月には,トルコ政府は,PKKに対する戦いを成功裏に終了したと発表した。(以上につき,乙81)
(エ)トルコにおいては,1987年4月に欧州連合(以下「EU」という。)加盟を申請し,特に2001年以降,その目的達成のため改革が進められており,その改革の一環として,共和国憲法も,1990年代初頭から治安の安定とともに,1987年,1993年,1995年,1999年(2回),2001年と逐次改正されている。2001年10月の憲法改正では,法律で禁止された言語の使用禁止条項が削除されるなど,思想,信条,表現の自由が憲法上より明確に保障されるように改められ,2002年8月には,クルド語の教育や放送を解禁する法案を含む14改革法案がトルコ国会において一括可決されるに至った。こうした改革は,民主主義を強化し,人権を保護するための基盤の多くが得られたと評価されている。もっとも,欧州委員会は,上記改革を経た後も,なお基本的権利と自由の十全な享受に対する重大な制限があるなどとして,トルコがEU加盟の政治的基準を十分には満たしていないと結論づけた。また,上記のような改正を経た現行憲法においても,表現の自由に関する規定において,国家における国土と民族から成る不可分の全体性の保護の目的による制限を留保している。(以上につき,乙80,82の1から3まで)
(オ)2002年12月以降,正義発展党(AKP)のリーダーであるエルドアン首相の下でEU加盟を目指して更に改革が続行され,同首相は,2003年3月の国会演説において,人権を世界的レベルに引き上げるため,EUの規範を含めてあらゆる国際的規範に合致し,個人の権利と自由を優先する新しい共和国憲法を構想し,EUに加盟することを最重要目標の一つとする政権プログラムを示している(乙80)。
(カ)トルコでは,テロ取締法(1991年4月成立。ただし,以下の規定は,本件各裁決当時のもの)が制定されており,次のような内容が規定されている(甲4,乙107,108)。
a 1条は,テロリズムの定義として,「憲法に定める共和国の基本政体及び政治的,法的,経済的,社会的制度の変革,国家及び領土の統一性の毀損,トルコの国家及び共和制体の存続を危うくし,国家の統治権を弱め,破壊し,あるいは奪取しようとし,基本的権利及び自由を侵害し,あるいは国家の内部的及び国際的安全,公共の秩序,厚生を威力,実力行使,暴行,脅迫のいずれかの方法により損なうことを目的とする団体に属する1人又は数名の者により行なわれる一切の行為をいうものとする。」と定めている。
b 5条は,犯罪が,同法1条に定義されたテロリスト犯罪として行われた場合には,一般の法定刑の1.5倍に加重することを定めている。
c 7条は,テロリスト団体を結成した者及びその団体の活動を組織し,主導した者は,5年以上10年以下の懲役及び3億トルコ・リラ以上5億トルコ・リラ以下の重罰金に処せられること,テロリスト団体に参加した者は,3年以上5年以下の懲役及び1億トルコ・リラ以上3億トルコ・リラ以下の重罰金に処せられること,テロリスト団体の構成員をほう助し,あるいはこれらの団体の宣伝を行った者は,1年以上5年以下の懲役及び5千万トルコ・リラ以上1億トルコ・リラ以下の重罰金に処せられること(一定の場合には,その2倍の刑とされること)をそれぞれ定めている。
d 8条(1995年改正後のもの)は,トルコ共和国及びその領土の不可分性を破壊することを目的とする書面又は口頭による宣伝,集会,デモを禁止し,そのような活動を指揮した者を,1年以上3年以下の懲役及び1億トルコ・リラ以上3億トルコ・リラ以下の罰金とすることを定めている。
e 13条は,同法違反行為に対して懲役刑が定められている場合,それを罰金刑その他の刑に転換し,又はその執行を猶予することはできないことを定めている。
f 14条は,同法違反行為又は行為者に関する情報を提供した者の氏名などは,原則として開示されないことを定め,15条は,テロリズム犯罪防止のための職務に従事している警察,情報機関などの職員がその職務の遂行中の行為に関して訴追された場合,3人以下の弁護人を付することができるものとし,その費用は所属する機関が負担することなどをそれぞれ定めている。
(キ)トルコでは,共和国憲法で拷問の禁止が定められており,拷問を処罰する刑法上の規定も存在する。しかし,1993年11月に作成された国連拷問禁止委員会の報告書,1992年12月に発表された欧州拷問等禁止委員会の公式声明では,トルコ国内では,拷問の実行が存在し,その申立ての数と内容に照らせば,それが系統的に実行されていると結論づけている。また,アメリカ国務省の人権状況に関する国別レポート(2001年)では,治安部隊による拷問,虐待は恒常的・広範囲にわたり行われており,政治犯罪の容疑で拘束された者のほとんど,また,一般犯罪の容疑で拘束された者もしばしば拷問・虐待の申立てをしている一方,拷問・虐待を犯した治安部隊メンバーの起訴,処罰はまれであると報告している。政府は,拷問が行われている事実を認めているが,それが組織的に行われていることは否定しており,警察の虐待に対する起訴件数は増加しているとされる。警察官や治安部隊のメンバーを起訴した事件において,一審等で無罪判決が言い渡された場合でも,上級審等で10年を超える懲役刑を言い渡された事案等,実行者が重い刑罰に処せられた事案も報告されている。(以上につき,甲18,乙80)
(ク)トルコは,政教分離国家であり,共和国憲法で信仰の自由と礼拝の自由が定められている。しかし,人口の98パーセントから99パーセントをイスラム教徒が占めており,一部のキリスト教徒とバハーイ教徒について布教活動や無断集会が申し立てられたかどで,拘留を含めて,社会や政府から嫌がらせを受けてきたとされる。もっとも,2002年8月の改革パッケージには,イスラム教以外の少数派宗教に対してより大きな自由を与える措置が含まれている。(以上につき,乙80)
ウ トルコにおけるクルド人の状況等
(ア)クルド民族とは,主にトルコ,イラク,イランにまたがる地域に居住し,クルド語を母語とする民族であるとされており,トルコにおいては6500万人余りの総人口のうち,概算1200から1500万人を占めているとされる(甲27,45,乙79)。
(イ)1991年には,トルコ国内においてクルド語を使用することを禁止する根拠となっていた法律が廃止され,以来,トルコ国内では,クルド語の出版物や音楽著作物が合法的に流通し,ラジオ,テレビ放送についてもクルド語による放送が一定の範囲内で事実上認められるようになった。また,2002年8月には,クルド語を含む少数民族言語の放送が法律で承認されることになった。もっとも,共和国憲法には,トルコ語以外のいかなる言語も,教育機関においてトルコ国民の母語として教育されてはならない旨の規定が置かれており,クルド語での教育は初等教育を終えた者に対して限られた時限でしか行うことができず,また,クルド語での放送時間も限定されているほか,トルコ語の通訳を付すことが要求されている。(以上につき,甲29,32,乙80,81)。
(ウ)英国内務省の2003年版報告書では,トルコの国内におけるクルド人は,クルド人であることのみを理由に迫害を受けるおそれがあるとは認められない旨が報告されている一方,公的または政治的にクルド民族のアイデンティティを主張するクルド人は,特に,南東部において,嫌がらせ,不当な扱い,迫害等を受ける危険を冒すことになると指摘されている(乙80)。
エ トルコにおける兵役義務と忌避者への扱いについて
トルコには,義務兵役制度があり,良心的参戦拒否の規定は設けられていない。徴兵忌避者は,裁判により3年を限度として拘置することで罰せられ,徴兵忌避の平均的な刑罰は1年であり,20歳未満であれば実刑判決は約3か月とされる。外国に住んでいる者についても,正当な理由なく3か月内にトルコに戻るようにとの命令に従わない場合には,トルコ国籍を取り消されることがあり,公民権は内閣により剥奪されるが,その復活を当局に申請することができるし,兵役を終えれば,その申請は受け入れられるものとされる。また,2004年7月に法務省入国管理局担当者が行った調査によれば,兵役に就く前の忌避の初犯については,自由刑が科される例はほとんどなく,50ドル程度の罰金で終わる例がほとんどであるとされており,海外で働いている者については,38歳まで兵役が免除され,38歳を過ぎた場合には,兵役に就くよう官報に公示し,3か月以内にこれに従わない場合には国籍が取り消される扱いであるとされている。さらに,PKKとの紛争が激化したような場合は,南東部出身の新兵を紛争地域に配属しないような特別措置を施しており,クルド人が兵役に応じた場合でも,PKKとの戦闘を行う可能性は極めて低いものとされている。(以上につき,甲45,46,乙80,97,127)
オ フィリピンの一般情勢等
(ア)1990年の調査によれば,フィリピンでは,ローマ・カトリック教徒が85パーセントを超えるなどキリスト教徒が人口の大半を占め,イスラム教徒の割合は約4.6パーセントにとどまっているとされるが,7パーセントに達するとの推計もある。イスラム教徒は,その勢力が多数派を占めるミンダナオ島の西部5州に集中しているものの,ルソン島の首都マニラ及びパラワンにも相当数のイスラム教徒のコミュニティが形成されている。(以上につき,乙101)
(イ)イスラム教徒に対しては,民族的,文化的な差別が存在し,イスラム教徒は教育レベルが低いという偏見があるとの指摘がある一方,家族,種族及び地縁等を重視するフィリピンの文化がイスラム教徒の就職や資産へのアクセスに障壁をもたらしているという指摘もあり,2005年の調査結果によれば,イスラム教徒に偏見を持つ者の割合は地理的場所と年齢との相関が強く,ミンダナオ住民はイスラム教徒をテロリストとみなす傾向が強いが,首都圏住民,ルソン島住民は偏見の割合が最も小さく,54歳以上の年齢の者は偏見が強いが,35歳以下の者の偏見は弱いと報告されている(甲120,乙101)。
(ウ)フィリピンでは,憲法上,宗教の自由が定められており,2001年には,大統領がラマダンの最終日を公休日と宣言したほか,2002年には,成立には至らなかったものの,イスラム教の祝日を国家の祝日とする法案が提出されるなどの動きもあった(乙101)。
(エ)1960年代には,ミンダナオ島のイスラム教徒によってモロ民族解放戦線(MNLF)が組織され,分離独立運動を展開したことから,キリスト教徒との対立が激化した。中央政府は1972年に戒厳令を布告して独立運動を非合法化し,武力鎮圧に努めたが,事態は悪化して内戦状態に至った。その後,MNLFから分派独立したモロ・イスラム解放戦線(MILF)が,爆弾テロ,外国人誘拐等,様々なテロ活動を行っており,時の政権との間では和平交渉の機会が持たれてきたが,停戦合意と戦闘の再開とを繰り返しており,現在までに全面的な解決をみるには至っていない。また,1991年に結成され,ミンダナオ島を中心にテロ活動を繰り返していたイスラム教徒過激派組織アブ・サヤフ・グループ(ASG)は,海外テロ組織との関係が疑われており,MILFとも共闘関係にあるとされるが,2001年のいわゆるアメリカ同時多発テロ以降,政府は,ASGに対する攻勢を強め,アメリカ軍と協力して,ミンダナオ島での掃討作戦を展開し,その勢力を減少させた。(以上につき,甲48,乙101,130の1・2,乙132)
(オ)上記(エ)のASGへの掃討作戦が展開される中で,ミンダナオ島周辺においては,多くのイスラム教徒に対する恣意的な拘禁,拷問等が行われていると報道されている。マニラにおいても,テロ事件が発生・発覚した場合,イスラム教徒のコミュニティが差別的に捜索の対象とされており,イスラム教徒が令状なく身柄を拘束された事例があったとの報道もある。(以上につき,甲50から54まで,114から118まで)
カ 原告らのトルコ又はフィリピンへの入国可能性
(ア)トルコ国籍法によれば,トルコ人と婚姻した外国人,及びトルコ人の子として出生した者は,トルコ国籍を取得することが可能であり,トルコ人が日本から強制送還される際,内務省の許可を得て,ともにトルコに入国することができるものとされている。また,いったん自国に強制送還された場合であっても,婚姻関係及び親子関係を証明する書類を提示することにより,自国内のトルコの在外公館からトルコへの入国ビザを取得することもできる。(以上につき,乙134)
(イ)フィリピンの移民法は,受入れに数量的制限のある「割当て移民」と,そのような制限のない「非割当て移民」の二つの類型を定めているところ,フィリピン人の配偶者で当該フィリピン人に同伴する目的を有する者は「非割当て移民」に分類され,数量的制限を受けることなく移民として同国に入国することができるものとされている(乙135)。
(3)原告らは,本件各裁決が,原告らに憲法上保障された幸福追求権,居住の自由及び人身の自由を侵害するものであるから,憲法13条,18条,22条及び31条に反しており,違法であると主張している。
しかし,前記1で述べたとおり,国際慣習法上,特別の条約の定めがない限り,国家は外国人を受け入れるかどうかについて,自由に決定することができるものとされており,我が国の憲法上も,外国人に入国する自由又は在留する権利等を保障したり,入国又は在留を許容すべきことを義務付けた規定は存在しないのであって,原告らの主張する幸福追求権,居住の自由及び人身の自由についても,在留が認められる外国人に対して,その範囲内で一定の保障が及ぶべきことはともかくとして,憲法上の人権を根拠にして,本邦に在留する権利を導くことはできないと解される。
この点に関して,原告らは,原告A及び同Bは本邦に5年以上平穏に生活しており,また,原告Cは,本邦で出生し,一貫して本邦内で生活を送っているものであって,日本社会との結び付きは極めて強いものがあるから,「定住外国人」としての地位を有しており,また,原告Aは,兵役忌避者として迫害を受けるおそれがあることから難民の地位にあるとした上,こうした地位にある者については,一般外国人と異なり,本件各裁決によって達成される利益が,原告らの被侵害利益を上回るものであることが明白であることを被告らにおいて主張立証すべきであると主張している。
しかし,不法滞在を続けた場合に,生活の必要その他の事情から,日本社会との様々な結び付きが生ずることは当然のことであり,その期間が長くなればなるほど,その結び付きが強まることも一般的に起こり得ることといえるが,そうした状況は不法滞在という違法状態の上に築かれたものであることは否定できないのであって,それだけで法的保護の対象となり得るものではない。少なくとも,外国人の在留を認めるか否かについて法務大臣が行使する裁量権の範囲を制限するような,特別な基準を設ける根拠にはなり得ないというべきである。なお,原告Aがトルコにおいて迫害を受けるおそれがあり難民に該当するか否かについては,項を改めて(後記(5))検討する。
(4)原告らは,市民的及び政治的権利に関する国際規約(以下「自由権規約」という。)23条において,家族の統合が保護されていること,同17条において,家族に対する恣意的・不法な干渉が禁じられ,こうした干渉からの保護が規定されていること,同24条において,児童が人種その他いかなる差別もなく,未成年者としての地位に必要とされる保護の措置であって家族,社会及び国による措置についての権利を有する旨規定されていることを挙げ,本件各裁決は,これらの条約の規定に違反するものであって違法である旨主張している。
しかし,一方で,自由権規約12条は,自国民及び外国人の出国の自由と,自国民の帰国の自由を保障しながら,合法的にいずれかの国の領域内にいる者に対し,移動の自由及び居住の自由について規定するにとどまり,外国人一般の入国及び在留の権利を保障していないこと,同13条において,合法的にこの規約の領域内にいる外国人は,法律に基づいて行われた決定によってのみ当該領域から追放することができる旨を規定しており,外国人に対して法律に基づく退去強制手続を行うことを容認していると解されることからすれば,自由権規約が前記1で述べた国際慣習法上の原則に変更を加えたものとみることはできない。
さらに,原告らは,児童の権利に関する条約3条1において,児童に関するすべての措置をとるに当たっては,児童の最善の利益が主として考慮されるものとすると規定されていること,同9条1において,児童がその父母の意思に反してその父母から分離されないことの確保を定めていることを挙げ,本件各裁決は,これらの条約の規定にも違反するものであって違法である旨主張している。
しかし,児童の権利に関する条約9条4が,児童の父母の一方又は双方からの分離が,締約国がとった退去強制等の措置に基づく場合には,要請に応じ,父母又は児童等に対し,家族のうち不在となっている者の所在に関する重要な情報を提供する旨を規定していることからすれば,退去強制の結果として児童が父母から分離されることを禁じる趣旨とみることはできず,やはり,同条約は,前記1で述べた国際慣習法上の原則に変更を加えたものではないとみるべきである。
確かに,家族の統合や未成年者が家族からの保護を受ける権利,児童の最善の利益や親子が分離されないことの確保は,一般論として,尊重に値する普遍的な価値を有しているものといえ,法務大臣が在留特別許可を付与するかどうかを判断する際に考慮されるべき要素になり得るとまではいえるものの,上に述べたことからすれば,上記各条約の規定が直接法務大臣の判断を規制するものとまではいえない。在留特別許可を付与しなかったために,上記利益が損なわれる結果が生じたとしても,それだけでは裁量権の範囲を逸脱又は濫用したことにはならないと解するのが相当である。
(5)原告Aは,トルコ本国において兵役を忌避していることを理由に処罰され,市民権を剥奪されるおそれがあり,この点は,難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)1条A(2)の定める「迫害」になり得るものであること,さらに,兵役拒否が真摯に抱いている確信に基づく場合には,「政治的意見を理由とする迫害」になり得ると主張している。そして,分離主義運動と関係するか,その疑いがあるクルド人兵役忌避者の虐待の報告があるとした上,原告Aの兵役忌避の理由は,クルド民族の自治・独立を志向しており,思想的に共感するPKKゲリラと戦わなければならず,武器を持たないクルド人に対しても銃を向けなければならなくなるおそれがあったことにあると主張し,こうした理由で兵役を拒否した原告Aを処罰することは「政治的意見を理由とする迫害」に該当することから,同原告をそのおそれのあるトルコに送還することは難民条約に違反するものと主張している。
しかしながら,トルコ国内における政府軍とPKKとの戦闘状況は,前記2(2)イ(ウ)で,トルコにおける兵役義務者の扱いは,前記2(2)エで,それぞれみたとおりであり,そもそも,原告Aの年齢,境遇に照らすと,兵役を忌避したという理由により,刑罰が科されることや,国籍を剥奪されること等の著しい不利益を受けると認めるだけの確たる根拠はなく,処罰されたとしてもせいぜい少額の罰金等の軽微な罰則で終わることが予想されるにすぎない。その点をおくとしても,実際にPKKとの紛争状態にあった南東部出身の新兵が紛争地域に配備される可能性は小さなものであったというのであるから,たとえ原告Aが,PKKその他クルド人と対峙することを避けたいとの信条を有していたとしても,それだけをもって兵役拒否の正当な理由とすることはできないといわざるを得ない。詰まるところ,原告Aにおいて,兵役拒否を理由として処罰されるおそれがあるとしても,これをもって「政治的意見を理由とする迫害」に当たるものとはいえない。また,クルド民族その他の兵役を忌避するグループが民族又は宗教的背景により特別に扱われているかについては,そのような事実はない旨の報告があるだけであって(乙97),仮に,分離主義運動との関係を疑われるような者について,過去に虐待の報告例があったとしても,そうした特別な事情のない原告Aについては,虐待を受けるおそれがあるとみるべき根拠はないものである。
したがって,トルコに送還することにより原告Aが「政治的理由による迫害」を受けるおそれがあるとはいえず,本件各裁決が難民条約に違反するものともいえない。
(6)さらに,前記前提事実及び前記(2)の認定事実を基に,原告らの主張を踏まえながら,原告らに在留特別許可を付与しなかったことが裁量権の範囲の逸脱又は濫用に当たるか否かについて検討する。
ア 原告らは,在留特別許可を付与すべき事情として,原告A及び同Bは長期間本邦に滞在しており,日本社会に溶け込んでいること,原告Aは来日後真面目に勤労しており,多くの日本人と親密な交友関係を結んでいること,原告Bもボランティア活動を行うなど地域社会に積極的に貢献していること,いずれも入管法違反以外に前科前歴がないこと,原告Cは日本で生まれ育ったもので,日本語以外は話せず,日本の文化に慣れ親しんでいること,原告ら家族は深い愛情で結ばれており,原告Cの成長上,両親と一緒に生活することが必要であること,本件各退令発付処分により原告A及び同Bが収容された際,原告Cは大きなショックを受けて抑うつ状態に陥っており,その不安を取り除くためには両親が常にそばにいることが必要であること等を主張している。
そして,原告らは,送還された本国での状況に関して,トルコにおいては,原告Aは,兵役忌避により処罰される可能性が高く,そうでない場合も兵役に就かなければならないこと,原告Aの両親がイスラム教徒でない原告Bとの結婚に反対していること,原告Bがキリスト教の信仰を維持するのも困難であること,原告Cの名前がクルド人の女性テロリストの名前に由来することから,その使用は許されず,名前の変更を迫られること,フィリピンにおいては,イスラム教徒が迫害されてきた歴史があり,偏見・差別も根強いものがあり,イスラム教徒である原告Aはテロリストの嫌疑を受けて根拠なく拘束・拷問・処刑されるおそれがあること,原告Bの家族もイスラム教徒であることを理由に原告Aとの結婚に反対していること,失業率が高く,英語,タガログ語の話せない原告Aが就職できる可能性は皆無であること,以上のような事情から,原告らは,トルコ及びフィリピンのいずれにおいても,原告らが生活を維持することが難しく,家族の統合を回復することも困難である旨主張している。
イ しかしながら,前記(3)でも述べたとおり, 原告A及び同Bが長期間本邦に滞在し,日本社会と強い結び付きを築いていることは,不法残留という違法状態の継続によって生じた結果であるし,本邦で就労していることも,それ自体は不法就労にほかならず,積極的に在留を許可すべき事情とすることはできない 。また,原告らに入管法違反以外の前科前歴がない点についても,それ自体としては積極的に考慮すべき事情とはいい難い上,特に原告Bについては,過去に入管法違反により退去強制の措置を受けてから3年足らずしか経過していない時期に,家族の反対に遭って日本人男性との結婚がかなわなかったという事情があるとはいえ,専ら自己の体面を保ちたいという理由から再度不法残留の行動に出たというのであって,順法精神に欠けるとのそしりを免れないものである。さらに, 原告Cについては,本件各裁決当時,3歳となる直前であって,トルコ・フィリピンいずれにおいても,新たな環境に順応することにも,現地の言語を習得することにもさほどの困難が伴うものとは考えられない し,原告ら 家族の結び付きが強いとする点も家族一般の事情を超えた特別な事情があるとまでは認められない 。原告Cについては,抑うつ状態にあるとの診断があり,その原因は両親が収容され,そのいずれからも監護が受けられなくなったことによるショックによることがうかがわれるが,それ以外の健康状態・発育状況に特に問題はないとされており,本件各裁決により, 父親と一時的な別離を強いられたとしても,母親である原告Bの監護の下に置かれる限り,原告Cの心身に重大な影響が生ずると認めるに足りる証拠はない 。
次に,原告Aがトルコに帰国した場合に兵役拒否により処罰される可能性については,前記(5)で述べたとおりであり,長期の自由刑が科されるおそれは小さなものにとどまる上,原告Aが兵役を拒否した理由として述べるところは必ずしも正当なものとはいえず,難民該当性も認め難いことからすれば, 仮に同原告に自由刑が科されることにより,原告B及び同Cとの共同生活が一時的に維持できない結果になるとしても,それは,原告Aが国民としての義務を果たさず,法律にのっとった制裁を受けることを意味するものであるから,そのことをもって,原告らに本邦での在留を特別に許可することを根拠づける積極的な事情とみるのは適当ではない 。ましてや,原告Aが本来の兵役を務めることにより,原告B及び同Cと一時的に離れ離れになることそれ自体は,在留特別許可の判断に当たって考慮すべき事情であるとはいい難い。原告Cの名前がクルド人の女性テロリストの名前であるとする点は,仮にそうであったとしても,その名前を使用することに不都合があり,実際に名前の変更を強いられることになるという事実にそう証拠は原告Aの供述しかなく,それだけではかかる事実をそのまま認め難いし,原告Cが送還されるとすればその送還先はフィリピンであって,原告らが家族として共同生活を送る場所の選択肢はトルコに限られるものでもない。いずれにせよ,そうした不利益が生じ得るとしても甘受すべきか又は回避することが可能な事情にすぎない。
そして,トルコ及びフィリピン各国の自国民の外国人配偶者に対する扱いは,前記(2)カのとおりであって,原告B及び同Cが,フィリピンからトルコへ入国することにも,逆に,原告Aが,トルコからフィリピンへ入国することにも,大きな困難が伴うとは認め難い。原告らは,トルコにおけるキリスト教の信仰の維持の困難さや,フィリピンでのイスラム教徒に対する根強い偏見・差別の存在,いずれの家族も相手の宗教を理由にして結婚に反対していること等の事情を挙げるが, 両国の憲法で宗教の自由は保障されており,事実上少数派としての不利益を被る場合があるとしても,信仰を維持することや社会生活を営むことそれ自体に著しい困難が伴うと認めるに足りる証拠はない。 フィリピンにおいては,イスラム教徒が根拠なくテロリストとしての嫌疑をかけられ拘束されたなどの報道もされているが,弾圧に類するようなイスラム教徒に対する当局の活動が行われているのは,主として,ミンダナオ島等のイスラム教徒組織との紛争地域であり,マニラでもそうした事件の報道はあるものの日常的にそれが生じている様子もうかがえないところであるから,原告Aが同Bの出身地であるマニラで共同生活を送ることに特段の支障があるとは認められない。このほか,原告らは,フィリピンでは,失業率が高く,英語・タガログ語の話せない原告Aが職に就ける可能性はないなどと主張するが,同原告は,日本語の特別な教育を受けることなく,本邦へ入国して長年就労を続けており,現在では,家族との会話も専ら日本語を用いているというのであって,原告Bが母国語であるタガログ語及び英語を不自由なく使いこなせることからすれば, 原告Aが言語を習得して職を見つけることは,一定の困難を伴うことは想定されるが,結局はその努力次第といえるのであって,少なくとも,原告Bと助け合えば,生活の基盤を築くことに著しい困難があるとまではいえない 。
(7)以上みてきたような事情を総合するならば,本件各裁決においては,原告らがそれぞれの国籍国に帰還して生活すること,帰還後, いずれかが他方の国籍国に移動して,家族として再度の統合を図ることに,著しい困難があるとは認められず,未成年者の家族からの保護,児童の最善の利益,親子が分離されないことの確保の要請にも一定限度でこたえているものと評価することができる。そうであるとすれば,前記(4)で述べたとおり,法務大臣が在留特別許可を付与するかどうかを判断する際,家族の統合や未成年者の家族からの保護,児童の最善の利益,親子が分離されないことの確保の要請が,考慮要素となり得ることを踏まえたとしても,本件各裁決において,その判断が事実の基礎を欠いたとか,社会通念上著しく妥当性を欠くことが明らかであるとはいえず,裁量権の範囲を逸脱又は濫用するものとはいえないから,これを違法ということはできない。
なお,原告らは,本件各裁決の比例原則違反をいうが,上記のとおり,送還先の国籍国での生活の維持や家族としての再度の統合に著しい困難があるとまでは認められないことからすれば, 比例原則を裁量違反の考慮要素の一つとするにしても,法務大臣に付与された裁量の違反をもたらすような比例原則違反があるとは認められない。 また,原告らは,外国人夫婦にそれぞれ不法残留・不法入国の入管法違反があり,夫と妻子が別国籍であって,子が本邦で出生した場合に,出国後の家族の統合が困難であることを理由に在留特別許可が与えられた事例があるとして,原告らに同様の許可が与えられないのは平等原則違反であるとも主張するが, 国籍国との結び付きや家族の統合の困難性,その他,在留特別許可を付与すべきかどうかを判断するに当たって考慮すべき事情は事案ごとに異なるのであって,原告らの指摘するような事案があったからといって,上記裁量違反をもたらすような平等原則違反があるとも認められないところである。
第4 結論
以上によれば,本件各裁決は違法ということはできないし,これらに基づいてされた本件各 退令発付処分にも違法はない というべきである。
よって,原告らの請求は,いずれも理由がないからこれを棄却し,訴訟費用の負担について,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条,65条1項本文を適用して,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第2部
裁判長裁判官 大 門 匡
裁判官 吉 田 徹
裁判官 小 島 清 二
松村総合法務事務所
ビザ総合サポートセンター
DNA ローカス大阪オフィス
〒540-0012
大阪市中央区谷町2 丁目5-4
エフベースラドルフ1102
TEL:06-6949-8551
FAX:06-6949-8552